SPEC社の新しいプリメインアンプ、RSA-888を試聴することが出来た。SPECは2010年に発足した国産ニューカマー。PIONEERに在籍していたエンジニアが独立して作り上げたメーカーだ。過去に何回かそのモデルに接したことがあり、いずれも良い印象を受けている。このRSA-888は同社の中では最廉価の製品だ。とはいっても定価は約30万円で、一般世間的な認識からすれば決して安くはない。だが、それでもマニア御用達メーカーと思われがちな同社が、このような価格帯の製品を出してくれたことは有り難いと思う。
試聴に使われたCDプレーヤーはACCUPHASEのDP-550、スピーカーがフィンランドのPENAUDIO社のSARA Sと、イタリアのFRANCO SERBLINのAccordoである。SARA Sは今回初めて聴くが、以前共通のユニットを使用した同モデルの下位製品であるCENYAには接したことがあり、音の傾向はだいたい見当が付いている。Accordoは過去に何度も聴いており、そのたびにその美音に感心したものだ。

さて、実際に聴いてみた。さほど高能率とも言えない両スピーカーを音圧の不足をまったく感じさせずに駆動している。欧米製のアンプで鳴らした時のような色艶やコクこそ抑えめだが、その代わりにスッキリと伸びたレンジ感と、特定帯域での強調感もないバランスの良さ、そして十分に及第点に達しているような解像度と情報量が確保されている。
ただし、残念ながら他社の同価格帯のアンプと聴き比べることは出来ず、本機がこのセグメントでどういう位置を占めるのか分からなかった。機会があれば改めて聴き直してみたい。
なお、このRSA-888には外見上、大きな特徴がある。それは横幅が35cmしかないコンパクト・サイズである点だ。私はかねてより単品のオーディオ・コンポーネントの無意味なデカさに疑問を持っていた。スピーカーこそ小振りのものが数多く出回るようになってきたが、アンプ類は十年一日のごとく重厚長大なフルサイズが幅を利かせている。

昔ながらのマニア連中は“大きいことは良いことだ”という古臭い価値観に固執しているのかもしれないが、世の中のトレンドはとっくの昔に軽薄短小省エネに振られている。その意味でこのRSA-888のエクステリアは、注目に値すると思う。
さらに面白いのは、このアンプにはいわゆる“足”が付いていないことだ。筐体を支えるための、通常は底板の四隅に配置されているゴム製(あるいは金属製)の部品が、本機には存在しない。ならば何でボディを支えるのかというと、木製のサイドパネルなのだ。このパネルは左右の前方が下に盛り上がっていて、その2点と後方のインシュレーター(これも木製)1点の計3点で接地する。
今までも3点接地のアンプ類はあったが、底板の中央近くに接地スパイクが配備されているため、安定性に欠けている例が散見されていた。対してRSA-888は、底面をしっかりと隅とサイドでホールドするため、堅牢度は抜群である。アンプ作りの新たな方法論として注目されよう。
試聴に使われたCDプレーヤーはACCUPHASEのDP-550、スピーカーがフィンランドのPENAUDIO社のSARA Sと、イタリアのFRANCO SERBLINのAccordoである。SARA Sは今回初めて聴くが、以前共通のユニットを使用した同モデルの下位製品であるCENYAには接したことがあり、音の傾向はだいたい見当が付いている。Accordoは過去に何度も聴いており、そのたびにその美音に感心したものだ。

さて、実際に聴いてみた。さほど高能率とも言えない両スピーカーを音圧の不足をまったく感じさせずに駆動している。欧米製のアンプで鳴らした時のような色艶やコクこそ抑えめだが、その代わりにスッキリと伸びたレンジ感と、特定帯域での強調感もないバランスの良さ、そして十分に及第点に達しているような解像度と情報量が確保されている。
ただし、残念ながら他社の同価格帯のアンプと聴き比べることは出来ず、本機がこのセグメントでどういう位置を占めるのか分からなかった。機会があれば改めて聴き直してみたい。
なお、このRSA-888には外見上、大きな特徴がある。それは横幅が35cmしかないコンパクト・サイズである点だ。私はかねてより単品のオーディオ・コンポーネントの無意味なデカさに疑問を持っていた。スピーカーこそ小振りのものが数多く出回るようになってきたが、アンプ類は十年一日のごとく重厚長大なフルサイズが幅を利かせている。

昔ながらのマニア連中は“大きいことは良いことだ”という古臭い価値観に固執しているのかもしれないが、世の中のトレンドはとっくの昔に軽薄短小省エネに振られている。その意味でこのRSA-888のエクステリアは、注目に値すると思う。
さらに面白いのは、このアンプにはいわゆる“足”が付いていないことだ。筐体を支えるための、通常は底板の四隅に配置されているゴム製(あるいは金属製)の部品が、本機には存在しない。ならば何でボディを支えるのかというと、木製のサイドパネルなのだ。このパネルは左右の前方が下に盛り上がっていて、その2点と後方のインシュレーター(これも木製)1点の計3点で接地する。
今までも3点接地のアンプ類はあったが、底板の中央近くに接地スパイクが配備されているため、安定性に欠けている例が散見されていた。対してRSA-888は、底面をしっかりと隅とサイドでホールドするため、堅牢度は抜群である。アンプ作りの新たな方法論として注目されよう。










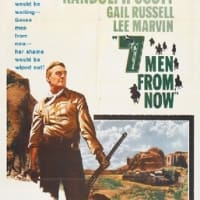















お目当てはRSA-888とRSP301でした
お出迎えのスピーカーは802ノーチラスでした
「鳴らないスピーカー」としてJ○X115と双璧と言われる、いや冗談ですが・・・
そこでアルバム「Equilibrium」とヘルゲ・リエンのテイク・ファイブ、さらに、つじあやのさんの「プカプカ」というヘビーローテーションをやってまいりました
RSA-888はガラスの仮面風に言うと「恐ろしい子」でした
あんな小さなD級が、ノーチラスを堂々と鳴らしております
そもそもとても手が届きませんが、ノーチラスはアンプの駆動力がないと鳴らないことは聞いたことがあります
RSP301の効果も実感しました
「Equilibrium」のギター曲は、スピーカー離れのすごくいい曲ばかりですが、つけた状態ですと、見事にスピーカーの存在が消えていたのに、外したとたん、スピーカーから音が鳴っているのがまるわかりになってしまいました
(ノーチラスってとんでもないスピーカーですね・・・)
テイク・ファイブでは「恐怖のピアノ連弾」を鳴らしきりました。ある評論家先生がRSA-888のことを「最も高速なアンプ」と評したそうですが、さもありなんです
「プカプカ」では、見事にスピーカーの外に鳥を飛ばし、天井を前から後ろにカラスを飛ばしました
D級として考えた場合、SoulnoteやN-MODEを超えたかなあ、もしかしてと思いました
ちなみに今日はお茶の水でアキュフェーズの新しいセパレートのデモをやっていたので、こっちも聞いてきました
・・・感想は、アキュフェーズって外連味があるんだなと思いました
スピーカーは奇しくもノーチラスの805でした
このスピーカーで音場音像を造ってしまうアキュフェーズも、値段なりのことがあるな、と思いましたが、RSA-888+RSP-301でいいじゃないの、プアオーディオ的には。と確信しました
・・・・で、そうですか。RSA-888は802を存分に鳴らしていましたか。かなりの駆動力ですね。まさにアンプ界のベビーギャングですね。こういう小振りで高性能の製品がもっと世に出てくれば良いと思います。重厚長大路線では、今の若年層はオーディオに見向きもしませんよ。
SOULNOTEはハイエンド路線に舵を切り、Nmodeは新製品開発の目処が付いていないらしいということで、ちょっと寂しい思いをしています。確かにSOULNOTEが提供するFANDAMENTALブランドのモデルは優れ物ですが、値段はもちろん使い勝手も含めて万人にアピール出来る製品とは思えません。
SPECはCDプレーヤーの開発も検討しているとのことで、楽しみに待ちたいと思います。
それでは、今後ともどうかよろしくお願いします。