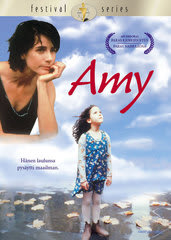(原題:Still Alice )凡作だ。突っ込みが浅く、ストーリーはいい加減で、演出は冗長。わざわざ劇場に足を運ぶまでもなく、テレビ画面で(それも、ヒマな時に)接するのが相応しい。
ニューヨークのコロンビア大学で教鞭を執る言語学教授アリスは50歳。子育ても終わり、仕事に打ち込む充実した日々を送っていた。ある日、講演の席で基本的な用語が口から出てこなくなる。やがてジョギングの最中に道に迷ってしまったり、周囲の者の名前を失念したりと異変は続いたため、彼女は病院の神経科で診察を受ける。
結果、アリスは若年性のアルツハイマー病に罹患していたことが判明。それからも、家族の願いもむなしく彼女の記憶は次第に薄れていく。そんなある日、アリスはまだ症状が軽かった時期に自らパソコンに残したビデオメッセージを発見。画面の中の自分が語ることを実行しようとする。
一番の敗因は家族の描き方が全然なっていない点だ。深刻に受け止めるべき事態であるにもかかわらず、皆どこか及び腰で、ハッキリ言って“軽く”考えているとしか思えない。せいぜいアリスのために家政婦を一人雇うぐらいで、万全な介護体制を敷くとか、来るべき別れの時に備えるとか、そういうことはほとんど示されない。アリスは大学に勤めていたし、夫は医学研究者であるから決して治療費にも困るような環境ではないはず。にもかかわらず、この成り行き任せの悠長さはいったい何だ。
極めつけは、前後不覚になりつつあるアリスを放置して、ダンナは自分一人で栄転のために遠くに引っ越すというくだりだ。結局、この夫にとっては妻の病気も他人事でしかなかったということか。ならばそれ以前に夫婦のギクシャクした関係を描き出してしかるべきだが、そういう気配もなかった。
アリスには3人の子供がおり、彼らの間で誰が母の面倒を見るのか等の揉め事ぐらいは勃発してもおかしくないと思うのだが、それも無し。アリスが患っているアルツハイマー病は遺伝性で、長女は将来的な発病が確実であることが判明するのだが、当然起こるはずの修羅場や愁嘆場も完全スルーされている。わずかにハネっ返りの次女が進路に関して悩む程度で、とにかくこの家族の有り様はまるで現実的ではないのだ。
監督リチャード・グラッツァーの仕事ぶりは全然ピリッとせず、平板すぎる展開に終始。特にアリスが自らのビデオメッセージ通りの行動を取ろうとする場面は本作のハイライトであるはずだが、全く盛り上がらない。主演のジュリアン・ムーアは本作でオスカーを獲得したが、大した演技ではない。受賞は彼女のこれまでの実績に対する功労賞という意味合いか。
夫役のアレック・ボールドウィンは大根。長女を演じるケイト・ボスワースにはロクな見せ場も無い。わずかに目立っていたのが次女に扮したクリステン・スチュワートだが、私は彼女の御面相が大嫌いなので(笑)、見ていてテンションが下がる一方だった。