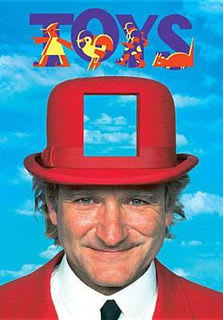(原題:Guess Who's Coming to Dinner)67年作品。第40回アカデミー主演女優賞と脚本賞の受賞作で、私は“午前十時の映画祭”にて今回初めてスクリーン上で接することが出来た。世評通りの面白さで、重要なテーマを扱っていながらドラマ運びは軽やか。良質のコメディでもある。観て良かったと思える佳編だ。
サンフランシスコの新聞社の社主であるマット・ドレイトンの元に、娘のジョーイが久々に帰ってきた。同伴していたのは彼女の婚約者。だが、その相手ジョン・プレンティスは黒人だった。マットはかねてより新聞紙上で理不尽な人種差別に対して激烈な抗議を行い、ジョーイにもリベラルな教育を受けさせてきた。しかし、いざ娘が白人以外の男と結婚する段になると、動揺は隠せない。

妻のクリスティは娘に理解を示すが、マットは頑なな態度を取るばかりだ。さらに、ジョンの両親もドレイトン家の夕食に招かれることになる。彼らも息子の嫁が白人になることに驚くしかなかった。気まずい空気が流れるが、若い2人の真摯な態度が少しずつ事態を好転させていく。「アメリカ上陸作戦」(66年)等で知られるウィリアム・ローズのオリジナル・シナリオを、名匠スタンリー・クレイマーが製作・監督した。
ジョンとジョーイは、当日の夜の飛行機でジュネーヴに旅立たねばならない。その前に何としても双方の両親の承諾を取り付ける必要がある。この“タイム・リミットを介した設定”というのが、まず上手い。限られた時間の中で、マットやクリスティがどのようにして娘たちに理解を示すのか、その段取りも無理がない。
そして、超エリートであるジョンの造型を“単なるレアケースではないか”と突っ込まれることを回避するディテールの巧みさに唸らされる。ジョンとジョーイにとって最大の障壁となるのが、それぞれの父親の“立場”である。人種的偏見は悪いことだと頭の中では思ってはいるが、親として子供が大過なく人生を送ることを望むのも当然なのだ。そのディレンマを、映画はいたずらに変化球や御都合主義的なエピソードを多用することなく、正攻法で切り崩してゆく。

社会的な“立場”で建前論を述べるのは誰だって出来る。だが、人生の機微というのはそんな杓子定規な図式で片付けられるものではない。それぞれの両親の若い頃の出会いはどうだったのか。親子関係を“育ててやったからその分親に奉仕しろ”という損得勘定で割り切って良いのか。それらの命題から逃げること無く、映画は着実に主題を積み上げてゆく。その真摯な姿勢が嬉しい。
クレイマーの演出は重くなりがちの題材を扱う上で、あえてコミカルなテイストを多用するという見上げたもので、各キャストの芸達者ぶりも併せて大いに笑わせてもらった。マット役のスペンサー・トレイシーとクリスティに扮するキャサリン・ヘップバーンは余裕の演技。ジョンに扮するシドニー・ポワチエも上手いが、実生活でも彼は後に白人女性(女優のジョアンナ・シムカス)と結婚することを考え合わせると、なかなか感慨深い配役だ。
またジョーイ役のキャサリン・ホートンはヘップバーンの姪でもあるが、天然ぶりを全面展開した妙演で感心した。サム・リーヴィットのカメラが捉えたサンフランシスコの風景。テーマ曲の「ザ・グローリー・オブ・ラヴ」も印象深い。
サンフランシスコの新聞社の社主であるマット・ドレイトンの元に、娘のジョーイが久々に帰ってきた。同伴していたのは彼女の婚約者。だが、その相手ジョン・プレンティスは黒人だった。マットはかねてより新聞紙上で理不尽な人種差別に対して激烈な抗議を行い、ジョーイにもリベラルな教育を受けさせてきた。しかし、いざ娘が白人以外の男と結婚する段になると、動揺は隠せない。

妻のクリスティは娘に理解を示すが、マットは頑なな態度を取るばかりだ。さらに、ジョンの両親もドレイトン家の夕食に招かれることになる。彼らも息子の嫁が白人になることに驚くしかなかった。気まずい空気が流れるが、若い2人の真摯な態度が少しずつ事態を好転させていく。「アメリカ上陸作戦」(66年)等で知られるウィリアム・ローズのオリジナル・シナリオを、名匠スタンリー・クレイマーが製作・監督した。
ジョンとジョーイは、当日の夜の飛行機でジュネーヴに旅立たねばならない。その前に何としても双方の両親の承諾を取り付ける必要がある。この“タイム・リミットを介した設定”というのが、まず上手い。限られた時間の中で、マットやクリスティがどのようにして娘たちに理解を示すのか、その段取りも無理がない。
そして、超エリートであるジョンの造型を“単なるレアケースではないか”と突っ込まれることを回避するディテールの巧みさに唸らされる。ジョンとジョーイにとって最大の障壁となるのが、それぞれの父親の“立場”である。人種的偏見は悪いことだと頭の中では思ってはいるが、親として子供が大過なく人生を送ることを望むのも当然なのだ。そのディレンマを、映画はいたずらに変化球や御都合主義的なエピソードを多用することなく、正攻法で切り崩してゆく。

社会的な“立場”で建前論を述べるのは誰だって出来る。だが、人生の機微というのはそんな杓子定規な図式で片付けられるものではない。それぞれの両親の若い頃の出会いはどうだったのか。親子関係を“育ててやったからその分親に奉仕しろ”という損得勘定で割り切って良いのか。それらの命題から逃げること無く、映画は着実に主題を積み上げてゆく。その真摯な姿勢が嬉しい。
クレイマーの演出は重くなりがちの題材を扱う上で、あえてコミカルなテイストを多用するという見上げたもので、各キャストの芸達者ぶりも併せて大いに笑わせてもらった。マット役のスペンサー・トレイシーとクリスティに扮するキャサリン・ヘップバーンは余裕の演技。ジョンに扮するシドニー・ポワチエも上手いが、実生活でも彼は後に白人女性(女優のジョアンナ・シムカス)と結婚することを考え合わせると、なかなか感慨深い配役だ。
またジョーイ役のキャサリン・ホートンはヘップバーンの姪でもあるが、天然ぶりを全面展開した妙演で感心した。サム・リーヴィットのカメラが捉えたサンフランシスコの風景。テーマ曲の「ザ・グローリー・オブ・ラヴ」も印象深い。