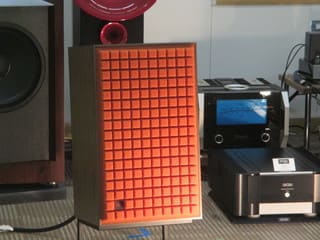(原題:IF BEALE STREET COULD TALK)作品の外観の雰囲気は良いのだが、中身は薄い。監督のバリー・ジェンキンスとしても、高く評価された前作「ムーンライト」(2016年)にはとても及ばない仕事ぶりで、早くも方向性に迷いが出ている印象を受けた。
70年代のハーレム。幼い頃から共に育ち、長じて恋人同士になった19歳のティッシュと22歳のファニーは将来を誓い合い充実した日々を送っていた。ところが、ある日ファニーが無実の罪で逮捕されてしまう。すでに妊娠していたティッシュとその家族は、何とかファニーを助け出そうとするが、上手くいかない。黒人作家ジェイムズ・ボールドウィンの小説の映画化だ。

物語の設定だけを読むと、誰でもこれは“不条理な境遇に追い込まれた主人公たちが徒手空拳で権力に立ち向かう熱いドラマ”だと思うだろうし、事実それ以外にはあり得ないようなシチュエーションなのだが、実際はそうではないのだ。
ファニーを救うために奔走するのはティッシュではなく、彼女の母親。しかも、結果は捗々しいものではない。リベラル派と思しき若い白人弁護士も登場するが、その言動はクローズアップされない。そもそも、ファニーが窮地に追い込まれた原因である黒人差別に関しても、直截的に描かれていないのだ。
斯様に、話の本筋がほとんどドラマティックに扱われていないにも関わらず、ティッシュとファニーの色恋沙汰を扱うパートは必要以上に長い。もちろんそれがストーリーの弱さをカバーするほど濃密に撮られているのならば文句はないが、これがどうにも淡白に過ぎて退屈だ。煮え切らない展開に週した挙句、気勢の上がらないラストが待ち受けているという、何とも冴えない結果に終わってしまった。
ジェームズ・ラクストンのカメラによる映像は透き通るように美しいが、ムード的に流されて70年代のニューヨークの下町らしい猥雑感や熱気はまるで表現されていない。そもそも、この映画はビール・ストリートが舞台ではないのだ(その通りがあるのはテネシー州メンフィスである)。
キャストでは、ティッシュを演じた長編映画初出演のキキ・レインが印象に残る。チャーミングな容貌と確かな演技力を持つ逸材で、今年度の新人賞の有力候補だ。ファニー役のステファン・ジェームズも悪くないし、各アワードを受賞したレジ―ナ・キングのパフォーマンスも要チェックだ。しかし、映画自体の出来が大したことが無いので、彼らの奮闘が報われているとは言い難い。なお、ニコラス・ブリテルの音楽は良好。サントラ盤は聴く価値がある。
70年代のハーレム。幼い頃から共に育ち、長じて恋人同士になった19歳のティッシュと22歳のファニーは将来を誓い合い充実した日々を送っていた。ところが、ある日ファニーが無実の罪で逮捕されてしまう。すでに妊娠していたティッシュとその家族は、何とかファニーを助け出そうとするが、上手くいかない。黒人作家ジェイムズ・ボールドウィンの小説の映画化だ。

物語の設定だけを読むと、誰でもこれは“不条理な境遇に追い込まれた主人公たちが徒手空拳で権力に立ち向かう熱いドラマ”だと思うだろうし、事実それ以外にはあり得ないようなシチュエーションなのだが、実際はそうではないのだ。
ファニーを救うために奔走するのはティッシュではなく、彼女の母親。しかも、結果は捗々しいものではない。リベラル派と思しき若い白人弁護士も登場するが、その言動はクローズアップされない。そもそも、ファニーが窮地に追い込まれた原因である黒人差別に関しても、直截的に描かれていないのだ。
斯様に、話の本筋がほとんどドラマティックに扱われていないにも関わらず、ティッシュとファニーの色恋沙汰を扱うパートは必要以上に長い。もちろんそれがストーリーの弱さをカバーするほど濃密に撮られているのならば文句はないが、これがどうにも淡白に過ぎて退屈だ。煮え切らない展開に週した挙句、気勢の上がらないラストが待ち受けているという、何とも冴えない結果に終わってしまった。
ジェームズ・ラクストンのカメラによる映像は透き通るように美しいが、ムード的に流されて70年代のニューヨークの下町らしい猥雑感や熱気はまるで表現されていない。そもそも、この映画はビール・ストリートが舞台ではないのだ(その通りがあるのはテネシー州メンフィスである)。
キャストでは、ティッシュを演じた長編映画初出演のキキ・レインが印象に残る。チャーミングな容貌と確かな演技力を持つ逸材で、今年度の新人賞の有力候補だ。ファニー役のステファン・ジェームズも悪くないし、各アワードを受賞したレジ―ナ・キングのパフォーマンスも要チェックだ。しかし、映画自体の出来が大したことが無いので、彼らの奮闘が報われているとは言い難い。なお、ニコラス・ブリテルの音楽は良好。サントラ盤は聴く価値がある。