慶聞抄(きょうもんしょう)
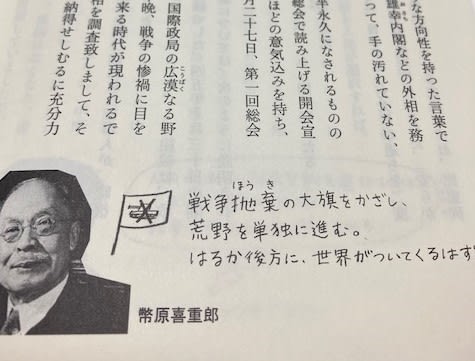
学問は歴史に極まれり
(儒学者・荻生徂徠の言葉より)
今年の報恩講さんは、役員さんに仏教女性会の常連さんたちを合わせて10人の限定参加で、いつもより寂しいものでしたが、このコロナ禍にあってお参りいただいたことを本当に有難く思いました。より一層、親鸞聖人の90年にわたるご生涯に思いを馳せたことでした。
もう一つ、私にとって忘れられないものとなったのは、マスクはいいとしてサングラス姿で出勤したことでした。直前に道でこけて、右目周辺に青タンを作ってしまったのです。眼鏡は壊れて、お岩さんみたいな形相でした。
最大のショックは、倒れる時にとっさに手が出なかったことです。顔面直撃衝突。これは本当に怖いし痛い。三週間たって青タンは薄まり、黄色がかって徐々に下がってきました。反省点は、①右手に紙袋を持っていた②焦って小走りだった③前につんのめることがある革靴。
菅義偉首相が日本学術会議会員候補のうち6名の任命を拒否するという問題が起きました。私はすぐ、1930年代に起きた「滝川事件」(京都大学の滝川幸辰教授の学説が無政府主義的だなどと問題視され退官に追い込まれた)や「天皇機関説問題」(憲法学者で貴族院議員だった美濃部達吉のこの説が不敬とされ、著作が発禁処分を受け、議員を辞職した)を思い出し、胸騒ぎを覚えました。首相は国会でその理由を質問されてもちゃんと答えていません。
でも理由は明らかです。日本学術会議は戦争に協力した過去を反省して、戦後一貫して軍事研究に否定的な立場をとっています。1967年には「軍事目的のための科学研究を行わない表明」をしています。首相は今、自らの任命権を振りかざして会員人事に介入してきたのです。会員が特別職の国家公務員であると強調して。そのうち、今は選挙で決める学長や教授の人事にも介入するのでは? 38年に「帝大騒動」という前例があります。
その後、井上科学技術相が梶田学術会議会長に「デュアルユース」を検討するよう伝えたという報道がありました。「デュアルユース」つまり、軍民両用テクノロジーということで、民間企業のトップも強く望んでいます。2015年度、防衛省は「安全保障技術推進制度」を創設し、学術会議も翌年、議論を開始せざるを得なくなりました。線引きの難しい問題ですが、要はどう歯止めをつけるか、そのための学術会議ではないでしょうか。少なくとも6名は政府の方々よりは「多様」で「総合的」で「俯瞰的」な人たちです。
その中に、日本近現代史の加藤陽子さんの名前を見つけ、本棚から「戦争まで」という本を出してきました。歴史を決めた交渉と日本の失敗を若干の中学生と多くは高校生に語り、彼らとの問答をまとめたものです。終章で、戦争調査会での幣原喜重郎首相の言葉を紹介しています。
「戦勝国にせよ敗戦国にせよ戦争が引き合うものでない、この現実なる参考を作る。将来我々の子孫が戦争を考えないとも限らない。その時の参考に今回の資料が非常に役立つような調査をせねばならぬ。」
質問に答えないばかりか、忖度させ記録も残さない、改ざんさせて平気な政治家に私たちはどこに連れて行かれるのでしょうか?
失敗から学ばないと、また痛い目に遭うに違いありません。 合掌
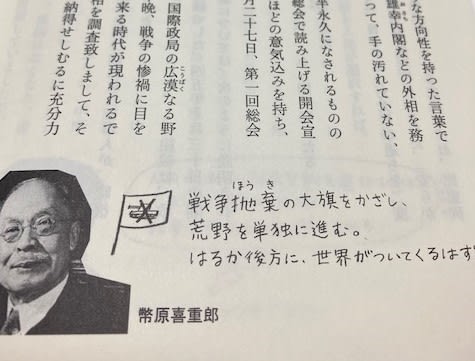
学問は歴史に極まれり
(儒学者・荻生徂徠の言葉より)
今年の報恩講さんは、役員さんに仏教女性会の常連さんたちを合わせて10人の限定参加で、いつもより寂しいものでしたが、このコロナ禍にあってお参りいただいたことを本当に有難く思いました。より一層、親鸞聖人の90年にわたるご生涯に思いを馳せたことでした。
もう一つ、私にとって忘れられないものとなったのは、マスクはいいとしてサングラス姿で出勤したことでした。直前に道でこけて、右目周辺に青タンを作ってしまったのです。眼鏡は壊れて、お岩さんみたいな形相でした。
最大のショックは、倒れる時にとっさに手が出なかったことです。顔面直撃衝突。これは本当に怖いし痛い。三週間たって青タンは薄まり、黄色がかって徐々に下がってきました。反省点は、①右手に紙袋を持っていた②焦って小走りだった③前につんのめることがある革靴。
菅義偉首相が日本学術会議会員候補のうち6名の任命を拒否するという問題が起きました。私はすぐ、1930年代に起きた「滝川事件」(京都大学の滝川幸辰教授の学説が無政府主義的だなどと問題視され退官に追い込まれた)や「天皇機関説問題」(憲法学者で貴族院議員だった美濃部達吉のこの説が不敬とされ、著作が発禁処分を受け、議員を辞職した)を思い出し、胸騒ぎを覚えました。首相は国会でその理由を質問されてもちゃんと答えていません。
でも理由は明らかです。日本学術会議は戦争に協力した過去を反省して、戦後一貫して軍事研究に否定的な立場をとっています。1967年には「軍事目的のための科学研究を行わない表明」をしています。首相は今、自らの任命権を振りかざして会員人事に介入してきたのです。会員が特別職の国家公務員であると強調して。そのうち、今は選挙で決める学長や教授の人事にも介入するのでは? 38年に「帝大騒動」という前例があります。
その後、井上科学技術相が梶田学術会議会長に「デュアルユース」を検討するよう伝えたという報道がありました。「デュアルユース」つまり、軍民両用テクノロジーということで、民間企業のトップも強く望んでいます。2015年度、防衛省は「安全保障技術推進制度」を創設し、学術会議も翌年、議論を開始せざるを得なくなりました。線引きの難しい問題ですが、要はどう歯止めをつけるか、そのための学術会議ではないでしょうか。少なくとも6名は政府の方々よりは「多様」で「総合的」で「俯瞰的」な人たちです。
その中に、日本近現代史の加藤陽子さんの名前を見つけ、本棚から「戦争まで」という本を出してきました。歴史を決めた交渉と日本の失敗を若干の中学生と多くは高校生に語り、彼らとの問答をまとめたものです。終章で、戦争調査会での幣原喜重郎首相の言葉を紹介しています。
「戦勝国にせよ敗戦国にせよ戦争が引き合うものでない、この現実なる参考を作る。将来我々の子孫が戦争を考えないとも限らない。その時の参考に今回の資料が非常に役立つような調査をせねばならぬ。」
質問に答えないばかりか、忖度させ記録も残さない、改ざんさせて平気な政治家に私たちはどこに連れて行かれるのでしょうか?
失敗から学ばないと、また痛い目に遭うに違いありません。 合掌
















