出かける途中に諏訪神社があり、立ち寄りました。
諏訪神社には庚申塔があるかもしれないと、ワクワクしながら…。

入り口にある田遊びの石碑です。
初めて聞く「田遊び」…なんだろうと思いました。
田遊びは、模擬的な稲作所作を行う日本の民俗芸能で、東京都板橋区に伝わる重要無形民俗文化財です。赤塚諏訪神社では2月13日の夜に奉納されます。
田遊びは稲作の季節を前に五穀豊穣を祈ります。夜に行うのは秘事であったからで、種まきから収穫に至る稲作の一連の作業を、所作と唱え言葉で再現しています。
You Tubeで見ることができます。
お百度石

願い事が成就するように百度石を基点として社殿に100回参拝する「お百度参り」。
近くの氏神神社や社寺に、百日間毎日参拝するというもので、これを百日詣といいます。それが簡略化され、一日に百度参るという形で百日詣の代わりとするようになった。
鎌倉時代初期には百度参りがあったことがわかっています。百度参りは人に見られないように夜間に行うとか、裸足で行った方がより効果があるなどと言われています。
境内を回ってみましたが、庚申塔はありませんでした。
諏訪神社には庚申塔があるかもしれないと、ワクワクしながら…。

入り口にある田遊びの石碑です。
初めて聞く「田遊び」…なんだろうと思いました。
田遊びは、模擬的な稲作所作を行う日本の民俗芸能で、東京都板橋区に伝わる重要無形民俗文化財です。赤塚諏訪神社では2月13日の夜に奉納されます。
田遊びは稲作の季節を前に五穀豊穣を祈ります。夜に行うのは秘事であったからで、種まきから収穫に至る稲作の一連の作業を、所作と唱え言葉で再現しています。
You Tubeで見ることができます。
お百度石

願い事が成就するように百度石を基点として社殿に100回参拝する「お百度参り」。
近くの氏神神社や社寺に、百日間毎日参拝するというもので、これを百日詣といいます。それが簡略化され、一日に百度参るという形で百日詣の代わりとするようになった。
鎌倉時代初期には百度参りがあったことがわかっています。百度参りは人に見られないように夜間に行うとか、裸足で行った方がより効果があるなどと言われています。
境内を回ってみましたが、庚申塔はありませんでした。



















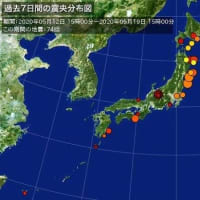
庚申塔無くて残念でしたね。
mariさんは、庚申塔のこと調べているのですか。
私はあまり気にしたことがなく、高知県にあるのかどうか見ていても、これがそうだと気づいてないと思います(大汗)
磨崖仏は、実家の氏神様(廃仏きじゃく以前はお寺だった)大日如来坐像があります。
お百度参りの石は境内で時折見かけます。
庚申塔、高知県には見かけませんか?
沖縄以外にはあるようです。
東京には多く残っています。
三猿が可愛らしく見えるので、つい探してしまいます。
出かけた折に一回り、ちょっとした勉強になります。
磨崖仏…いいですネ。
いつかブログで見せてください。