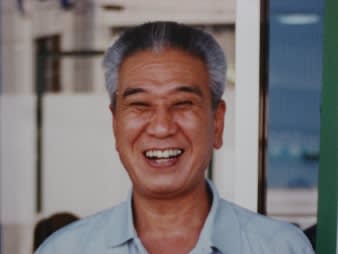~ 恩師の「心行の解説」下巻より ~
講演 五
「六根あるがゆえに己が悟れば菩提と化すことを悟るべし」
先の続き・・・
私たちは天上の世界におりますと、
自分の魂の光の量をさらに上げることができないために、
この厳しい現象界で肉体の中に入って魂の修行をします。
現象界というのは天上界から見ますとものすごく危険極まりない場所で、
いつ転がり落ちるか分からないような断崖絶壁を旅している世界ですね。
一歩踏み外すとたちまち奈落の底へ落ちます。
仲良く幸せに暮らしていた家庭で、奥さんが亡くなられたあと、
息子さん夫婦にもの事が起きてお嫁さんが子供を残して家を出てしまい、
私たちが知り合った当時の幸せな調和された家庭が二年もしないうちに
完全に破壊したのを知っていますが、
このような崖ふちを私たちは旅をしているということです。
一つ何かの縁にふれましたら、突然奈落の底へ落ちているという方が
いっぱいありますね。
会社の場合も同じです。
この間まで景気よく盛大にやっておられた方が、
ある日会社の前を通りますと、
破産のため会社は潰れ、家族は分散していました。
これも危険なこの世の旅で一歩足を踏み外した姿です。
自然界の海原の航海にも譬えられます。
海原は或る時は波一つなく静かに凪いでいますし、
また暴風に荒れ狂う時もあります。
海面は凪いでいても霧に閉じ込められて航海不可能な状態もあり、
凪いでいるから「やれ嬉しや」と航海していると暗礁が出ていて
船底を突き破ってしまうこともあります。
それと全く同じです。
私たちの人生も油断していたら港の入口で船の底を
割ったという例になりますね。