本物の曜変天目を観たあと、以前録画しておいた番組
『幻の名碗「曜変天目」に挑む』を改めて観ました。
その中で「何らかの人為的な加工を施して創られたのではないか」
という推測のもとに再現に取り組んだ方の作品を観ると、
テレビ画面上では「かなり近いなあ」という印象でした。
どのような技法を用いたのか番組中では詳しくは紹介されていませんので、
一度焼いたものに加工して再度焼き直したのか、
全体に釉薬をかけたあとに斑紋となる箇所に何か手を加えて焼いたのか、
その辺のところはわかりません。
インターネットで調べてみると、
この方の作品をもって「曜変天目の復元に成功」とする方々もいれば、
曜変天目はあくまでも窯の中の変化(=窯変)だけで創られたものであり
人為的な加工を施したものは「絵付け曜変天目」などと呼ぶべきである、
と主張される方々もいて、評価は様々です。
後者の主張をする方々の根拠の一つとして、
「人為的な加工を施したのであれば、もっと大量に残っているはずだ」
ということがあります。
素人考えですが、私もそう思います。
(それ以上のことは、専門的過ぎてわかりませんが・・・)
ただ、どのような方法であれ、もし現物が存在していなかったら
「復元」を試みることもできなかったでしょうし、
そもそも、このような「美しさ」が焼物の中に秘められていたことすら
知り得なかったのではないでしょうか。
そう考えると、今、現に存在していることの「奇跡」を思わずにはいられません。
また数学の例えで恐縮ですが、
長い間解けなかった難問(フェルマーの最終定理やポアンカレ予想など)
が証明される過程では無数の試みや失敗がありましたが、
それらは別の形で数学の発展に大きく寄与したとされています。
曜変天目は今から800年ほど前に誕生したとされています。
もしかしたら、"あの時代"に"あの場所"でしか決して起こらない
「偶然」があったのかもしれません。
そうであるならば、二度と同じものを創り出すことはできないことになります。
でも、多くの方々が様々な方法で試みる「曜変天目再現」の営みは
決して無駄ではないでしょう。
そこからまた新たな発見があり、
それが、まだ見ぬ「美しさ」へと「窯変」していくかもしれませんから。
『幻の名碗「曜変天目」に挑む』を改めて観ました。
その中で「何らかの人為的な加工を施して創られたのではないか」
という推測のもとに再現に取り組んだ方の作品を観ると、
テレビ画面上では「かなり近いなあ」という印象でした。
どのような技法を用いたのか番組中では詳しくは紹介されていませんので、
一度焼いたものに加工して再度焼き直したのか、
全体に釉薬をかけたあとに斑紋となる箇所に何か手を加えて焼いたのか、
その辺のところはわかりません。
インターネットで調べてみると、
この方の作品をもって「曜変天目の復元に成功」とする方々もいれば、
曜変天目はあくまでも窯の中の変化(=窯変)だけで創られたものであり
人為的な加工を施したものは「絵付け曜変天目」などと呼ぶべきである、
と主張される方々もいて、評価は様々です。
後者の主張をする方々の根拠の一つとして、
「人為的な加工を施したのであれば、もっと大量に残っているはずだ」
ということがあります。
素人考えですが、私もそう思います。
(それ以上のことは、専門的過ぎてわかりませんが・・・)
ただ、どのような方法であれ、もし現物が存在していなかったら
「復元」を試みることもできなかったでしょうし、
そもそも、このような「美しさ」が焼物の中に秘められていたことすら
知り得なかったのではないでしょうか。
そう考えると、今、現に存在していることの「奇跡」を思わずにはいられません。
また数学の例えで恐縮ですが、
長い間解けなかった難問(フェルマーの最終定理やポアンカレ予想など)
が証明される過程では無数の試みや失敗がありましたが、
それらは別の形で数学の発展に大きく寄与したとされています。
曜変天目は今から800年ほど前に誕生したとされています。
もしかしたら、"あの時代"に"あの場所"でしか決して起こらない
「偶然」があったのかもしれません。
そうであるならば、二度と同じものを創り出すことはできないことになります。
でも、多くの方々が様々な方法で試みる「曜変天目再現」の営みは
決して無駄ではないでしょう。
そこからまた新たな発見があり、
それが、まだ見ぬ「美しさ」へと「窯変」していくかもしれませんから。















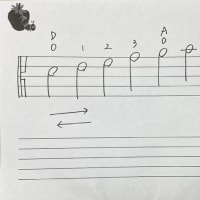













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます