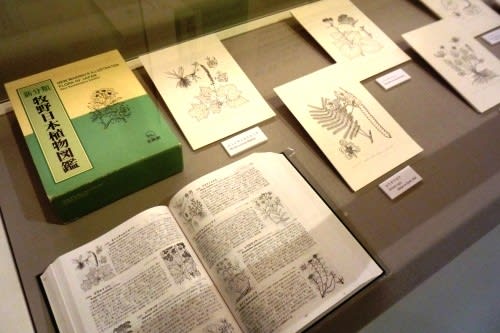【今年で17回目、高校生の熱演におひねり次々と】
大阪の笑い納めが枚岡神社の「注連縄掛(しめかけ)神事」(通称お笑い神事)なら、奈良のそれは 漢国(かんごう) 神社の「大祓⋅獅子神楽」だろう。太神楽曲芸師の豊来家玉之助さんが2008年に1年間の厄払いと新年の招福を願って獅子舞を奉納したのが始まり。今年も29日に石舞台で約2時間にわたって繰り広げられ、境内は熱演と軽妙なトークで笑いの渦に包まれた。(下の写真は「へべれけ」の一場面)

漢国神社は近鉄奈良駅から西へ徒歩数分の距離にある。獅子神楽は同神社の韓園講(からそのこう)の主催で、午後1時から始まった。幕開けの演舞は豊来家さんの「韓園」。1人で獅子頭を両手に持って舞うもので、ご自身で創作したとのこと。次いで「宮参り」「大黒」と続いた。

昨年まで演舞でもトークでも豊来家さんの八面六臂の活躍が目立った。ところが今年はやや控えめ。その分、若手出演者の力量が上がってきたということだろう。

その中で注目を集めたのが兵庫県立西宮高校邦楽部の「県西太鼓“爛漫”」の皆さん。「 雲」と題した獅子舞を力強く華麗に演じて、演舞後にはこの日一番のおひねりが舞台上に飛び交った。(写真 上と下)

この後も演舞が続いた。「剣」「荒神祓崩し」「親子獅子」。そして次の演目「へべれけ」に移る前、豊来家さんが「その前に見ていただきたいものがある」と話し、舞台裏に「ナカムラさ~ん」と声を掛けた。登場したのは昨年、半紙を口にくわえたまま舞う過酷な群舞で、終盤に口元から半紙を落とした女性だった。

今年は豊来家さんの太鼓に合わせ、1人で最後まで舞い終えた。昨年「次はもっと練習を積んで落とさないよう頑張ります」と話していたこの女性。その言葉通り、見事に雪辱を果たした。今年も笑い納めの愉快なひとときを過ごすことができた。
【 東大寺大仏殿には長蛇の列】
29日東大寺を訪れると、参道も大仏殿の周りも参拝客で賑わっていた。その多くがたぶん海外からの観光客。大仏殿への入場口には長蛇の列ができていた。

入場し中門の基壇から大仏殿を望むと、その間も人の波が続いていた。元旦の午前零時から8時までは入堂が無料になる。大仏殿上部中央の観相窓も開いて、境内からも大仏さまのお顔を拝むことができる。

大仏殿内も「柱くぐり抜け」の場所に長い列ができていた。柱の下に開いた穴をくぐると無病息災や祈願成就のご利益があるという。そばにはこんなお願いの立て札 。「大変混雑することから、待ち時間が長く苦情が寄せられています。より多くの皆様に手際よく柱くぐりをしていただけますよう、記念写真は1人1枚でお願いします」

普段くぐり抜けに挑戦するのは子どもや小中学生が大半。だが、この日は多くが大人の旅行客だった。 中には頭が出ても胴体がなかなか抜けず、知人に助けを求め引っ張り出してもらう人も。「記念写真は1人1枚」に、「抜ける自信のない方は自重を」と付け加える必要があるかもしれない。

【興福寺五重塔素屋根工事の長大クレーンは一休み】
興福寺の国宝五重塔は来春から本格的な保存修復工事が始まる。そのための塔を覆う素屋根(高さ約60m)の建設も最終段階を迎えている。猿沢池から見上げると、つい最近まで立っていた長大クレーンが姿を消していた。だが、よく見ると素屋根の足元に赤白模様のクレーンらしきものが!

塔最上部の相輪も完全に覆われているように見える。クレーンも役割を終えたのかも。そう思った。だが、どうも違うらしい。近くの興福寺国宝館の関係者によると、今は年末年始で工事休止中のためクレーンを折り畳んでいるとのこと。素屋根の完成は来年3月末の予定。その後、7年後の2032年3月の完成を目指し、屋根瓦の葺き替えや漆喰壁の塗り直し、木部破損箇所の修理などを行う。