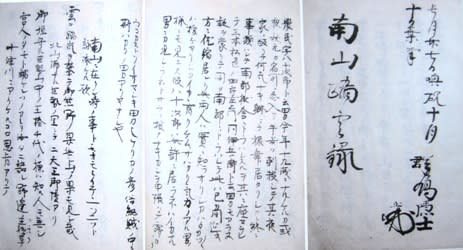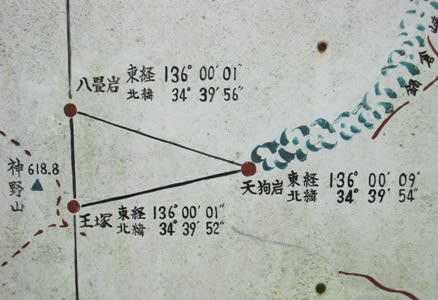【平易な文章で綴る示唆に富むエッセー集】
著者の日高敏隆氏(1930~2009)は「動物行動学」研究の草分け的な存在。滋賀県立大学の初代学長や総合地球環境学研究所の初代所長なども務めた。本書には主に1990年代以降、新聞や各種会報などに掲載したエッセー70点余を収録している。平易な文章で身辺や社会の出来事、昆虫のことなどを綴っており、なかなか示唆に富む指摘も多い。

プロローグのタイトルは『打ち込んではいけない』。高校の卒業生に向けたはなむけのような一文だが、「できるだけさまざまな経験をするのがよい。しごとでも勉強でも遊びでも、何かひとすじというのは絶対に損だ」とし、「恋愛またしかり」と続ける。そして「一つのことに打ちこむことは、人間を貧しくすることだ。絶対に一つのことに熱中してはいけない」という。
『地球環境学とは何か』では、「地球上には何百万種とも何千万種ともいわれる動物が存在してきたが、〝いわゆる地球環境問題〟という問題をひきおこしたのは、われわれ人間という種だけである」とし、「それは人間が自分たちは自然とは一線を画した存在であるという認識をもち、自然と対決して生きていこうとしたからではないか」と指摘する。
『渋谷でチョウを追った少年の物語』の中では、言語や優れた学習能力を持つ人間とチョウを比較して、「それは彼ら(チョウ)がそこまで到達できなかったからではなく、そのどちらも必要なかったからです」という。『動物に心はあるか』では「多くの動物たちが何かを考えていることはまず間違いない」とし、「古くから『言語なき思考』ということが言われている。これが、ヒトの意識・思考と非常に異なるところである」と指摘する。その例証として「ネコが夢を見ることはほぼ確か」という話を挙げる。
昆虫が人家の明かりに寄ってくるのは〝正の走光性〟という性質によるそうだ。『灯りにくる虫』では「いったん家の灯りにひきつけられてしまった虫たちは、メスに出会うこともなく、子孫を残すこともなしに、短い一生を終えてしまう」という悲劇を綴る。夜が更けると灯りは消される。真っ暗な闇の中で虫たちは飛べない。やがて朝に。光はまぶしすぎて動けない。そして夜になると家の明かりにまた吸い寄せられる。その繰り返しの果てに――。
こんなユニークな体験談も綴られている。中国人が書いた「引力」という小説が文芸書売り場でどうしても見つからなかったが、物理学のコーナーに行くと平積みされていた。レジで「1万円からでよろしかったでしょうか?」という過去形の言い方には「いささか当惑を感じる」と疑問を投げかける。「飛行機雲がもとになって雲が生じ、曇り日がふえてくるのではないかということもいわれるようになった」「(自動水洗の)赤外線ランプは自然につくものではないから、当然電力を食っている……省エネという掛け声にも反している」という指摘もなるほどと思わせられた。
『空と地上』という一文も印象に残った。ベトナム戦争中に航空機が激戦地のダナン上空に差し掛かった。地上から黒煙が上がるのも見えた。その時、機中は昼食の時間でみんなワインなどを手に食事中だった。「ぼくはあらためて飛行機の怖さを思わざるを得なかった。それは落ちるとか、ハイジャックされるとかいうことではなく、地上の人間の生活のことを忘れさせるということである」。