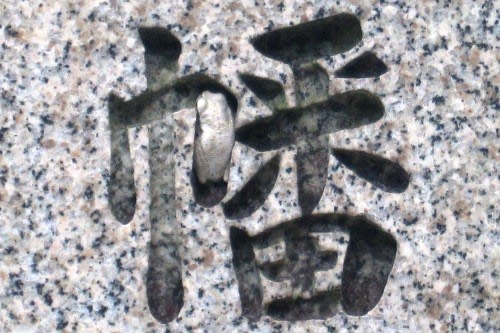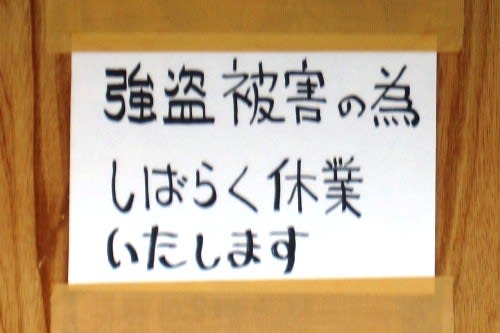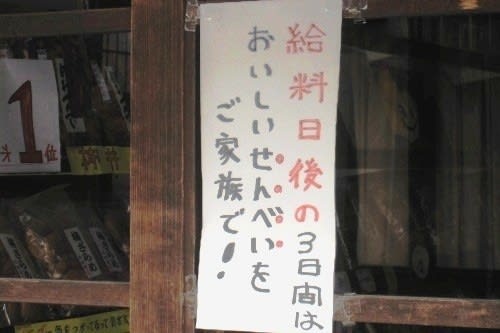【多彩な獅子舞や曲芸などで大盛り上がり】
近鉄奈良駅のそばにある古社、漢国(かんごう)神社の石舞台で12月29日「大祓・獅子神楽」の奉納が行われた。2008年に太神楽曲芸師・豊来家玉之助さん(51)が1年の厄払いと新年の福を願って獅子舞を奉納したのが始まり。今では歳末恒例の風物詩としてすっかり定着、この日も境内は多くの観客で埋め尽くされ、演舞が終わるたびに拍手とともにおひねりが次々に投げ込まれた。

出演者は豊来家さんを中心に漢国神社韓園講(からそのこう)、桃俣(もものまた)獅子舞保存会(奈良県御杖村)、西宮神社獅子舞保存会(兵庫県西宮市)の面々。神楽奉納は午後1時「道中」で幕開けし、続いて道先案内の「猿田彦舞」、「宮参り」と続いた。

4番目の演目「韓園」は1人で獅子頭を左右両手に持って舞う。豊来家さんが自ら創作したという。いわば獅子舞の“二刀流”だ。

豊来家さんは邪気を払う「剣」に続く6番目の「大黒」でも再び登場し、軽妙なトークで会場の笑いを誘っていた。観客席から舞台へおひねりが飛び交う。


続く「抜身荒神祓」と「抜身中村」はこの日一番の見どころ。半紙を口にくわえたまま、鈴や宝刀を手に激しく舞う。口で息を吸うことも吐くこともできない。半紙が唾で濡れても落ちやすくなってしまう。真剣な表情で舞う演者に、和紙をくわえて息や唾がかからないように刀剣を手入れする武士の姿が重なって見えた。

2つの演舞の最中、観客席は静まり返って視線は半紙をくわえた口元に注がれた。「大丈夫かなぁ?」。次第に心配になって見つめていると、ついに若い女性の口元から半紙が落ちてしまった。それがこの演目の過酷さを端的に表していた。「練習を積んで来年は落ちないようにします」。そう話す女性の爽やかな表情が印象的だった。

奉納芸はまだまだ続く。「荒神祓崩し」の後は「へべれけ」。千鳥足のひょっとこが瓢箪のとっくりと大きな金杯を持って登場し、観客に渡した杯に酒を注ぐ(まね)。それを一気に飲み干す観客。隣に座った女性にも杯が回ってきた。舞台後方に控えた豊来家さんから声が飛ぶ。「女性ばかりに(杯を)渡すんじゃない!」。会場はまたまた爆笑の渦に包まれた。(隣席の女性へ。ブログへの写真掲載、快諾していただきありがとうございました)

続く「参神楽」の演舞では豊来家さんが太鼓に合わせ自ら笛を吹いていた。その演奏の見事なこと! この後の演目「太神楽」でも傘回しや籠鞠(かごまり)などの曲芸を披露した。豊来家さんの芸には失敗しても、みんなを笑わすための演技では、と思わせるところがある。

まさに八面六臂の活躍。豊来家さんが以前、NHKの連続テレビ小説「わろてんか」で松坂桃李さんに傘回しなどを演技指導したことを自慢していたことを思い出した。

神楽奉納もいよいよフィナーレ。「荒廻剣」に続いて、参加者全員が「伊勢音頭」を歌いながら舞台に勢揃い、一人ひとりお礼の挨拶をしたり新年の抱負を話したりしていた。最後に豊来家さんの「四方鎮(よもしずめ)」の舞で、2時間近くにわたった熱演の舞台を締めくくった。この後、観客には小豆とカボチャを煮込んだ御杖村の郷土料理「いとこ煮」がふるまわれた。