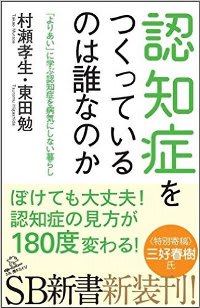【村瀬孝生・東田勉共著、SBクリエイティブ発行】
共著者の村瀬氏は「宅老所よりあい」(福岡市)代表で、著書に「ぼけてもいいよ『第2宅老所よりあい』から」などがある。一方、東田氏は介護や認知症、薬害を主要テーマとするフリーライター兼編集者。主な編著作に「認知症の『真実』」「介護のしくみ」など。本書は「『よりあい』に学ぶ認知症を病気にしない暮らし」を副題に掲げ、介護の現場を知り尽くした2人が対談を通じて認知症高齢者を取り巻く環境やケアの問題点などを鋭く浮き彫りにする。
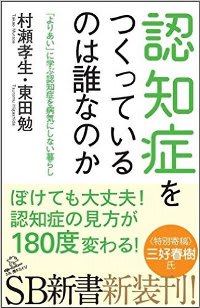
「認知症は国や製薬会社や医学会が手を組んでつくりあげた幻想の病」「2004年に認知症という病名が厚生労働省によってつくられた」「認知症と診断されると抗認知症薬が投与され、興奮や徘徊といった副作用が出たら、それを抑えるために向精神薬が投与される。そのことによって、お年寄りは本物の認知症にされてしまう」――。「はじめに」に綴られた東田氏の刺激的な表現に引き込まれるように、続く6章+終章(三好春樹「生活とリハビリ研究所」代表の特別寄稿)を一気に読んだ。
厚労省は今年1月、国内の認知症患者が10年後の2025年に現在の1.5倍の700万人になると発表した。村瀬氏は「認知症は制度的に増えて当たり前」と指摘する。「公的介護サービスを受けようと思って申請する際、認知症がないと要介護度が高く出ない」ため、「加齢による物忘れやそこから生まれる勘違いを認知症にした方が、給付が受けやすくなっている」からだ。
「認知症」という言葉が使われる以前は広く「ぼけ(呆け)」や「痴呆」という言葉が使われた。「呆」の字の成り立ちは赤ん坊がオムツをされるときに両手両足を開いている状態を表すそうだ。だから「お年寄りがぼけたからって慌てる必要はない。子どもに戻ったようなものだから」と村瀬氏は言う。東田氏も「痴呆やぼけという言葉を刈り取った結果、年相応にぼけていたお年寄りまでも全部、認知症にさせられてしまった」と指摘する。
第1章「介護保険制度と言葉狩りが認知症をつくっている」に続く第2章「あらゆる形の入院が認知症をつくっている」では「病院の白い無機質な空間は……健常なお年寄りでさえ見当識障害を起こしかねない」として入院の怖さに触れる。第3~第5章では認知症をつくっている主体として「厚生労働省のキャンペーン」「医学会と製薬会社」「介護を知らない介護現場」を挙げ、さらに第6章では「老人に自己決定させない家族」にも責任の一端があると指摘する。東田氏は第4章で他の薬剤に例を見ない増量規定など抗認知症薬の問題点も列挙する。
村瀬氏は多くの認知症高齢者らと接してきた体験から「人は『できる自分』と『できなくなる自分』を精神的にも肉体的にも『行ったり来たり』しながら老いていくように思える。そこにどう具体的に付き合い、支援していくのかが問われている」という。終章の寄稿で三好氏も「私たちの仕事は老いと障がいという、アイデンティティを失いそうな危機に直面している人を支えること」「アイデンティティを支えているものの一つが生活習慣である。チューブやオムツや機械浴といった特別なやり方をしたのでは、老人の生活習慣を根こそぎ壊してしまう」と指摘。そして「いい介護とは何か。高度な専門性でも、やさしさやまごころでもなくて、『老人がイヤがることはしない』ということではないか」と自問自答する。
本書を読んでいて、何度かつい笑ってしまった。その1つが村瀬さんの目の前で、認知症予防のための脳トレとして92歳の夫が82歳の妻から掛け算をやらされる場面。「1かける1はなんぼね」。夫が答えると「2かける2は?」。夫が正しく答えるたびに妻の顔が輝く。ところが「2かける5」になると、なかなか答えが出てこない。妻は「ほら、言うてごらん。2・5たい」と繰り返す。「2・5はどうなっとるとね」。そしたら、夫がパッと顔を挙げて「10」ではなくこう答えた。「俺には二号はおらん」。「もうびっくりです」と村瀬氏は当時を振り返る。