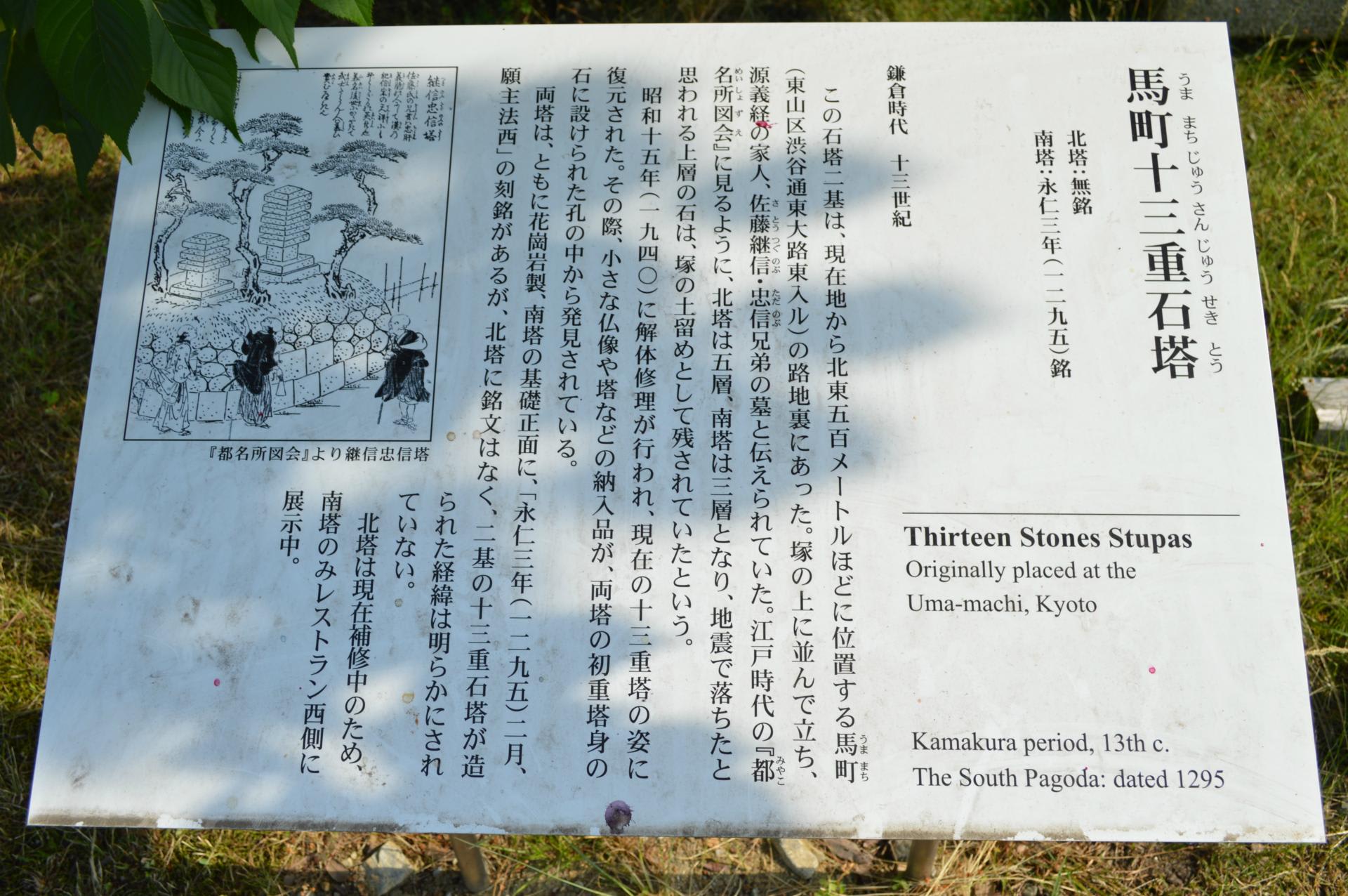現世と異界が接する場所とされ、
近くに陰陽師・鬼一法眼の屋敷があったという。
義経は法眼が秘蔵する「六韜(りくとう)」の兵書を奪おうと
法眼の末の皆鶴姫(『義経記』では幸寿前)に接近、
契りを交わして兵書を盗み出させた。
義経は兵書を一字一句もらさず読み通して去り、
後に残された姫君は嘆きのあまり亡くなってしまう。
東北地方には、皆鶴姫が島流しにあって
気仙沼で亡くなったという話が伝わる。
関連記事 ➡ 一条戻橋



正しくは四海唱導妙顕寺といい、日蓮宗の大本山の1つである。
日蓮聖人の孫弟子に当たる日像上人が、元亨元年(1321)に、
京都における日蓮宗最初の道場として創建したのが当寺の起こりである。
建武元年(1334)には、後醍醐天皇から法華宗号と勅願寺の綸旨(詔の趣旨)を受け、
法華宗最初の勅願寺として洛中洛外の宗門の第一位に認められた。
しかし、度々の法難と災禍により寺地を転々とし、
天正11年(1583)に秀吉の命により西洞院二条の旧地から現在地に移された。
その後、天明の大火(1788)で焼失したが、天保5年(1834)に再建され、今日に至っている。
寺宝として尾形光琳筆の「松竹梅」図三幅などがあり、
塔頭の泉妙院には、光琳と陶工として有名な弟乾山の墓がある。 京都市
妙覚、立本、妙蓮、本隆寺は当寺からの分出である。
寺宝に「後小松天皇宸翰御消息」がある。
光琳の墓 塔頭善行院の南に接した一画、塔頭泉妙院の境内の2ケ所にある。

本堂の前には、「妙顕寺型灯籠」といわれる石灯籠がある。
手前の大きな石柱は 大正11年4月11日 建立


祖師堂


鬼子母神堂


鐘楼

慶中大菩薩
石鳥居 延享4年(1747)正月建立


石鳥居 大正9年建立


鐘真屈(しょうきんくつ) 日蓮・日朝・日像の遺骨を納めてある







単立寺院



百々御所とよばれる格式高い門跡尼院で、
寺伝によると景愛寺中の福尼寺を、応安年間(1368~75)
光厳天皇皇女華林恵厳禅尼によって現在の地に再興されたのが起こりという。
その後、皇族や公家より入寺されることが多く、
特に江戸時代初期には後水尾天皇皇女久厳尼・理昌尼王が入寺されてより
歴代皇女が住持となり、皇室との関係深い門跡寺院として栄えた。
天明の大火で焼失した。本堂は天保年間(1830~44)に再建されたものです。
書院の襖絵は、光格天皇の勅命による円山応震筆、吉村孝敬筆がある。
勅作堂には光格天皇作の阿弥陀立像を安置し、傍らに足利義政夫人日野富子の坐像がある。
寺宝は多く、光格天皇遺愛の人形をはじめ、
古式豊かな遊戯具(双六、投扇興、買覆い)等多数ある。
これに因んで「人形寺」とよばれ、毎年春秋2回人形展を行い、
人形塚では人形の供養が行われる。
昭和12年 建立

人形塚

「万勢伊さん」と呼ばれる江戸時代の御所人形が、寺に残っています。
後西天皇の皇女本覚院宮様の持ち物だった。
書画などに卓越した才能を持ち、信心深かった宮様は、ことのほかこの人形を愛され
その気持ちが、いつしか人形に乗り移った。
人形は、昼は書のお手伝いを、日が暮れると行燈を提げて寺の周囲を夜回りした。
本覚院宮様の死後も二人の皇女に仕えたが、
同寺の尼僧によって魂を抜かれた。
これが人形供養のはじまり、という。
本堂

庫裏

宝鏡寺第15世溪山禅師は、義政と富子との間に生まれた娘である
日野富子の坐像

関連記事 ➡ 華開院 日野富子 墓所