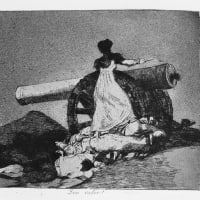上の絵はユトレヒト(オランダ)の画家、ヤン・ファン・スコーレル(1495~1562)の油彩画「学生の肖像」(1531)である。先日行ったブリューゲル「バベルの塔」展において、ボスとブリューゲルの中間期にあたる画家たちの作品の一つとして展示されていた。
今回はこの「学生の肖像」から喚起された「教育」の根本のようなものについて書いてみたい。
12歳の少年。おそらく裕福な家の子弟である。帽子の赤、胸当てのある黒いジャケット、手にもっている紙片とペン、それらの取り合わせが品位と知性を感じさせる。貴族の子どもだろうが、落ち着きと確信のあるまなざしに思わず惹きつけられた。ボスやブリューゲルたちの絵が並ぶなかで、シンプルで清冽なたたずまいは異彩を放っていた。
現代の子どもたちにはない大人びた、静かで悠然とした構え。いや、若手プロ棋士の連勝記録を更新している日本の14歳の少年、その落ち着いた大人顔負けの風貌にも驚いたが・・。下世話な言い方をすれば、共通点は「人間が出来ている」といえるか・・。
この12歳の少年の肖像画をみて、当時の教養というものの神髄を想像し、さらに人間としての器量、風格さえも感じた。そのバックボーンには、今日でいうところのリベラルアーツが厳然として存在していたに違いない、と逞しく思いを馳せてしまったのだ。
論理、文法、修辞、算術、幾何、天文、音楽、この7部門を教養の根幹としたリベラルアーツ。欧米における教育の基本であり、原型。古代のギリシャ・ローマ時代から継承されている人文の総合知である。
たとえば、ヨーロッパ諸国の高等教育において、選択科目ではあるらしいがラテン語の文法、修辞を学ぶことは、エリートとしての獲得すべき資質育成の象徴ともなっている。フランスの新大統領マクロンは、20歳以上年上のそれも担任教師との結婚で話題になったが、彼が話すフランス語がラテン語の教養に裏付けられた魅力的な言葉づかいだったことも人気を集めた理由らしい。
薄い紙のメモには「神はすべてを与えられるが、何も失わない」という標語がラテン語で書かれてあるという。16世紀には広く知られた格言であり、下部の手摺にも「豊かなのは誰か? 何も欲しない人である。貧しいのは誰か? 守銭奴である。」とある。これはいずれも、1514年に出版されたエラスムスの「格言集」からの引用とのこと。
ここにはリベラルアーツの何ごとも書かれていない。「神を信じて正しく合理的に考えられるようラテン語を学んでほしい」という願いが、このエラスムスの格言に託されている、と筆者は考える。また、ギリシャ由来の民主主義、物事を合理的に考えること。そのためには自由で闊達な精神を育くむこと。そうしたリベラルアーツの端緒にふれる多くの格言をエラスムスは書いた。
「何も欲しないことの豊かさ」とは、リベラルアーツの学知を体得することの究極ともいえるからだ。(確かな知識と自由な人間中心の人文主義を尊ぶエラスムスは、当時の聖職者の偽善を敢然として告発したり、一方でルターや「ユートピア」のトマス・モアとの論争でも知られる。)
現在の日本の教育においても、そうした西欧由来のリベラルアーツの伝統を汲んでいるはずである。戦前はまだ「和魂洋才」なる気風は残存していたが、敗戦後はアメリカ支配の洗礼をうけて、より自由と民主主義の精神は浸透したし、教育もまた、自らが考えで判断できる人間をつくってきたはずである。少なくともリベラルアーツ風でもいい、真実や物事を深く、正しく理解する自由な教養人を育ててきたと信じたい。
すなわち、そんな教養人の代表といえるのは、政治家という職業を持つ人たちである。「人間として出来ている」人たちともいえる。
もう、言いたいことは99%も書いた、ということにしよう。残りの1%にふれると、別の事柄に話がおよんでしまう。ここで筆をおく。
※今回は、カリフォルニア工科大学理論物理学研究所所長の大栗博司氏による記事「リベラルアーツの意義」(東京新聞・夕刊 6/21 )に多くの刺激をうけたことを記しておく。
なにか美しい成長はないか。毎度おなじみ身近な花がふさわしいかと・・。

▲最近咲いたサボテン。今年はいろいろ咲いてくれている。下は、蕾から開花までの1か月の経過。