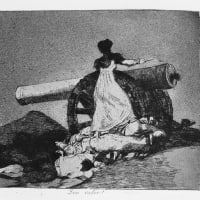田端といえば文士村。芥川龍之介、室生犀星、堀辰雄、佐田稲子らの大正・昭和の作家らが住み、また近年では小沢信夫、奥成達さんらが住んでいると伝え聞いていたが、確かめてはいないし他にもいらっしゃるかもしれない。駅前には文士村記念館があり近代文学にちなむイベントが(直近では、高橋源一郎氏によるセミナーがあったとのこと)行われているようだ。足を踏み入れたことはないし、いつでも行けると思うと、わざわざ出っ張らないのは無精者の習いだろう。なにかきっかけが欲しいところだ。
子供時代には、田端はある種の聖地であった。当時の国鉄、田端駅周辺にはひろい敷地があり、電車のみならず蒸気機関車の操車場があり、車両を回転させて洗車するところを見ることができた。厭きることなく見続けたものだが、今はそんな施設はあるのだろうか。敷地は現在でも広く、山手線・京浜東北線はじめ新幹線もずらり並んで停車しているのを見ると、すこしときめきを覚え、鉄オタと呼ばれる方々の心情は多少わかる気がする。
幼少の頃、まだ西日暮里駅ができる前、その近くの線路に沿った土手道は絶好の遊び場であった。線路内の立ち入りが許されないことは、もちろん承知であったが、雑草の繁みに隠れて侵入する格好の場は子供にとっては目ざといものだ。私たち餓鬼どもは、小遣いをはたいて求めた五寸釘を、地を這うようにしてレールの上におくのである。列車が通り過ぎるとまるい鋼鉄は見事にペシャンコになる。それをやすりで砥ぎ、手裏剣に仕立てたものだ。(隠密剣士、伊賀の影丸、ご存知ですか) 今にして思えばかなり危険なことをしたとおもう。もっと悪いこともしたが墓場にもってゆこう。(こう書くとなにか事件性をおびる。邪気のない遊びだ。2B弾を石にくくり付け駅構内に投げ入れる。派手な破裂音が響きわたって、人々が慌てふためくのを見る。やはり、今なら警察沙汰かな・・)
そんな田端駅南口を出て、西側の土手沿いの途はいまでも散歩コースとなっている。その途中、ほんの五十メートルぐらいに亘った細長い空き地がある。
秋はどんぐり拾いを楽しみ、いまから梅雨の時季にはあじさい(紫陽花)が濃密に咲く場所でもある。

漢字だと「紫陽花」と当てるようだが、ネットで調べてみたらおもしろいことが分った。集(あづ)と真藍(さあい)の合成語だというのだ。「あづさあい」が転じて「あじさい」になったと・・。眉に唾をつけたいが、真藍とはくっきりとした青色で、つまり青い花が集まっている様をあじさいと称したとなれば、信憑性は増したといえるか・・。
咲き始めの薄緑からだんだんと青みが増していく、中には紫へと赤みが強くなっていくものもあって、花こころをそそらせてくれる。梅雨に打たれても、その鮮やかな色彩は、水に滴ってよけいに映えるようである。





ただしこれらのアジサイは西洋種らしく、日本古来のあじさいは「額あじさい」の類のことで見ることは少ないとおもえる。



※ ↑ 額アジサイ。 おおきめの2点はネット上の公開のものを使用させていただく。小フォトはご近所のもの。
追記
花の奥ふかい世界に誘ってくれた人はたくさんいる。文学者では、澁澤龍彦、須永朝彦(幻想文学の泰斗、今は超俗というか恵まれた自然の傍らで文人極みの生活を矍鑠としておくっていらっしゃる。ぜひ「須永朝彦の埴科便り」にアクセスされたし。格調高い歴史仮名遣いと見事な花の写真などを披瀝されている、私にとって見本のような、しかし真似のできないブログである)
そしてもう一人、仏文学者の杉本秀太郎氏がいらしたが、去る5月27日に京都市下京区の自宅にてご逝去なされた。享年84歳であった。
ここに、哀悼の意を表し、氏の仕事を称えたい。特に安野光雅氏との共著「みちの辺の花」は、私の花にたいする蒙昧をいとも軽く、また疾風のように鋭く啓いてくれたのである。合掌
追々記:京都のご実家が歴史的建造物として名高い


〇京都・四条烏丸に開業した呉服商「奈良屋」がご実家。いわゆる京都町屋の典型的な建物として、京都市指定文化財、国の重要文化財となっているそうだ。(財)奈良屋記念杉本家保存会が維持運営