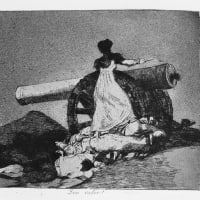雨がすること、と書いてこの時期の、何処かの洪水を心配したのではない。(追記)
日本人は「梅雨」という季節に馴れ親しむ心性がある。人それぞれに感慨を思いおこさせる「多雨」の時季だ。日本人なら単純に、雨降りを待望む農民と、退屈さを愉しむ町民の風情は、自明的に理解できる。
そう、紫陽花や緑の美しさを愛でる季節でもある。一方、お天道様を拝めない、つまり洗濯物を干せない、そんな鬱屈した生活感情があって、そのどちらかにも揺れ動く。そんな揺れる心も、「日本」に再帰させる。実に面白い。
とつぜんで申し訳ないが、モームの短編に『雨』がある。随分まえに読んで粗筋さえも忘れてしまった。不思議にも、後味のような読後の印象は、心の奥底に粘りついている。
春をひさぐ淫らな女と、その女を啓蒙するというか神の道に導く聖職者の話だ。女は善良になってゆく・・。場所は南洋の島だ。シンガポールのラッフルズ・ホテルとか、ゴーギャンの実作を目ざとく見つけ、それを売買していたモーム。
そんな彼の実生活を想像してもらえれば、モームを読んだことがなくても、大英帝国が支配した時代の南洋、あの辺の土地柄や人々の生活を想像できるかと思う。
とにかく、雨季が長い(現在はどうだろう)。日本の梅雨よりも、さらに鬱陶しいイメージがモームの文章から感じられた。
来る日も来る日も雨が降り続ける。聖職者はたぶん牧師で、偶像さえも禁止するプロテスタンティズムのキリスト者。なんと、牧師の高潔な信仰心は、ペイントが剥げるように溶けて流れてしまう。あろうことか、聖職者が長雨のせいで生粋の男になってゆく(野獣か・・)、そんな感じだ。
ある日、牧師は女を犯す。信仰にめざめ、善良さを身につけつつあった女は、まさに絶望の極みに陥る。当然だ、神から辱めをうけるのだから・・。女の淫らさ、性の魅力、それらは鑑賞する側(女性も含めて)が感じてほしい。それは、たぶん監督の恣意力だったのだろう?
牧師は、獣欲を満たした唯の男だったことを悟り(?)、自死する。
映画はかなり前に見たのだが、記憶が薄く、断片的にしか思いだせない(後で、検索する。注※)。
そんなストーリーであるのに、なぜか「雨」が人間を狂わすようなニュアンスが、読後も映画を見た後でも感じさせた。
英国も日本も島国で、その心性もウェットなところがあるので、そういう展開はかなり面白く、結末をふくめて抗えない人間の弱さを、モームは表現したかったのではないか。
それは、人を差別するという白人の心性に気づいた、モームは先進的なイギリス人であった。(そのことを突然思いついて書いている。)
アメリカにおける黒人差別運動がいろいろな展開を繰り広げているのに、日本のマスコミではほとんど報道されない。国歌の星条旗の歌詞の内容が取り沙汰され、アメリカ国歌そのものを廃止しようとか・・。
西海岸シアトルのどこかの一角で、解放自治区が誕生した。黒人差別抗議デモの勢いに恐れを感じて、可笑しいのだが警察が遁走した! で、どうなるのだろうか?
ガバナンス機能がなくなれば、自主的に市民が「街」をマネージメントする(安全と秩序、そして生存)。
まず、食事を優先して、困窮者にふるまう。コロナ禍の第2波のなかでも、みんながボランティアで参加している。あるブロックでは、運営の責任者が15,6歳の高校生だって!。(幼児の初めてのお遣いよりも、面白くてインパクトあるファクトだと思うのだが・・)。
歴代大統領等の銅像取り壊しへの動きは、マスコミでも少し触れられている。しかし、それらの社会・歴史的背景にまったく触れない。日本のメディア情況は、惨憺たるものだ。人々の関心を満足させるだけのための、都知事選挙、コロナの第2波の動き、そんな国内情報だけが中心だ。
いずれアメリカの情勢も、後追い的に池上彰が解説するんでしょうが、たぶん日本人には「ぜんぜん関係ない」という印象を持たれるんだとおもう。世の中は動くようにしか動かない。
幸い、日本人は梅雨というレインシーズンがあるので、雨によって正気が狂うことはない。めでたし、めでたし。だったら良いのだけれど。
(注※)ウィリアム・サマセット・モームの小説『ミス・トンプソン(雨)』に基づき1922年ニューヨークで初演されたジョン・コルトンとクレメンス・ランドルフ作の戯曲『雨』の映画化であり、ルイス・マイルストンが監督・製作、ジョーン・クロフォードとウォルター・ヒューストンが主演。名画座で観たのか、記憶にないのだが観たと思う。ジョーン・クロフォードの顔を見て、なんとなく思い出してくる。ルイス・マイルストン監督といえば、『西部戦線異状なし』『オーシャンと11人の仲間』の監督であった! (リメイク版はなかったかな?)


▲本降りになる前に、谷中霊園の出口で見かける。(以前からずっとあったけど、昨日カメラに収めようと思った)
(追記):投稿してから後、九州地方で雨による実害が出ているニュースがあった。地方によっては、災厄をもたらす激しい雨が当たり前となった。「梅雨」さえも、温暖化によって失うことになりそうだ。(2020.7.04 早朝に記)