妻が見ているTOKIOのテレビ番組の、本場インドのカレー料理特集を観た。カレーに使われるスパイスの種類は、あらかた把握しているつもりだったが、「ヒング」という名のスパイスの存在を知り、猛烈に興味をそそられた。
主に、南インド料理に使われているスパイスで、コクと香りの総元締め的存在。これこそがカレーらしさを決める、最終兵器のような役割があるとも・・。
デリーのスパイス専門店で、TOKIOの長瀬くんが、にやにやする店員に促されて「ヒング」の香りを嗅いでみたら、瞬間のけぞって大声を発した。くさやのような強烈な臭いだという。その派手な驚きように、周りのインド人たちはやんやと歓ぶ。
「ヒング」というスパイスは、なんと「悪魔の糞」と呼ばれているとのこと。その理由は、果物の王様ドリアンのような強烈なにおいを放つからだ。「くさや!」だと言った長瀬くん、あなたは正しい。
しかし、これではまだ、このスパイスの本質が分からない。不満と興味がないまぜのままボルテージは高まる。
番組はそれから、一般家庭でのカレー料理の作り方を見聞するコーナーにうつった。具は、油で揚げたジャガイモのみ。カレーは、多種多彩なスパイスを使って、手際よく作っていく。一方で、クミンシードやカレーリーフを投入してご飯を炊く。そして見る間に、本場の極上カレーライスが完成(編集してあるから所要時間不明)。
長瀬くんによれば、バターの油「ギー」と、フレッシュトマトをジュースにした旨味、そして「ヒング」が、カレーの美味さ、コクと香りを創りだしたのではないか、と結論をだした。
この「ヒング」なる存在は、永遠不滅のわがカレー魂に火をつけた。「ジャガイモ、わが愛」で書綴ったように、いただいたジャガの最後の分をつかってカレーをつくることにした。もちろん「ヒング」を使ってのレシピ新開発のために。
さっそく西日暮里にあるインド系食品店に行った。テレビで見た樹脂状の原形のものはなく、容器にパウダー状のヒングが入ったものしかなかった。密封されていて、円形状の口をカッターナイフで開ける。精製した(熱を加えた?)からであろうか、臭いはそれほどでもなく、とはいえドリアンに似た独特の匂いが漂ってくる。

▲「ヒング」なる文字はどこにもない。商品名「ASAFOETIDA POWDER」ムンバイにある会社の製品で、輸出専用とのこと。薬・栄養剤の容器にしかみえない。ネットでは、この容器を瓶の中にいれて保存している方がいた。臭気が気になるのか・・
「ヒング」の正式名称は「アサフェティダ」という。イラン、アフガニスタン原産で、セリ科の多年生植物。1mの高さに成長し、太い茎から樹脂が染みだして、それを固めたものを使う。和名は「阿魏」(あぎ)といい、漢方では鎮静薬として用いられる。
その他、「ジャイアント・フェンネル」という呼び名もある。ちなみに「ヒング」(hiṅgu)はサンスクリット語だ。
「複数の揮発性硫黄化合物を含みニンニクやドリアンに似た強烈な臭いがあるが、油で加熱すると強烈な臭いは消えて、タマネギのような風味となる。インドにおいて香辛料として幅広く用いられる他、ウスターソースの原料としても使われている。強烈な臭気を喩えて、Devil's dung(悪魔の糞)という呼び名もある」と、ウィキペディアにも同様のことが書かれていた。
もう、やめられない、とめられない、ヒング様。
天然の「味の素」でもあるという、「ヒング」を使った初めての料理(大匙2杯ほど)。ジャガイモの入ったカレーは、やはり市販のルーを使うと間違いないのだが、今回ばかりはすべて家にあるスパイスを総動員して、ジャガイモ主体の野菜カレーをつくった。いつも使う、セロリ、生姜を忘れたのだが、出来は上々であった。
「ヒング」を知らなかったのは、たぶん日本ではまだ、よく知られていない南インド料理の定番スパイスだからではないだろうか。それにしても、カレー料理を紹介した番組やレシピ本はいろいろ見てきたつもりだったが、「ヒング」を使ったカレーは初めてだ。味を占めたところで、今後も、いろんなカレーにチャレンジしたい。

▲また、禁を破って、食べ物の写真をアップ。食べ終わった後の残りで、素材は在りあわせのもの。美味そうに見えないのがつらい。



















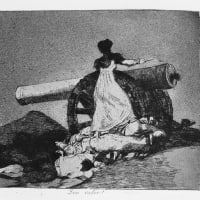

作ると即食べました。後の祭りですな。
食べ物の写真は、基本撮らないことをモットーにしています。悪しからず。