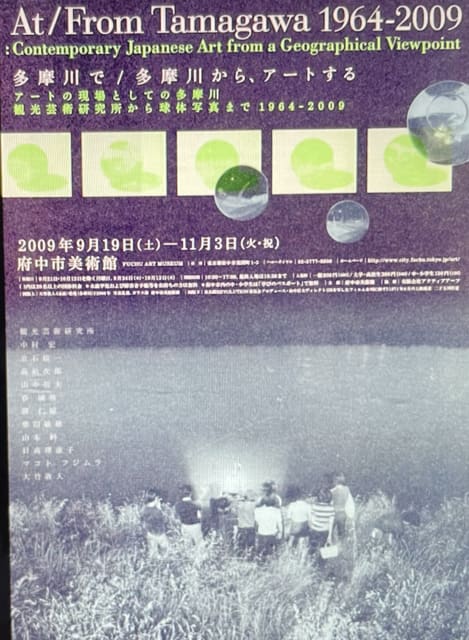1976年日本で初めての田中保の展覧会が「知られざる巨匠」として、新宿の伊勢丹で開催され、34点の作品が紹介された。1904年、田中は18歳の若さで単身シアトルに渡米し、画家になり、1920年にパリに移住した。パリで画家として名声を得るが、54歳で亡くなるまで一度も祖国日本の地を踏むことはなかった。今となっては信じられないが、当時の日本の画壇から田中は評価されなかったのである。
20世紀モダニズムが台頭していた華やかな芸術の都、パリで活躍した日本人画家がいた。しかし、日本では1970年代の初個展までその画家が埋もれていたのはどういうことだろうか。
現在埼玉県立近代美術館で「シアトル→パリ 田中保とその時代」展が開催されている。(10月2日まで)この展覧会では、田中の画家としての激動の道のりを振り返りながら、同時代活躍した画家の作品と共にその足取りを作品と資料で再検証している。田中の足取りを追いながら、その作品を一部紹介していきたい。
田中は1886年(明治19年)金融業を営む父(元岩槻藩士)の元、埼玉県の岩槻で9人の兄弟の4男として生まれた。県立第一中学校(後浦和中学校と改名し、現在の浦和高等学校)に入学するが、3年生の時に父が急逝したため、一家は破産し、離散。9人兄妹のうち、3兄弟はバラバラで海外に行くことになった。田中は中学校卒業後してすぐの1904年、アメリカのシアトルに船で渡った。
移民が押し寄せたシアトルで、田中は農家の手伝い、ピーナッツ売り、コック見習いなどをしながら、英語も学んだ。そして、シアトル市立図書館や美術館、展覧会などに通い、独学で絵を勉強した。1912年頃オランダ人画家フォッコ・タマダの主宰する塾に入り、指導を受けた。当時同じようにアメリカに渡った日本人画家に清水登之や国吉康夫がいるが、清水とはタマダの塾で一緒に学んだ。
この展覧会のセクション1と2では、シアトルでの田中の初期の作品が展示されている。力強い自画像と濃淡の浮かび上がる裸婦の木炭のデッサンに高度な描写力が裏付けされている。この頃の清水の作品も展示されている。

田中保『自画像』(1915年頃)埼玉県立近代美術館蔵
日本でアカデミックな絵画教育を受けずに、欧米の作家が描いたような「黒シートの裸婦」(1915年頃)のような作品を短期間で描けるようになるとは、驚きだ。画家という職業でアメリカンドリームを夢見て、ひたすら貪欲に技術を磨いていったのかもしれない。

田中保『黒シートの裸婦』(1915年頃)埼玉県立近代美術館蔵
展覧会には1912年頃から出展し始め、1914年28歳の時、ワシントン州立協会ギャラリーの北西画家展で、海景画が高く評価され、作品も売れ、徐々にメディアからも注目されるようになる。
1914年、シアトル美術協会で作品を展示したとき、田中の講演会を聞いた詩人で美術評論家のルイーズ・ゲプハント・カンは田中の裸婦の作品を高く評価した。後に田中とルイーズは結婚したが、異人種間の結婚は当時許されず、ルイーズはアメリカ国籍を失った。
1915年サンフランシスコで開催された万国博美術部門にアメリカ代表として選ばれ、『マドロナの影』(1914年)が展示された。黄色の背景に横向きの表情の見えない女性が、オレンジがかった布を持ちながら、すくっと立っている。あたかも夢の中でぼんやり現れた女性を描いたかのような幻想的な油彩作品。この作品は評価が高く、田中の代表作の一つであろう。この頃田中のアメリカでの評価は確立され、シアトル美術協会でも指導をするようになった。
1915年、シアトル市立図書館展示室で初めての個展を開いた田中は、裸婦をメインに描くようになった。しかし、裸婦は「挑発的で非道徳的」と、たびたび展覧会で批判を浴びる。その批判に対して田中は、地元紙に「芸術のあるべき姿」として、「芸術のあくまで個人にかかわる問題であり、個人の心的、精神的な活動の表明である」(『画家タナカ・ヤスシ シアトルとパリにかけた夢』図録 1997年 埼玉県立近代美術館 p 133)という主張の寄稿をした。その後も批判に対するより強い主張の寄稿文も書いたが、アメリカ人には理解されなかった。
シアトルには16年在住したが、田中とルイーズは非難を浴びたアメリカを去って、1920年パリへ約100点ほどの絵画を伴って移住した。エコール・ド・パリの時代、自由な空気の流れる芸術の都で、田中は精力的に個展を開いたり、作品をサロン・ドートンヌなどのサロンやグループ展に毎年出展した。シアトルで酷評された裸婦の作品もパリでは高く評価された。自分の画塾も開いている。
モダニズムの旗手といわれた詩人のエズラ・パウンドや小説家ジェイムス・ジョイス、ヘミングウェイたちとも交流をしながら、田中の才能は大きく開花し、政府が作品を買い取るほどフランスの画壇で成功をおさめたのである。パリでの成功は、文学者も含めて様々な関係者にコネクションが強かったルイーズの助言やサポートも大きかったかもしれない。
田中は、日本人画家たちと距離をおき、交流が少なかった。日本で美術教育を受けず、日本の画壇にコネクションもなかったためか、画壇は田中を受け入れず、1924年第5回帝展に落選した。フランスで成功した日本人画家に対する嫉妬ややっかみなどもあったのではないか。もし、田中の吸引力のある作品群が当時の日本画壇に紹介されていたら、若い芸術家たちへの衝撃は大きく、何らかの強いインスピレーションをもたらしたであろう。
田中は54歳で亡くなるまで日本には一度も戻らなかったが、日本に対する望郷の念を抱き続けていたに違いない。この展覧会に展示されているいくつかの海の風景画の構図やモチーフは、当時ヨーロッパで流行ったジャポニズムも感じさせ、西欧と東洋の融合された田中のエキゾチックな作品は注目されたに違いない。
セクション4の「パリの異邦人、ヤスシ・タナカ」で展示された服を着た作品の女性像は、ルノワールの描く女性のように、頬を赤く染め、夢見がちな眼差しでゆったりと座っている。ルイーズがモデルと言われる『黄色のドレス』(1925-30年)の女性の瞳は、穏やかで相手を包み込む優しさが滲み出ている。ルイーズにとって、自分たちの感性の合うパリに来て、良き理解者に恵まれた満足感や安堵感があらわれているかのようだ。

田中保『黄色のドレス』(1925年-30年)埼玉県立近代美術館蔵 昭和57年度埼玉銀行寄贈

田中保『黒いドレスの腰かけてる女』(1920-1930年)埼玉県立近代美術館蔵 昭和57年度埼玉銀行寄贈
『青いコートを着て腰かけてる女』は、女優の見せるような可愛らしく華やかな表情で、黄色のバックと青の服の対比のせいか、画面に惹きつけられる。
対して、裸婦の作品群が展示された「1924年の活動」というコーナーでは、一瞬別の次元に迷い込んだかのような錯覚に陥る。官能的でヴィーナスを思わせるようなふくよかな体形。様々な画風の眩い裸婦像が配置され、田中の精力的な仕事の跡がわかる。海の前で座る裸婦の後姿を描いた『背中の裸婦』(1920-1930年)は、ブルーの海を背景に、白みがかった肌色の腿から放たれる月光の反射光が際立つ。田中の異国での孤独感を反映しているかのようだ。

田中保『背中の裸婦』(1920-1930年)埼玉県立近代美術館
最後のコーナーに猫を描いた2作も印象的だった。『花と猫』(1920-1940年)は、赤い花の隣の窓際に座る猫をパステルで丁寧に描写している。こちらもバックは黄色で猫が黒。パステルの味わいを最大限にひき出している。もう片方の焦げ茶で固めた油彩の『猫』(1920-1930年)は、写実的で味わいがある。

田中保『猫と花』(1920-1940年)埼玉県立近代美術館
1920年代日本画壇で冷遇された田中保と田中を支え続けたアメリカ人の妻のルイーズが、令和の時代に作品とともに再検証される展覧会の開催によって、田中が海外で残した功績がますます評価されることを願う。
明日のNHK Eテレの「日曜美術館」アートシーンでこの展覧会が紹介されるそうです。
放送日:9月18日(日)9:45〜
再放送:9月25日(日)20:45〜
見出し画像は『サン・ベネゼ橋』(1928年頃)埼玉県立近大美術館 昭和57年度埼玉銀行寄贈
「シアトル→パリ 田中保とその時代」展
会場:埼玉県立近代美術館
会期:2022年7月16日(土)~ 10月2日(日)※会期中、一部作品の展示替えがあります。
前期:8月21日(日)まで
後期:8月23日(火)から
休館日:月曜日(7月18日、8月15日、9月19日は開館)
開館時間:10:00 ~ 17:30 (展示室への入場は17:00まで)
20世紀モダニズムが台頭していた華やかな芸術の都、パリで活躍した日本人画家がいた。しかし、日本では1970年代の初個展までその画家が埋もれていたのはどういうことだろうか。
現在埼玉県立近代美術館で「シアトル→パリ 田中保とその時代」展が開催されている。(10月2日まで)この展覧会では、田中の画家としての激動の道のりを振り返りながら、同時代活躍した画家の作品と共にその足取りを作品と資料で再検証している。田中の足取りを追いながら、その作品を一部紹介していきたい。
田中は1886年(明治19年)金融業を営む父(元岩槻藩士)の元、埼玉県の岩槻で9人の兄弟の4男として生まれた。県立第一中学校(後浦和中学校と改名し、現在の浦和高等学校)に入学するが、3年生の時に父が急逝したため、一家は破産し、離散。9人兄妹のうち、3兄弟はバラバラで海外に行くことになった。田中は中学校卒業後してすぐの1904年、アメリカのシアトルに船で渡った。
移民が押し寄せたシアトルで、田中は農家の手伝い、ピーナッツ売り、コック見習いなどをしながら、英語も学んだ。そして、シアトル市立図書館や美術館、展覧会などに通い、独学で絵を勉強した。1912年頃オランダ人画家フォッコ・タマダの主宰する塾に入り、指導を受けた。当時同じようにアメリカに渡った日本人画家に清水登之や国吉康夫がいるが、清水とはタマダの塾で一緒に学んだ。
この展覧会のセクション1と2では、シアトルでの田中の初期の作品が展示されている。力強い自画像と濃淡の浮かび上がる裸婦の木炭のデッサンに高度な描写力が裏付けされている。この頃の清水の作品も展示されている。

田中保『自画像』(1915年頃)埼玉県立近代美術館蔵
日本でアカデミックな絵画教育を受けずに、欧米の作家が描いたような「黒シートの裸婦」(1915年頃)のような作品を短期間で描けるようになるとは、驚きだ。画家という職業でアメリカンドリームを夢見て、ひたすら貪欲に技術を磨いていったのかもしれない。

田中保『黒シートの裸婦』(1915年頃)埼玉県立近代美術館蔵
展覧会には1912年頃から出展し始め、1914年28歳の時、ワシントン州立協会ギャラリーの北西画家展で、海景画が高く評価され、作品も売れ、徐々にメディアからも注目されるようになる。
1914年、シアトル美術協会で作品を展示したとき、田中の講演会を聞いた詩人で美術評論家のルイーズ・ゲプハント・カンは田中の裸婦の作品を高く評価した。後に田中とルイーズは結婚したが、異人種間の結婚は当時許されず、ルイーズはアメリカ国籍を失った。
1915年サンフランシスコで開催された万国博美術部門にアメリカ代表として選ばれ、『マドロナの影』(1914年)が展示された。黄色の背景に横向きの表情の見えない女性が、オレンジがかった布を持ちながら、すくっと立っている。あたかも夢の中でぼんやり現れた女性を描いたかのような幻想的な油彩作品。この作品は評価が高く、田中の代表作の一つであろう。この頃田中のアメリカでの評価は確立され、シアトル美術協会でも指導をするようになった。
1915年、シアトル市立図書館展示室で初めての個展を開いた田中は、裸婦をメインに描くようになった。しかし、裸婦は「挑発的で非道徳的」と、たびたび展覧会で批判を浴びる。その批判に対して田中は、地元紙に「芸術のあるべき姿」として、「芸術のあくまで個人にかかわる問題であり、個人の心的、精神的な活動の表明である」(『画家タナカ・ヤスシ シアトルとパリにかけた夢』図録 1997年 埼玉県立近代美術館 p 133)という主張の寄稿をした。その後も批判に対するより強い主張の寄稿文も書いたが、アメリカ人には理解されなかった。
シアトルには16年在住したが、田中とルイーズは非難を浴びたアメリカを去って、1920年パリへ約100点ほどの絵画を伴って移住した。エコール・ド・パリの時代、自由な空気の流れる芸術の都で、田中は精力的に個展を開いたり、作品をサロン・ドートンヌなどのサロンやグループ展に毎年出展した。シアトルで酷評された裸婦の作品もパリでは高く評価された。自分の画塾も開いている。
モダニズムの旗手といわれた詩人のエズラ・パウンドや小説家ジェイムス・ジョイス、ヘミングウェイたちとも交流をしながら、田中の才能は大きく開花し、政府が作品を買い取るほどフランスの画壇で成功をおさめたのである。パリでの成功は、文学者も含めて様々な関係者にコネクションが強かったルイーズの助言やサポートも大きかったかもしれない。
田中は、日本人画家たちと距離をおき、交流が少なかった。日本で美術教育を受けず、日本の画壇にコネクションもなかったためか、画壇は田中を受け入れず、1924年第5回帝展に落選した。フランスで成功した日本人画家に対する嫉妬ややっかみなどもあったのではないか。もし、田中の吸引力のある作品群が当時の日本画壇に紹介されていたら、若い芸術家たちへの衝撃は大きく、何らかの強いインスピレーションをもたらしたであろう。
田中は54歳で亡くなるまで日本には一度も戻らなかったが、日本に対する望郷の念を抱き続けていたに違いない。この展覧会に展示されているいくつかの海の風景画の構図やモチーフは、当時ヨーロッパで流行ったジャポニズムも感じさせ、西欧と東洋の融合された田中のエキゾチックな作品は注目されたに違いない。
セクション4の「パリの異邦人、ヤスシ・タナカ」で展示された服を着た作品の女性像は、ルノワールの描く女性のように、頬を赤く染め、夢見がちな眼差しでゆったりと座っている。ルイーズがモデルと言われる『黄色のドレス』(1925-30年)の女性の瞳は、穏やかで相手を包み込む優しさが滲み出ている。ルイーズにとって、自分たちの感性の合うパリに来て、良き理解者に恵まれた満足感や安堵感があらわれているかのようだ。

田中保『黄色のドレス』(1925年-30年)埼玉県立近代美術館蔵 昭和57年度埼玉銀行寄贈

田中保『黒いドレスの腰かけてる女』(1920-1930年)埼玉県立近代美術館蔵 昭和57年度埼玉銀行寄贈
『青いコートを着て腰かけてる女』は、女優の見せるような可愛らしく華やかな表情で、黄色のバックと青の服の対比のせいか、画面に惹きつけられる。
対して、裸婦の作品群が展示された「1924年の活動」というコーナーでは、一瞬別の次元に迷い込んだかのような錯覚に陥る。官能的でヴィーナスを思わせるようなふくよかな体形。様々な画風の眩い裸婦像が配置され、田中の精力的な仕事の跡がわかる。海の前で座る裸婦の後姿を描いた『背中の裸婦』(1920-1930年)は、ブルーの海を背景に、白みがかった肌色の腿から放たれる月光の反射光が際立つ。田中の異国での孤独感を反映しているかのようだ。

田中保『背中の裸婦』(1920-1930年)埼玉県立近代美術館
最後のコーナーに猫を描いた2作も印象的だった。『花と猫』(1920-1940年)は、赤い花の隣の窓際に座る猫をパステルで丁寧に描写している。こちらもバックは黄色で猫が黒。パステルの味わいを最大限にひき出している。もう片方の焦げ茶で固めた油彩の『猫』(1920-1930年)は、写実的で味わいがある。

田中保『猫と花』(1920-1940年)埼玉県立近代美術館
1920年代日本画壇で冷遇された田中保と田中を支え続けたアメリカ人の妻のルイーズが、令和の時代に作品とともに再検証される展覧会の開催によって、田中が海外で残した功績がますます評価されることを願う。
明日のNHK Eテレの「日曜美術館」アートシーンでこの展覧会が紹介されるそうです。
放送日:9月18日(日)9:45〜
再放送:9月25日(日)20:45〜
見出し画像は『サン・ベネゼ橋』(1928年頃)埼玉県立近大美術館 昭和57年度埼玉銀行寄贈
「シアトル→パリ 田中保とその時代」展
会場:埼玉県立近代美術館
会期:2022年7月16日(土)~ 10月2日(日)※会期中、一部作品の展示替えがあります。
前期:8月21日(日)まで
後期:8月23日(火)から
休館日:月曜日(7月18日、8月15日、9月19日は開館)
開館時間:10:00 ~ 17:30 (展示室への入場は17:00まで)