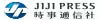「買い物弱者」増加を想定 コンビニ 高齢者対応強化 (4月25日神戸新聞より)
(※青系文字がmasumi)
コンビニの買い物弱者支援は一般紙の記事になります。
でもガソリンスタンド業界のこういった話はあまり記事にはなりません。
“住民出資の村営”や“富山の置き薬方式の灯油配送”になって初めて、(地域版で)記事になるくらいです。
多くは“値上げ”の報道です。
この業界の内実を伝えるような報道はありません。
簡単に諦めてはいけない。にあるような“努力が実を結んでいる元気の良い”店も確かにあります。
それはそれで素晴らしいことです。
けれども、自店の経営努力ではどうしようもない“卸格差”、これによって顧客を失ってきた販売店が多いことも事実です。
一般の個人客が安値のセルフを好んだ結果、
店頭では閑古鳥が鳴いているような店でも、灯油・軽油・工業用潤滑などの配達や洗車等で何とか収支を保っています。
低マージンの燃料油では赤字で、別の事業や不動産収入で収支を合わせているところもあります。
自身は給料を取らずに年金で生計を立てながらーというところもあるようです。
それでも世の中のほとんどの消費者はこの業界の内情を知らない。
このブログでガソリンスタンドの事を書き出して、同業者の方から多くのコメントやメールを頂きました。
批判的な内容もありましたが、多くは共感と応援の声です。
その中には頭の下がる行いが記されていることもあります。
不採算を承知での独居老人宅への小口配達、そんなことは地場店には普通のことです。
そうではなく(配達ではなく)、
ポリ容器から石油ストーブに灯油を移し替えてあげるために、週に3回出向いている同業者(従業員はいない販売店)がいます。
>赤字だけど、 火事になるよりはいい
元売が非効率だとして切り捨てようとしてきた小規模業者にこそ、こういう経営者は多い。
地域の中で唯一になるまで営業を続けたお店も、その前に閉鎖したお店も、又その前に閉鎖したお店もー
それは過疎地だけに限らず、中山間部でも、都市部でもそうです。
規制緩和以降の卸格差による販売価格差で顧客(販売数量)を減少させ、低マージン経営を余儀なくされながらも、閉鎖の“その日”まで燃料供給を担ってこられたのです。
4月26日燃料油脂新聞より
SS過疎地問題 将来への展望
福島県内における取り組み事例(下)
(SS過疎地@支援の条件は町民の利用率の続きです)
-実態調査事業を踏まえての将来展望は
「町で唯一の給油所が廃業した場合の対策として、一つは隣接する地域から燃料供給することが考えられる。
もう1つは町が核となって町ぐるみで第三セクター的に現給油所の運営維持を図る。
その際は給油所だけでなく、複合施設としてワンストップで商品・サービスを提供する形が望ましい。
なぜならほかの小売りサービス業も単独では商売継続が難しいから。
ほかに道の駅を利用する方法もあり得るだろう」。
ー調査事業を通じて得られた成果は
「町にも大きな問題意識を持ってもらえた。
今後の対応について町、県石商、石油連盟、資源エネルギー庁、県が連絡と協議を行う土壌ができた。
地域住民に対してもSS過疎問題の現状を説明することで、一定の理解が得られた。
住民の消費行動やSSの商売上、あまり効果や影響を与えることはできなかったが、住民側にも一定の危機感が生まれたと思う」。
ー県石商が果たしていくべき役割とは
「県石商の仕事として石油流通に関する領域のなかで、自治体や住民にいかにSSがなくなることへの危機感を感じてもらい、SSの必要性を認識してもらうか。どちらかといえば受け身だが、こちら側から危機感を伝えなければ始まらない。
基本的な出発点と言えるのが、自治体における防災の町づくりにおいて、災害対応の位置付けとしてSSの役割と必要性を明文化し、町ならば町の事業として対策を講じていくことができるかどうかにある。
それができて初めて町と県石商が協議し、さらに県やエネ庁が制度的な金融支援を行うというように、三位一体の協力体制をつくり、それを維持することが課題になってくる」。
ーSS過疎地問題への向き合い方は
「SS事業存続の観点から言えば、商売が成立さえすれば果たして問題はないのかということ。
離島予算のような支援は可能か、また有効か。
抜本的な解決策はなく、また県石商が出来ることも小さいが、まずは問題に気付いてもらい、事前に地域とSSが話し合い、対策を講じることが大事なのではないか。
なぜなら自然災害は待ってはくれない。
町や村が隔絶されれば人命に関わる。
とくに自治体にはSSの存廃問題というより、住民の生命と財産を守る意識が強く求められる」。
ーこれからの対策として必要なことは
「SS過疎地問題について国が県市町村に直接働きかけ、もっと本腰を入れて取り組むための仕掛けをつくり、そのための支援措置や予算を確保することが必要と考える。
石油業界の実態を知らない自治体が多いことから、第一歩として認識を深め、危機意識を持ってもらう。
しかし問題は切実で、すでに具体的な対策を打つ時期に来ている。
石油業界としても、たとえば元売会社が当該SSに“過疎手当”を支給する方法などもあるはず。
また公益的活動として消費者から石油への正しい理解が得られるよう努力しながら、需要防衛に業界全体が協力していくことも重要。
安易に費用対効果を求めたり、目に見えないところを評価しないのでは対策を進めることはできない」。
※
地域の中で唯一のガソリンスタンドになっても、町民の利用率は16.9%しかありません。
調査事業によって住民側に危機感を持たせることができたとしても、
>住民の消費行動やSSの商売上、あまり効果や影響を与えることはできなかった
利用率16.9%
この数字をどう思われますか?
価格に拘らずに高値店であっても利用されている消費者の皆さんには信じられないと思いますが、
近隣に10円20円という価格差の安値店がある地場店の多くが「ま、そんなもんだろうな」、と納得しているのではないでしょうか。
もし昔のように価格差がなければ?
もちろん通勤等で通る沿線上の、町外の店を利用する人もいるでしょう。
サービスの違いで町外の店を選ぶ人もいるでしょう。
人間ですから相性もあるでしょう。
それでも利用率は70%~90%はあったのではないでしょうか。
では、価格差がなくなったら?
危機感を持ってもらった上で、価格差がなくなったら?
昔の利用率に戻るかというと、残念ながら戻らないと思います。
16.9%が、良くて60%くらいじゃないかなと思います。
今はもう、住民出資の村営でなければ利用率は上がらないのではないでしょうか。
4月28日追記
価格差最大10円超
「安易に追随できない」地元業者は冷静な対応
自治体向け契約などへ影響も
価格の二極化は市町村向けの契約価格にも影響を及ぼす。
「交渉の度に取り上げられるが、いまのところ担当者との話し合いで、われわれの置かれている立場や実態を話し、理解してもらっている。しかし確約をもらっているわけではない。大きな価格差のままの状態が長引けば、出方も変わっくる可能性がある」
※
>われわれの置かれている立場や実態を話し、理解してもらっている
以前は理解してもらう“術”もありませんでした。
公用燃料は夫婦喧嘩のもと
自民党の二階俊博幹事長は26日、東京都内のホテルで講演し、「マスコミは余すところなく記録を取って、一行でも悪いところがあったらすぐ首を取れと。なんちゅうことか」と述べ、メディアの報道姿勢を批判した。東日本大震災をめぐる発言で復興相を辞任した今村雅弘氏が念頭にあり、「人の頭をたたいて血を出したという話ではないのだから、いちいち首を取るまで張り切っていかなくてもいいのではないか」とも語った。
二階氏の発言に野党は反発した。民進党の安住淳代表代行は記者会見で、「都合のいいところだけ報道させればいいという意識がある。そこが問題だ」と指摘。共産党の穀田恵二国対委員長も会見で「本末転倒だ。報道の自由、メディアの存在意義を根本から否定しかねない発言だ」と述べた。
※今村氏を擁護するかのような“問題発言”。
再稼働に必要な審査の申請内容に不備が指摘され、審査が保留された日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」(茨城県)について、原子力規制委員会の田中俊一委員長は26日の定例記者会見で「あまりに不備過ぎて、本当に福島の事故を反省した上で申請しているのかというほどひどい」と厳しく批判した。
原子力機構は3月、常陽の審査を申請。熱出力は14万キロワットだが、10万キロワットを超えると住民の避難対策が必要な範囲が半径5キロ圏から同30キロ圏に拡大するため、10万キロワットに制限して運転する方針を示した。規制委は25日の審査会合で「出力は審査の大前提。設備と整合しなければ審査できない」と指摘し、審査を保留した。
田中委員長は「ナナハン(排気量750cc)のバイクを運転するが、30キロでしか走らないから(原付き免許で運転を認めてほしい)という話。許すわけにはいかない」と原子力機構の姿勢を批判した。
※
>本当に福島の事故を反省した上で申請しているのかというほどひどい
反省してないんじゃないの?
上のニュースのお二人もだけど。