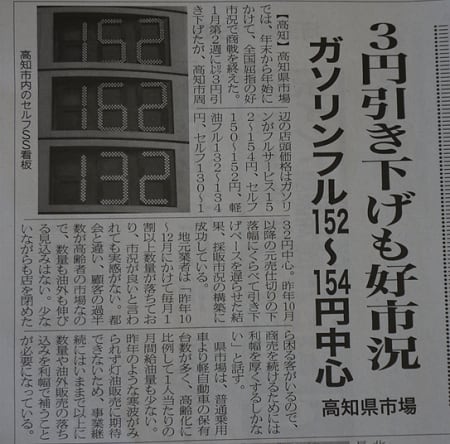1月16日ぜんせきより
販売業者の“声”伝達
各地の販売業者からは、系列玉と業転玉との卸格差は縮小しつつあり、需給環境に改善の兆しがみえるものの、低マージン経営の常態化により、人材確保や後継者問題が浮き彫りとなるなど、SSの存続に強い危機感を訴える声が目立つ。
1月21日ぜんせきより
経営実態調査 販売業者の声 (上)
14年度調査からスタートし、今回で5回目。
系列・業転格差は縮小傾向にあるものの、地場業者の仕入れを下回るような売価が横行しているような現状への悲鳴が各地で散見されるほか、低マージンの常態化で人手不足問題や後継者問題が顕在化するなど、石油製品の安定供給基盤である地場中小SS網の崩壊を危惧する声が高まっている。
中小SS網“崩壊”を危惧
◆低マージン
・業転格差はあまりなくなりましたが、マージンが少なくこれからの商売に自信がありません。少しでも税負担がなくなればとお乗っています。(北海道)
・業転品を低価格で販売している限り、低マージンになってしまいます。従業員に満足に給料も払えない。いくら頑張っても先が見えません。設備、施設などは老朽化しています。更新するだけの資金がありません。私財をつぎ込みながらなんとか運営しています。もう限界です。(東北)
・(石油は)災害時などに必要不可欠な燃料。低マージンなため、人員不足、人員の高齢化が進んでいます。SS運営、維持にはたくさん資金がかかります。全国各地で閉店が増えていますが、マージンが上がれば閉店も少なくなるのではないでしょうか。(関東)
・発券店値付けカードが増え、利幅が低下しています。(中部)
・粗利さえあれば、小売店でも頑張る。後継者も出てくるし、災害対策もできるし、人材確保もできる。いまの家族経営者には厳しすぎます。(中国)
・SS維持費を負担しない客に同じサービスはできませんが、客は理屈をわかっていません。フルサービスSSは5~7円で維持できません。ただただ忙しくなるだけで人は増やせず、従業員は疲れています。(九州・沖縄)
◆後継者問題
・後継者を求む!(中部)
・弊社の販売店がこの10年で5店舗閉店しました。近い将来も閉店する店が(他系列も含め)出ると思います。立地条件は過疎地で小規模店がほとんどです。理由は後継者不在、利益が出ない(赤字)ことでやむを得ない事情です。利益のほとんどは燃料油で、油外はほとんどありません。都市部の価格競争の影響で燃料油マージンは低下し、慢性的な赤字が続いています。困るのは弱者(地域の人々)で、抜本的な構造改革が必要と思います。(中国)
・子どもは現在勤めている会社を辞めて継ぐことも考えてくれましたが、私たちが長年経営してきて全く安心できる時期がなかったので(赤字続きで)、後継者にすることには賛成できませんでした。(四国)
◆人材確保難
・現在も求人をハローワークに出していますが、面接すらないのが現状です。15年くらい前の従業員といまの従業員ではレベルが違い、このままではどうなるんだろうと心配です。(北海道)
・従業員を募集してもなかなかあつまらないので、AI、IOTを活用し、人が少なくてもSSが運営できるシステムを構築してほしい。(東北)
・人材不足で困っています。なにを行うにしても人材が足らないためできません。ローテーションを組んでの営業ですが、従業員に負担が掛かっています。募集を掛けても応募がなく、アルバイトの補充もできません。このような状態でいつまで営業が続けられるか非常に不安です。(関東)
・近年、SSでアルバイトをする学生、主婦が減り、募集をしても全く反応がありません。正社員を何人も抱えると収益が合わず事業継続が困難になります。(近畿)
・休みも少なく、フルサービスで頑張っているが、利益確保が難しい。人材確保のため求人誌への掲載費が多額になっている(月10万円以上)。元売の求人サイトへ掲載しているが全く問い合わせもない。時給を上げることでなんとか人員を確保しているが、人件費がかさむし、長く勤務される方が少なく、いつも人員不足になっている。(中国)
・厳しい環境の中での作業、なかなか人材が確保できない。(九州・沖縄)
1月25日追記
1月23日せんせきより
経営実態調査 販売業者の声 (中)
業転格差、不当廉売・差別対価 安値乱売横行に危機感
・業転品との価格差。元売特約店としての優位性、官公庁入札含めた地元企業の優位性を確立していただきたい(北海道)
・業転品との価格差が大きく、不当廉売と思われる価格が見受けられ、低マージンを強いられている。元売が価格調整をしっかりすべきと思う。(北海道)
・業転品を3割ほど仕入れています。2~5円の差があります。商圏にはPBSSが7円安。系列A・系列Bの各1店が5円安と、業転品で薄めても太刀打ちできません。私のSSにくる業転玉はほとんど系列A・系列Bの製品です。せめて業転玉の価格を同額か2~3円高くしてほしい。正規店を守ってほしいです。(九州沖縄)
・業転品を購入して低価格で販売している業者がいて(セルフ)10円もの差が出ている。元売のブランド料を考えて欲しい。(九州沖縄)
◆不当転売、差別対価
・いまだ、仕入値以下で販売する業者が存在することの不思議。元売統合が進んでいるのに、いまだ需給バランスが崩れているのか。「安い値段=沢山売れる」は時代に合致していないと考えます。業転品は減少傾向とはいうけれど、“業転品んは作らない”くらいの覚悟で精製元売は事業を行ってもらいたい。(北海道)
・長年の一部業者による採算を度外視した低価格販売により企業業績は悪化を辿り、もはやSSの改修工事費も捻出できない状況にある。国や公正取引委員会はもう少し市況対策に迅速、積極的な対応を望む。(東北)
・当SSから500メートル離れた場所に大手流通業のSSがあります。当店の仕入値でガソリンを販売しています。自由競争の時代ですが、あまりにも酷いです。(東北)
・元売が統合され、スポット玉は減少し表面化(安値)しなくなった。ただし同系列の仕切格差がまた発生してきている。元売子会社および大特約店と小規模店との格差が大きくなっている。(関東)
・差別対価です。30分圏内にメーカー直営店ができてから、安売りがあり、価格を合わせて売らなければならないので利益を出すのは大変です。決算で黒字は出ていますが、すべてガソリン以外(LPガス)の頑張りです。スタンドは地下タンク・ローリー、計量機すべてを点検しなければならず、その費用も人件費などを引けば利益はほとんどなくなります。業転品を増やせばマークを持っていかれてしまうので、それもできず、息子が継いでもいいと言ってくれましたが断りました。(関東)
・どうして価格差があるんですか。私のSSは仕入れが高いためセルフより10円以上高く売っても利益が出ないのに、お客様は儲け過ぎじゃないかと言われますが、実情を知ってもらえる方法はないものですか。大変困っています。(関東)
・過疎地でSSを1ヵ所営んでおりますが、SSは地域貢献と考え、いまだ経営しておりますが、SS部門では毎年、赤字の累積です。近郊のセルフSSの価格と、うちのお客様とあまり価格の開きがあっては申し訳なく、尽力している次第です。(関東)
・石油販売業界には、多種の目的が違う会社が存在している。①利益の確保を目的としている地場特約店②採算度外視で販売数量の確保を目的としている会社③大型ショッピングセンターの集客手段を目的としてSSを運営している会社④その他。以上の通り、様々な目的の会社が存在することにより大きな販売価格差が発生し、健全な販売活動が不可な状況にあるため、不当廉売・差別対価の取締り強化を願いたい。(関東)
・不当廉売を厳しく取り締まり、厳罰に処するべき。(中部)
・郡部でのSS運営は厳しく、運営を継続するためにも、業転価格、差別対価の対策を早く願う。(中部)
・ノンブランド業者に対し揮発油が安定的・継続的に供給されていますがどうしてでしょうか。(中部)
・異業種からのSS進出での不当廉売で我々の仕入れ値以下で販売しているのに、どうすることもできない。おかしい。(四国)
・製油所の閉鎖に伴う調達コストの高騰は必然であり、業界全体的に価格の底上感はあるが、一部大手元売系店舗の当社仕切価格に近い廉売が悪影響を及ぼしている。(九州沖縄)
1月28日追記
1月25日せんせきより
経営実態調査 販売業者の声 (下)
・今回の震災で設置したばかりの自家発電機が有効活用できました。全額補助のお蔭で設置できとても助かりました。しかし、震災により、SSの防火塀の破損や、事務所にも多少の被害がありますので、なんらかの支援があると助かります。(北海道)
・過疎地域のSSに補助金などの支援。災害時の山間地域へのローリーの手配やスムーズな燃料の供給手配。過疎地域でローリー運転手確保のための施策。免許取得のための費用の補助金。(関東)
・今後人手不足が深刻な状況となりますので、少人数でもSS運営ができるよう消防法の改正など、多方面に働きかけをしてSS支援を行っていただきたい。(中部)
・ガソリンが高騰していく中で、ガソリン税に消費税、とても厳しく商売しています。冬場の灯油代、各消費者の負担で生活も苦しめている状況です。とても先行き不安な状態が続くと思われます。(北海道)
・石油製品に税金を掛け過ぎだと思っております。課税しやすい物からどんどん課税する。(東北)
・一般の公道を走るのはガソリン車もEVも一緒だから、燃料のいらないEVなどにも税金をかけるべきと思います。(関東)
・燃料油の売価が上がると真っ先に高いね、高くなったねと言われる。ガソリン税の高額負担を説明してもなかなか理解してもらえず困っています。税負担の軽減をお願いしたい。(中部)
・揮発油税と消費税の二重課税は納得できない。自働車関係の税金負担が多過ぎる。若者の車離れが加速する。(近畿)
・2019年10月から消費税が10%になるタイミングでタックス・オン・タックスの問題を見直しを進めて欲しい。またEVなどの車両間の税負担について、ガソリン税から道路走行税への見直しを進め、道路を利用する全ての車両が公平に税負担する時期に来ていると思います。将来の車両構成を見据えた税負担の見直しをお願いします。(中国)
・消費税アップに伴う二重課税は解消していただきたい。(九州・沖縄)
◆災害対策
・「ガソリンスタンドは災害時の最後の砦」「自らも被災したスタッフ、必死に給油作業を継続。被災者の命を守る」なんて、災害が起こった直後にはよく報道されたりしますが、平時の扱いはどうでしょう。「ガソリン高、家計を直撃」「遠出を控えるレジャー客」「少量・定額給油で賢く節約」など。ガソリンが高いのは悪、それを売るガソリンスタンドも当然庶民の敵のような報道がなんと多いことか。我々はボランティアでも公共施設の人間でもありません。平時は安売り店に列を成し、たまに来店して文句を言いながら少量給油のお客に対して「緊急時だけ助けろ」というのも感情的に無理があります。『満タン&灯油一缶運動』が功を奏している地域もあるようですが、全国的に見てまだまだ認知度が低いと思われます。高いガソリンが悪、節約の対象ではなく、ガソリンの重要性や地域密着型のガソリンスタンドの重要性をもっと広く強く、一般にアピールしていただきたい。当社のスタッフは皆仕事に誇りを持ち働いていますが、自分の仕事に誇りを持てない方が多数いるのではないか。エネルギー拠点として重要な仕事をしているのだから、仕事に誇りを持てるようなアピール、政策を推進していただきたい。(関東)
・地方自治体の地場業者の利用について、最近、県単位については、入札についても協力してもらえるようになってきたが、市区町村レベルは全く感度がない方が。現在も組合員でない他県の安価な業者を落札対象としている。我々も努力はするが、官公需適格組合を通した納入・災害対応・過疎化対策に一貫性を持たせてほしい。(関東)
・低コスト重視の公共施設の燃料の入札制度を改めて地域業者重視の随意契約で地域業者の経営状態を安定させることが、地方活性化につながると思います。(近畿)
・消防庁に対してSSの規制緩和を進めて欲しい(特に給油許可など)。(四国)
:::::::::::
<これまでの販売業者の「声」>
2015年01月27日 石油協会 経営実態調査 販売業者の声
https://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/fb4b3209231ed1d933e1e0b60b0da6c7
2016年01月27日 経営実態調査・販売業者の声2015 「廃業やむなし」
https://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/a371aabd369a4c25afb4e7e2dcf66fcd
2017年01月21日 販売業者の声
https://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/1f841e6d2c617eee67bab984e1550566
2018年01月27日 販売業者の声2017 「SS存続危機顕著」
https://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/174b4434df4661da93c5a046c8931010
全国の地場店の声を共有するため。
※インターネットを利用されない人も多いのです。