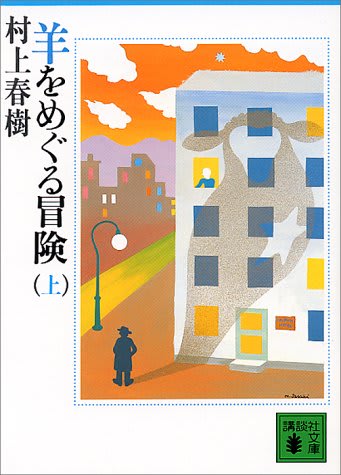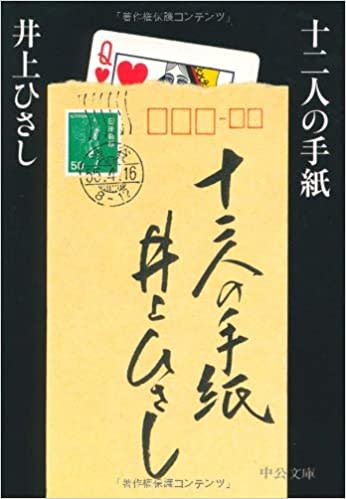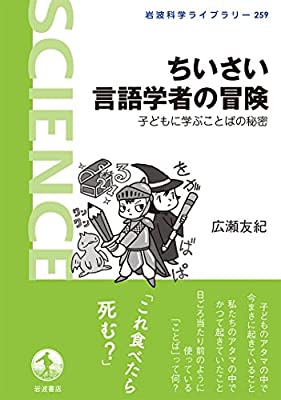原田マハさんの『暗幕のゲルニカ』を読みました。9.11のテロと第二次世界大戦中のピカソをオーバーラップさせ、戦争への抵抗の意志を描く作品です。美術への興味を高めてくれる素敵な本でした。
この本を読みながら、2002年のことを思い出した居ました。私は2002年の2月に一人でニューヨークに生きました。2001年の9月11日に貿易センタービルへのテロがあったので、びくびくしながら行った記憶があります。飛行機も空いていて、定員の5分の1ぐらいしか乗っていませんでした。
その時MoMaは改装中で、クイーンズに仮の美術館を作り展示を行っていました。すでにある施設を使うのではなく、プレハブのような施設でした。本当に「仮の美術館」という雰囲気です。しかしやっているのは「ピカソ・マティス展」です。施設の貧弱さは感じられるのですが、その中には現代アートの名作が並んでいるのです。不思議な感覚でした。
ピカソがどういう人だったのか。人間をはるかに超えたカリスマ性を持ちながら、しかし人間的な姿がこの本の中で描かれています。芸術が社会の中で生まれ、社会の中で輝くのだというのがよくわかります。
ピカソと、ピカソに関わる人々の心が芸術を生み出しているというのが感じられる本でした。楽しめました。