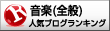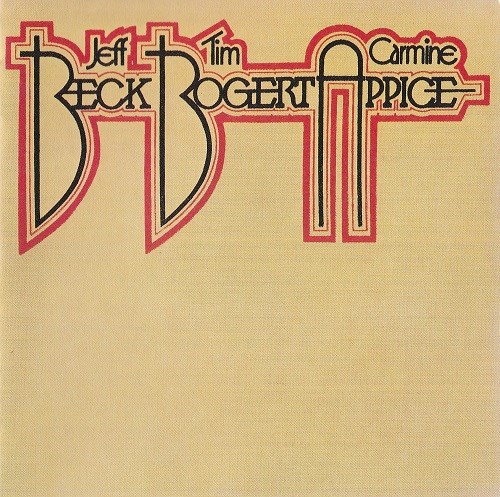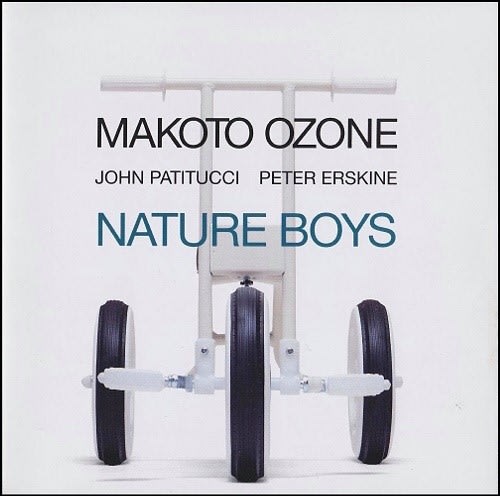先月だったか、ジェイさんのブログで「小島良喜ソロ・アルバム・リリース」のニュースを知りました。発売予定日は10月22日。もちろん速攻でamazonに予約注文、今日か明日かとその日を待っておりました。
小島さんは日本屈指のピアニスト、キーボーディストです。ブルーズやファンクなどの黒人音楽に根ざしたソウルフルなプレイが売り物です。米国滞在時は地元ミュージシャンからも厚い信頼を受けていたと言いますし、帰国後は浜田省吾さんや井上陽水さんらから重用されるプレーヤーとして、今や八面六臂の活躍ぶりです。
ぼくが小島さんを知ったのは、もう何年前になるかなあ、ジャズ・ピアニストの佐山雅弘さんと組んだ「フォア・ハンズ」というユニットを聴きに行ったことに始まります。理知的ながら遊び心に富んだ佐山さんのピアノに一歩もひけを取らず、人間味が感じられるような温かさと激しさが感じられたような小島さんのピアノはかなり印象に残るものでした。
その後、2003年だったでしょうか、あるジャズ雑誌に「コジカナツル」デビューの記事が載っておりました。メンバーにぼくの大好きなベーシスト、金澤英明が名を連ねていたので興味を持って記事を読んでいたら、ピアノがあの小島良喜だという。主にロック、ブルーズのフィールドで活躍していた小島さんは、ピアノ・トリオを組もう、という金澤さんの提案に「ぼくはジャズ・ピアニストじゃないから」と一度は断ったといいます。でも金澤さんは小島さんの幅広いユニークな音楽性に目をつけていたのでしょうね。結局ドラムスの鶴谷さんを加えてバンドはスタートすることになります。
このトリオに興味を持ったぼくは、早速「コジカナツル」のデビュー・アルバムを手に入れました。音楽に魂を奪われたヤンチャなオトナ達が夜更けに集まってワイワイやっている、そんな雰囲気のする作品でしたね。ピアノ・トリオというフォーマットとはいえ、ジャズのそれを踏襲しながらも、自分の感性をまずあふれさせる小島さんのピアノはとてもソウルフルでした。ピアノ・トリオはピアノ・トリオであっても、ジャズの範疇に収まらない、一種型破りな彼らの存在は日本の音楽シーンの中でも稀有な存在だと思います。
その小島さんがソロ・アルバムを出すのです。楽しみでないわけがありません。
脇を固めるのが日本一のグルーヴ・マスターと言われる山木秀夫(Drs)、盟友金澤英明(b)、日本最高のロック・ギタリストChar(g)、ジャズ界の重鎮である峰厚介(ts)、そのほかTOKU(flh)、フライド・プライドの名ヴォーカルであるSHIHO(vo)、沖縄在住のデヴィッド・ラルストン(vo,g)らがゲストとして名を連ねています。
1曲目の「片想い」は浜田省吾の名曲。これを小島さんは小粋で泣けるシックな4ビート・ジャズにアレンジしています。
ハマショーの作品というと、「きみと歩いた道」にも取り組んでいますが、これはSHIHO嬢をヴォーカルに据えてエモーショナルに聴かせてくれます。
「"A"Cat called"C"」は都会の片隅で鳴っているような、少々やさぐれた感じの4ビートです。ヴィブラフォンの音色が似合いそう。ブリッジで入るCharのギターがこれまたジミヘンも真っ青になるくらいの出来栄えです。
「Truth」は「コジカナツル LIVE!!」にも収録されていた小島さん渾身の名バラード。エレピとオルガンの音色がとても温かいのです。
「BASSAB」は盟友金澤さんのベースを大きくフィーチュアーしたアーシーなバラード。小島さんはこのアルバムのうち数曲でシンセサイザー・ベースを使ってますが、それ以外のベース・パートは安心して金澤さんに預け切ってますね。相当信頼関係が厚いのだと思います。
小島さんの多面体な音楽性がよく分かるアルバムだと思います。そうはいってもテクニックを全面に出してピアノを弾きまくるという場面はあまりなく、彼の頭の中に鳴っているサウンドを具現化してみた、というほうが当たっているのではないでしょうか。つまりプレーヤーとしてより、サウンド・クリエーターとしての小島良喜を出しているのでしょうね。
プレイそのものでは、ピアノはよく歌っているし、ダイナミクスを巧く生かして音楽を生きたものにしているし。オルガンを弾いてもツボをほんとによく心得ているというか、ここぞというところの背後でいつも温かく、優しく鳴っているんですね。さすがは小島さん、といったところです。
しかし以前は「ジャズはよく分からない」みたいな発言をしていた小島さんが、比較的4ビートを多く取り入れてアルバムを作っているのも面白いと思います。そのへん、金澤さんの影響が大きかったりしてね。
ぼくとしては、1曲は「コジカナツル3」に入っていた「マイ・バック・ペイジズ」のようなゴスペル・ロックをガンガンに弾いて欲しかったんですが、それはまた別の機会に期待することにしましょう。このアルバムに収められたもの以外に小島さんの引き出しはまだまだ数多くありそうです。
◆Kojima
■演奏・サウンドプロデュース
小島良喜 (piano、keyboards)
■アルバム・リリース
2008年10月22日
■録音エンジニア
青野光政
■録音
青葉台スタジオ、スタジオ・サウンド・ダリ、ワーナー・ミュージック・レコーディング・スタジオ
■収録曲
① KATAOMOI (小島良喜)
② "A" Cat called "C" (小島良喜)
③ Are You Happy (小島良喜)
④ "Co""J" (小島良喜)
⑤ Kimi To Aruita Michi (浜田省吾)
⑥ DRAGON FLY (小島良喜)
⑦ TRUTH (小島良喜)
⑧ BASSAB (小島良喜)
⑨ AWAWA (小島良喜)
⑩ BANG (小島良喜)
⑪ Stay out of my way (小島良喜)
⑫ NAP (小島良喜)
■録音メンバー
小島良喜 (acoustic-piano①②③⑤⑥⑧、electric-piano⑦、organ⑦、keyboards④⑨⑪⑫、synthesizer②⑤⑧⑩⑪、synthesizer-bass②⑪)
金澤英明 (acoustic-bass①②③⑤⑥⑦⑧⑨)
山木秀夫 (drums①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪)
Char (electric-guitar②③⑤)
峰厚介 (tenor-sax②③⑥)
TOKU (flugel-horn②⑥⑨)
Shiho (vocal⑤)
David Ralston (vocal⑪、guitar⑪)
■レーベル
ZAZZY
ぼくは小学校4年の時に転校しました。
それまでのぼくは、とくに音楽好きというわけでもなく、野球やドッジボールが好きな、ごくごく普通の小学生でした。
それでも音楽の授業の時や、給食の時間、下校の時間などにかかっていたクラシックの曲のメロディーのきれいなものには惹かれていたし、テレビの番組やCMなどの中で聴かれる音楽の中にも強く印象に残るものがありました。その頃に好きになった、記憶に残っている曲といえば、シューベルトの「ます」とか、ホルストの「木星」、ビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビー」などがあります。
でも特別音楽が好きだったわけでもないし、自分が今のような音楽を手放せない生活を送るなどとは思ってもみませんでした。
転校したての時は、「転校生」という一種特殊な存在のせいでちょっとばかり周りから浮いた雰囲気を味わったりもしましたが、それでも子供同士のこと、月日がたつにつれ友達もできたし、学校が楽しくもなってゆきました。
授業の合間の休み時間に遊ぶだけでなく、次第に同級生の家へも行くようになったある日、クラスのリーダー的存在だったマキノ君に「今日、うちへ遊びに来いよ」と誘われました。
何人かの友達と一緒に、学校の帰りがけにマキノ君の家に寄りました。
そこで通された彼の部屋にはオーディオ・セットが置いてありました。まだミニ・コンポなんてない時代のことです。プレーヤーからアンプ、チューナー、カセット・デッキなんかもついた大きなコンポーネントでした。
「アニキのレコードだけど」と言ってマキノ君がかけてくれたレコード、それは初めて聴く「洋楽」というものでした。それまでは、音楽といえば、学校で聴くクラシックと家のテレビで聴く歌謡曲ぐらいしか知らなかったぼくにとっては初体験の「洋楽」だったんです。
その日何をして遊んだかとか、何を話したとか、他に誰がいたかなんてことは一切覚えていません。強烈に記憶に残っているのは、窓から射し込む夕日が部屋じゅうをオレンジ色に染めていたこと、そしてそのオレンジ色の中で聴いた、ピアノが印象的な曲のことだけです。ジャケットの青色が印象的なレコードでした。そう、その曲がビートルズの「レット・イット・ビー」で、レコードがいわゆるビートルズの「青盤」だったんですね。
子供心にも郷愁を誘うような見事な夕日の中で聴いた「レット・イット・ビー」の感動、今でも忘れません。そして、この時に漠然と思ったのが、「ああ、ピアノが弾けたらなぁ。。。そしたらこの曲を弾いてみたい。いつか弾いてみたいなぁ」ということでした。
初めて触れた「洋楽」がロックで、しかもビートルズだったというのは、今思えば、ぼくにとってみれば人生の方向が変わってしまったくらいの衝撃だったんだな、と思いますね。
その後すぐにビートルズ熱に火が点いたか、というと、そうでもなかったんですね。なにせその頃のぼくの家にあったのは、子供用のおもちゃみたいなポータブルのモノラル・レコード・プレーヤーだけでしたから、とても音楽を聴くような環境ではなかったんです。ちなみに、当時わが家にあったレコードといえば、何枚かの童謡のほかには歌謡曲と軍歌が少しあるだけでした。覚えているのは梓みちよの「こんにちは赤ちゃん」、皆川おさむの「黒ネコのタンゴ」なんかがあったことですね。
たしか小学校5年生になってからだと思いますが、ラジカセ(ラジオ付きカセット・テープ・レコーダー)を買ってもらいました。家でも洋楽をよく聴くようになったのはそれからです。その洋楽熱は中学に入ってから本格的に燃え上がり、ビートルズを出発点としてクィーン、ウィングス、キッス、エアロスミス、イーグルス、シカゴなどなどを聴くようになっていったというわけです。
今日は「ぼくとビートルズの出会い」というささやかなお話でした~(^^)
音楽との邂逅譚を心にしまっておられる方、きっと多いことでしょうね。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
「フュージョン」というジャンルが現れたのは1970年代の後半だと記憶しています。
その当時は「クロスオーヴァー」という言葉が使われていました。おもにジャズとロックが、文字通り交差(クロスオーヴァー)したり、融合(フュージョン)してできたものです。
この動きの先駆けとなったミュージシャンにはマイルス・デイヴィスをはじめ、カルロス・サンタナやジョン・マクラフリン、ハービー・ハンコックらがいましたが、ジェフ・ベックのこの「ブロウ・バイ・ブロウ」こそジャズとロックの垣根を越えた、まさにボーダーレスなアルバムのうちの1枚ではないか、と思っています。

天気の良い日曜の午後や、寝る前のひとときなど、部屋でくつろいでいる時のBGMにピッタリだなぁ、などと思ったりしていますが、じっくり聴いても非常に聴きごたえを感じさせられる1枚です。
クールで研ぎ澄まされたジェフのギターですが、だからといってテクニック至上の無味乾燥な音楽ではありません。感情豊かに、自由自在にギターを語らせているのが心地よい。
そう、ジェフはギターを「弾く」のではなく、「語らせ(歌わせ)る」ミュージシャンなのです。
ジェフの音楽の出発点はブルーズで、その後はブラック・ミュージックへの接近を図っているようですが、このアルバムのヴォイシングを聴くと、だいぶジャズに近づいているようです。しかし、単にジャズとの融合を図ろうとしたというよりは、この時点でジェフが表現したかったことが結果的にクロスオーヴァー・サウンドとなって表れた、ということではないでしょうか。
納得のゆく自分のバンドを作ることにたいへん苦労していたジェフですが、ここらあたりからバンド・サウンドよりも、自分のギターで作り上げるサウンドの追求に専念しているようにも思えます。

バックの面々のサポートも実に素晴らしいですね。
マックス・ミドルトンは、ジェフ・ベック・グループでも起用された、気心の知れたキーボード・プレイヤー。
ベースのフィリップ・チェンは、このアルバムでの好演が買われ、のちロッド・スチュワートのバンドに加入しました。
ドラムスのリチャード・ベイリーは、この時点でなんと弱冠18歳! うーん、見事。
このアルバムには、ジェフの看板曲のひとつでもある「スキャッターブレイン」をはじめ、計9曲が収められています。
その中には、レノン=マッカートニーが作ったR&R「シーズ・ア・ウーマン」や、BB&A時代にトラブルがあったと言われているスティーヴィー・ワンダーの曲が2曲入っています。
スティーヴィーの曲は「哀しみの恋人達」と「セロニアス」。とくに「哀しみの恋人達」は今でもライブでよく演奏しているほか、多くのギタリストに取り上げられています。
ひとつの新しい流れを作ったという意味でもたいへん重要なアルバムです。
しかし、単なる音楽ファンとして心地よいギター・サウンドに浸りたい時にも、ちゃんとその欲求に応えてくれる素敵なアルバムだと思います。
◆ブロウ・バイ・ブロウ/Blow by Blow
■演奏
ジェフ・ベック/Jeff Beck
■リリース
1975年3月29日
■プロデュース
ジョージ・マーティン/George Martin
■収録曲
[side-A]
① 分かってくれるかい/You Know What I Mean (Jeff Beck, Max Middleton)
② シーズ・ア・ウーマン/She's a Woman (John Lennon, Paul McCartney)
③ コンスティペイテッド・ダック/Constipated Duck (Jeff Beck)
④ エアー・ブロワー/Air Blower (Richard Bailey, Jeff Beck, Phil Chen, Max Middleton)
⑤ スキャッターブレイン/Scatterbrain (Jeff Beck, Max Middleton)
[side-B]
⑥ 哀しみの恋人達/Cause We've Ended as Lovers (Stevie Wonder)
⑦ セロニアス/Thelonius (Stevie Wonder)
⑧ フリーウェイ・ジャム/Freeway Jam (Max Middleton)
⑨ ダイヤモンド・ダスト/Diamond Dust (Bernie Holland)
■録音メンバー
ジェフ・ベック/Jeff Beck (guitar)
マックス・ミドルトン/Max Middleton (keyboards)
フィル・チェン/Phil Chen (bass)
リチャード・ベイリー/Richard Bailey (drums, percussions)
スティーヴィー・ワンダー/Stevie Wonder (clavinet ⑦ guest : uncredited)
■チャート最高位
1975年週間アルバムチャート アメリカ(ビルボード)4位、日本(オリコン)27位
1975年年間アルバムチャート アメリカ(ビルボード)76位
山中千尋の通算7作目となる最新アルバム『アフター・アワーズ』は、2007年12月23日に惜しまれながら82歳で逝去した世界的ジャズ・ピアニスト、オスカー・ピーターソンへのトリビュート作品です。
ちなみに「アフター・アワーズ」とは、「ライヴが終わった後の時間」という意味で、その時にはお客で来ていたミュージシャンなども交えて、ジャム・セッションが繰り広げられるのが常となっています。
山中さんは、当初は別の企画で新作を録音する予定だったそうですが、そのレコーディングの矢先にオスカーの訃報が飛び込んできました。このニュースを聞いた山中さんが急遽予定を変更して録音に臨んだのが、アルバム『アフター・アワーズ』というわけです。このアルバムは、今日に至るまで大きな影響を受けてきたオスカー・ピーターソンへの想いが詰め込まれたトリビュート・アルバムだと言えるでしょう。

オスカー・ピーターソン(pf)
収められているのは「オール・オブ・ミー」、「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」、「コンファーメイション」、「帰ってくれればうれしいわ」、「虹の彼方に」、「エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー」等、われわれが行うジャム・セッションでも御馴染みの曲ばかりです。
しかしこれが、さっぱりしていてなかなか良いんです。もちろん、いつもの山中さんの個性あふれる演奏も良いですが、スタンダード集とはいってもこれはこれで「千尋カラー」を楽しめるアルバムだと思います。
今作は、ピアノ+ギター+ベースというドラムレス・トリオですが、これは1950年代のオスカー・ピーターソン・トリオを思い起こさせるオールド・ファッションなスタイルです。『アフター・アワーズ』は、生前のオスカーが心をこめて取り上げていたスタンダード・ナンバーを、このドラムレス・トリオでトリビュートしたものです。
トリビュート・アルバムとは言っても、偉大な先人の演奏をそのままコピーするのとは違い、オスカーをリスペクトしながら、山中さんも自分の個性を出そうとしているのではないでしょうか。
そして、オマージュ的性格を持つせいでしょうか、このCDは、選曲が今までの山中さんからするとある意味意表を突くような、スタンダードの名曲を揃えているのが特徴です。
バランス的には、ギターが全面に出ている時などピアノが引っ込んでいるし、流麗なピアノ・ソロの時は4ビートを刻むギターがほどよく流れていて、なかなか良いんじゃないかな、と思います。スウィング期によく聴かれたような鋭く刻むギターに乗っかって演奏されるリリカルな山中さんのピアノ、素敵です。その中心で野太く弾いているのがベースの脇義典氏。脇さんは、バークリー音楽大卒業後ずっとニューヨークで活躍されているベーシストです。ほんとうによく歌うベースを弾くので気に入ってしまいました。
左から 脇義典、山中千尋、アヴィ・ロスバード
今までの山中さんのアルバムと比べると、オールド・スタイルでやや地味であることは否めないでしょうけれど、お酒でも飲みながら気楽に楽しんだり、ジョギングのお供に聴いたりするのに適した、リラックスしたアルバムだと思います。
また、このアルバムから感じられるレトロな雰囲気も温かくていいなぁ。全員の体に共有して流れるビートから躍動感が感じられて楽しいです。
急なレコーディングだったけれど、急遽集まってサクサク録音をこなしてみた、という雰囲気のするノリも、昔のバップ華やかなりし頃の空気を醸し出ているような気がします。1曲1曲の時間が短いことも、40~50年代の録音物を意識してのことかもしれません。
山中千尋さんは2001年のデビュー以来、澤野工房から3枚のアルバムを発表しました。2005年には澤野工房からヴァーヴへ移籍し、それ以降も『アフター・アワーズ』を含め4枚のアルバムをリリースしています。2007年春にはヨーロッパでアルバム・デビューを果たし、同年11月に行われた初のワールド・ツアーも大成功を収めました。現在の彼女はニューヨークを拠点に、内外で精力的な演奏活動を展開、今や名実共に日本を代表するジャズ・ピアニストのひとりに挙げられています。昨今目立つ日本人プレーヤーの活躍ですが、これからも山中千尋さんや、他の日本人ミュージシャンに期待しています。
◆アフター・アワーズ/After Hours
■ピアノ
山中千尋
■リリース
2008年2月27日
■プロデュース
山中千尋
■録音
2007年12月30日、2008年1月3日 イーストサイド・サウンド(ニューヨーク市)
■収録曲
① オール・オブ・ミー/All Of Me (Seymour Simons, Gerald Marks)
② ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー/There Will Never Be Another You (Harry Warren, Mack Gordon)
③ コンファメーション/Confirmation (Charie Parker)
④ ユード・ビー・ソー・ナイス・トウ・カム・ホーム・トゥ/You'd Be So Nice To Come Home To (Cole Porter)
⑤ スー・シティ・スー・ニュー/Sioux City Sue New (Keith Jarrett)
⑥ オール・ザ・シングス・ユー・アー/All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar HammersteinⅡ」)
⑦ 虹の彼方に/Ove The Rainbow (Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg)
⑧ エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー/Everything Happens To Me (Matt Dennis, Tom Adair)
※All songs arranged by Chihiro Yamanaka
■録音メンバー
山中千尋 (piano)
脇義典 (bass)
アヴィ・ロスバード/Avi Rothbard (guitar)
■レーベル
VERVE
ジェフ・ベックも気がつけばもう60歳を超えてるんですね。でも写真を見ると、とてもそんな歳だとは思えない若々しさです。相変わらずのジェフの姿を見ると、やはりうれしいものがあります。
ぼくはとくにジェフ・ベックのファンというわけではありませんが、それでも彼のアルバムの中には好きでよく聴いていたものが何枚もあります。その中の一枚が、「ベック、ボガート&アピス」です。
ティム・ボガート(Bass)とカーマイン・アピス(Drums)のコンビは、ヴァニラ・ファッジやカクタスを通じ、ロック界有数の強力なリズム・セクションとして活躍していました。ジェフは早くからこのふたりとのジョイントを考えていたようですね。

ベック、ボガート&アピス
ロックでのトリオ編成といえばギター、ベース、ドラムスというのが一般的です。1970年代までの主なロックのギター・トリオといえばクリーム、グランド・ファンク・レイルロード、ジミ・ヘンドリックス・エキスペリエンシスなどがあげられます。これらに共通しているのは、個々のソロ・プレイのスペースを大きく取っているところでしょう。
このアルバムに収められている曲は、歌モノとして楽しむこともできますが、やはりライヴにおいて充分にアドリブを行うことを目的としているものが多いみたいですね。


BB&Aというグループは、ベースとドラムスがアメリカ出身だから、というわけでもないのでしょうが、どちらかといえばサウンドにアメリカン・ロックっぽさが感じられます。スリー・ドッグ・ナイトのメンバーがゲストで参加していたり、スティーヴィー・ワンダーやカーティス・メイフィールドの曲を取り上げていたりするので、よりアメリカナイズされているような気がするのでしょうね。
このアルバムは、一部ではあまり評価が高くないらしいのですが、ぼくには、ブルース一辺倒だった頃と比べてサウンドが広がっているように感じるのです。

このアルバムで驚いたのは、やはりティム・ボガートのプレイです。ティムはすぐに、ジャック・ブルースと並ぶぼくのアイドルになりました。
初めてこのレコードを聴いた頃のロック・ベースは、そのほとんどが非常にベーシックなパターンだったので、ティムのプレイには驚きとともに憧れを抱いたものです。「黒猫の叫び」「迷信」などでのリフを生かしたメロディックなプレイや、卓越したテクニックをフルに発揮した「レディー」でのスピーディーなプレイは幾度となく繰り返して聴きました。
ただし、一緒にプレイしてみると、ジェフには、ティムの奔放なベース・ラインが「やりすぎ」にしか思えなくなっていったようですね。そのへんが、このトリオが早々に分解してしまった理由のひとつだったみたいです。
ぼくらの間でさえ、演奏上の「相性」ってなかなか難しいですからね。
◆ベック、ボガート&アピス/Beck Bogert & Appice
■歌・演奏
ベック、ボガート & アピス/Beck Bogert & Appice
■リリース
1973年2月
■プロデュース
ドン・ニックス/Don Nix ①⑧、ベック、ボガート & アピス/Beck Bogert & Appice ②~⑦⑨
■収録曲
[side-A]
1.黒猫の叫び/Black Cat Moan (Nix)
2.レディー/Lady (Appice, Beck, Bogert, Bogert, French, Hitchings)
3.オー・トゥ・ラヴ・ユー/Oh To Love You (Appice, Beck, Bogert, Bogert)
4.迷信/Superstition (Wonder)
[side-B]
5.スウィート・スウィート・サレンダー/Sweet Sweet Surrender (Nix)
6.ホワイ・シュッド・アイ・ケアー/Why Should I Care (Kennedy)
7.君に首ったけ/Lose Myself With You (Appice, Beck, Bogert, Bogert, French)
8.リヴィン・アローン/Livin' Alone (Appice, Beck, Bogert, Bogert)
9.アイム・ソー・プラウド/I'm So Proud (Curtis Mayfield)
■録音メンバー
☆ベック・ボガート&アピス
ジェフ・ベック/Jeff Beck (guitar, vocals, lead-vocals①)
ティム・ボガート/Tim Bogert (bass, vocals, lead-vocals④⑥⑦)
カーマイン・アピス/Carmine Appice (drums, vocals, lead-vocals②③⑤⑧⑨)
★ゲスト
デュアン・ヒッチングス/Duane Hitchings (piano, mellotron③)
ジム・グリーンスプーン/Jim Greenspoon (piano⑤)
ダニー・ハットン/Danny Hutton (backing-vocal⑤)
■チャート最高位
1973年週間チャート アメリカ(ビルボード)12位、イギリス28位、日本(オリコン)22位
ラジオや有線放送などで流れていた曲が耳に入った瞬間、思わず夢中で聴き入ってしまうことがあります。そういう時は、すぐにでもCDショップに向かってまっしぐらに進みたくなったりします。
「ブリリアント・グリーン」のファースト・アルバムも、たまたまラジオで聴いて、衝動的に買いに走りました。

その時ラジオでオンエアされていたのは、「冷たい花」でした。
これは、当時TBS系で放映されていた音楽番組「カウントダウンTV」のオープニング・テーマだったんですが、テレビというものをあまり見ないぼくにとっては、全く未知の曲だったわけです。
独特のギターサウンドと、それに乗せてせつなげに歌われる歌、非常にインパクトがありました。
アルバムは、どちらかというとブリティッシュ・ロック風のギター・サウンドが柱となっているようで、重いリズム、ヘヴィで暗いギターが「ブリリアント・グリーン・サウンド」をくっきりと形作っています。しかしメロディーはとてもポップです。この二面性が「ブリリアント・グリーン」の魅力だという気がします。このあたり、あの「オアシス」に通ずるところもあるようですね。
さらに気だるくさらりとした川瀬智子のボーカル、これがほの暗いサウンドに妙にマッチしています。バックで使われているオルガンの音色も効果的。

アルバム1曲目の攻撃的なハード・ロック「I'm In Heaven」、2曲目のダークな「冷たい花」、9曲目のポップな「There will be love there -愛のある場所-」(TBS系ドラマ『ラブ・アゲイン』テーマ曲)などが聴き物ですが、彼らの個性的なサウンドはアルバム全般に染み渡っています。
その他「You & I」も好きだし、「Stand By」なんかは「ラバーソウル」~「リボルバー」あたりのビートルズを彷彿とさせていて、聴いていると心地良いです。

ここのところそれぞれソロ活動を活発に行っていたみたいですが、今年2月にはシングル「Ash Like Snow」を発表しています。またどんどん極上のロック・サウンドを聴かせて欲しいものです。
最近、ベスト・アルバムも出たみたいですね。欲しいです~
◆the brilliant green
■歌・演奏
the brilliant green
■リリース
1998年9月19日
■プロデュース
the brilliant green & 笹路正徳
■収録曲
① I'm In Heaven (詞:川瀬智子、曲:松井亮)
② 冷たい花 (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作) ☆オリコン1位
③ You & I (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作)
④ Always And Always (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作)
⑤ Stand by (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作)
⑥ MAGIC PLACE (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作)
⑦ "I" (詞:川瀬智子、曲:松井亮)
⑧ Baby London Star (詞:川瀬智子、曲:松井亮)
⑨ There will be love there -愛のある場所- (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作) ☆オリコン1位
⑩ Rock'n Roll (詞:川瀬智子、曲:奥田俊作)
☆=シングル・カット
■録音メンバー
[the brilliant green]
川瀬智子(vocal, chorus)
松井亮(guitars)
奥田俊作(bass, chorus)
[additional musicians]
笹路正徳(keyboards)
伊藤隆博(keyboards)
渡嘉敷祐一(drums)
佐野康夫(drums)
田中一光(drums)
川瀬正人(percussion)
三沢またろう(percussion)
横山剛(manipulation)
篠崎正嗣ストリングス(strings)
■チャート最高位
1998年週間アルバム・チャート オリコン2位
1998年年間アルバム・チャート オリコン16位
先日、CDショップで偶然に「ジョージ川口に捧ぐ」と題されたアルバムを見つけました。
ぼくは、まだ川口氏のCDを持っていなかったし、日本の誇る偉大なドラマーの音をぜひとも聴いておきたいと思ったので、即手に入れました。
このアルバムには、1953年から62年にかけての、ジョージ川口氏のベスト・テイクが並んでいます。
ジョージ川口氏は2003年11月に76歳で亡くなっています。1927年に京都市で生まれ、5歳の時から20歳頃まで旧満洲(中国東北部)で過ごしました。満洲飛行学校の教官として終戦を迎えた川口氏は、1947年春に日本に引き揚げます。その後、「ジョージ川口とビッグ・フォー」を結成して日本に空前のジャズ・ブームを巻き起こし、日本ジャズ界の黄金時代を築き上げました。

実に派手で、豪快なドラミングです。聴いているだけで楽しくなってくるような、華やかさがありますね。このアルバムでは川口氏の技と力を尽くした、パワフルなドラム・ソロがたっぷり堪能できます。
しかし、伴奏に回った時のドラミング、これがまた的確です。曲に色合いや広がりを出し、力強いグルーヴ感を生み出して、フロントをしっかりとサポートしています。
豪快といえば、氏のホラ話は有名ですね。まさにドラミングそのままの、豪快というか、壮大というか、スケールの大きなホラ話、好きだった人も多いんじゃないかな~

「ビッグ・バンドの一員として慰問に行った先が、ベトナムの最前線。演奏中に北ベトナム軍の攻撃が始まった。
急にクラリネットの音がしなくなったと思ったら、撃たれている。今度はアルト・サックスの音がしなくなったと思ったら、これまた撃たれている。
メンバーが次々に倒れてゆく中、シンバルに当たる弾の『カンカンカン』という音を聴きながら、私は必死にドラムを叩いていたんだよ、ワッハッハ」
「米軍のベース・キャンプに仕事に行った時にバクチに加わり、勝ちまくって潜水艦を一隻ぶん取ってきたが、置いておく場所がないから横須賀に係留してあるよ」(横須賀の米軍キャンプで演奏し、ギャラとして駆逐艦を貰ったが置き場所がないので横須賀に置いたままにしてある、またはB-29をもらったが置き場所がないから飛行場に放置してある、というバージョンもある)
その他にも「終戦直後の満州でソ連兵相手のバンドでドラムを叩いたところ、あまりに気に入られてソビエト本国に連れて行かれそうになったため、一升瓶の醤油を飲み仮病を装って諦めさせた」とか、「戦時中フィリピンから米軍の空母を操舵して逃げ帰って来た」、「同じく戦時中南方の収容所を脱走して、ついでに虎退治をしてきた」などという見てきたようなホラ話もあるらしいです。まるで落語を聞いてるみたいですね。
これらの豪快な話、当時のバンドマンならではの雰囲気に満ちた、とても面白いものだったそうですよ。
しかしこういうキャラクターのミュージシャンも少なくなってきたような気がします。
ぼくにはあんまり面白いホラ話が思いつかないんですよね~
「ウソ」は人を傷つけるけれど、「ホラ」はみんなで笑えるもんね。せいぜいネタ集めを頑張ってみようかな~。

◆ビッグ・バン・ブロウ フィーチャリング・ビッグ・フォア ジョージ川口に捧ぐ
■演奏
ジョージ川口
■アルバム・リリース
2003年12月25日
■コンピレーション・プロデューサー
森谷秀樹 ほか
■収録曲
① オール・マン・リヴァー/Ol'man River (Jerome Kern)
② ホワイト・ジャケット/White Jacket (ジョージ川口, 松本英彦)
③ ビッグ・フォア・プラス・ワン・テーマ:ラヴァー/Big Four Plus One Theme:Lover (Richard Rodgers)
④ ビッグ・フォア・モッブ/Big Four Mob (松本英彦)
⑤ セヴン・カム・イレヴン/Seven Come Eleven (J. Charles, B. Christisn, Benny Goodman)
⑥ バラード・メドレー/Ballad Medley (Hoagy Carmichael~Richard Rodgers~Vernon Duke)
⑦ ドラム・ブギー/Drum Boogie (Gene Krupa, Roy Eldridge)
⑧ ジャングル・ドラムス/Jungle Drums (Ernesto Lecuona)
⑨ チェロキー/Cherokee (Ray Noble)
⑩ 今宵の君/The Way You Look Tonight (Jerome Kern)
⑪ 四月の思い出/I'll Remember April
⑫ スイート・ジョージア・ブラウン/Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey)
⑬ 死刑台のエレベーター/Ascenseur Pour L'echfaud (Miles Davis)
⑭ ウォーキン/Walkin' (Richard Henry Carpenter)
■録音メンバー
ジョージ川口とビッグ・フォア(ジョージ川口drums, 松本英彦t.sax, 中村八大pf, 小野満b)①②
ジョージ川口とビッグ・フォア・プラス・ワン(ジョージ川口drums, 松本英彦t.sax, 渡辺貞夫a.sax, 八木正生pf, 木村新弥b)③④⑤⑥⑦
ジョージ川口とビッグ・フォア・プラス・ワン(ジョージ川口drums, 林鉄雄tp, 村岡健t.sax, 鈴木宏昌pf, 鈴木順b)⑬⑭
松本英彦とジャズ・コンボ(ジョージ川口drums, 松本英彦t.sax)⑧
(ジョージ川口drums, 松本英彦t.sax, Fl, 中村八大pf, 上田剛b)⑨⑩
(ジョージ川口drums, 松本英彦t.sax, 渡辺貞夫fl,a.sax 中村八大pf, 上田剛b)⑪⑫
■スターダスト[STARDUST]
■2003年
☆岸ミツアキ(pf)
☆ピーター・ワシントン(b)
☆グラディ・テイト(dr)
■試聴はこちら
日本ではスタンダード・ジャズなどと呼ばれている、
「アメリカン・クラシック・ポピュラー・ソングス」に、
愛情を注ぎ、積極的に演奏し続けているのが、
ジャズ・ピアニスト 岸ミツアキさんです。
故・藤岡琢也さんが岸さんの大ファンだったことは有名ですね。
ジャズでは楽曲を
即興演奏(アドリブ)の素材として
使う場合もとても多いですが、
岸ミツアキは、素材をあくまで歌曲として捉え、
原曲の良さを生かしながら、
ピアノで大事に歌いあげようとしています。
「STARDUST」は、
レッド・ガーランド(pf)生誕80周年にちなむ
トリビュートという一面もあるアルバムです。
「スターダスト」や「フォギー・デイ」などの
名曲もたくさん取り上げられています。
軽快なスウィング感がとても心地よいピアノですね。
タッチはあくまで優しい。
バラードでは意識的に派手さを抑えた感じがしますが、
それが却ってゆとりと渋さを生んでいる気がします。

小粋なリハーモナイズや遊び心のあるアレンジは、
おなじみの名曲に今までと違った光沢を与えています。


彼のステージは楽しいです。
見事な演奏はもちろん、
関西出身だけに、軽妙なトークも見どころ(聴きどころ?)。
ちなみに彼の奥方である古閑みゆきさんも、
とってもステキなジャズ・シンガーなんですよ

このアルバム、夜中に聴くなら
ワインかカクテルが似合いそうです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ついこの間CDショップを覗いたら、ジャズ・コーナーの売り上げベスト10の棚にハービー・ハンコックのグラミー受賞作「リヴァー」があったんです。買おうかどうしようか考えながら他の商品を見ていると、目に飛び込んできたのが、同じくハービーの「スピーク・ライク・ア・チャイルド」のジャケットです。
ハービー・ハンコックは好きなミュージシャンでもあるし、どちらにしようか迷ったんですが、アコースティックなハービーが聴きたかったので、「スピーク~」をレジへ持って行きました。
薄暮の中でキスをする恋人同士の写真が使われているジャケットがステキです。このふたりは、ハービーと恋人時代の現夫人なんだそうですね。
このアルバム、少年時代との決別をコンセプトにしたアルバムらしいです。

ピアノ・トリオ+ホーン・セクション3人のセクステット編成になっていますが、管楽器は時折りテーマを演るほかはバッキングに徹しています。管楽器は、基本的にはピアノ・トリオの音飾として使用されている感じで、その音色もとてもまろやか。フリューゲル・ホルン、バス・トロンボーン、アルト・フルートという組み合わせは、ホーン特有の金属的な響きが抑えられていて、とても耳馴染みが良いと思います。こういう編成からもハービーのセンスの良さが窺えますよね。
管楽器群はソロこそ取りませんが、サウンドの組み合わせや凝った音使いのアレンジが相まって一種浮遊感の漂う不思議なムードを醸し出しています。これがハービーのピアノに彩りを添えているように思うんです。
アルバムから漂ってくる落ち着いた雰囲気が心地よいですね。
美しく柔らかいホーン・アンサンブル、スウィンギーなベースとドラムス、リリカルなハービーのピアノ。
タイトル・チューンのほか、「ライオット」や「ソーサラー」などの名曲が収録されていて、ハービーの作曲者としての資質の高さも垣間見えます。
ハービーのピアノはとてもリリカルでありながら思索的。決して甘さに流されておらず、爽やかでクール。ベタつかず、知性とちょっとしたシャレっ気みたいなものを感じるのです。
「ライオット」は現在に至るまでのハービーの重要なレパートリーです。マイルス・クィンテットの1967年作のアルバム「ネフェルティティ」に収められているのが初演です。サスペンス・タッチの簡明なテーマに続き、ピアノが颯爽と弾き始めます。とても躍動感のあるナンバー。
タイトル・チューンの「スピーク・ライク・ア・チャイルド」は、バラード系のボサノヴァ。黄昏時から夜の濃紺に移ってゆくジャケット写真の魅力そのものが現れている緩やかな曲です。
「ソーサラー」はマイルス・デイヴィスの同名アルバム(1967年)が初演。ここではピアノ・トリオで演奏されています。「ソーサラー」(邦題:魔術師)とはハービーがマイルスに親しみを込めてつけたあだ名です。このアルバムでは、ハービーの饒舌で緊張感のあるプレイが爽やかに響き渡っています。

「ファースト・トリップ」はロン・カーター作。ピアノ・トリオでスウィンギーに演奏されています。ロンの息子が初めて学校に通うことになった日の様子を表現したものだそうです。
「トイズ」「グッドバイ・トゥ・チャイルドフッド」は、ともに巧みに計算されたブラス・アンサンブルの中から現れるハービーのピアノがとてもしっとり浮き上がってくる感じ。
ピアニストとしてだけでなく、コンポーザー、アレンジャーとしてのハービーの存在価値を際立たせた作品だと言えるのではないでしょうか。新しい音を生み出そうとする気概のようなものも伝わってくる気がする新鮮なアルバムだと思います。 エレクトリックなハービーもカッコ良いのですが、こういったアコースティックなハービーの音楽もぼくは好きですね~。
◆スピーク・ライク・ア・チャイルド/Speak Like a Child
■演奏
ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (piano)
-----------------------------------------------
ロン・カーター/Ron Carter (bass)
ミッキー・ローカー/Mickey Roker (drums)
ジェリー・ドジオン/Jerry Dodgion (alto-flute)
サド・ジョーンズ/Thad Jones (flugelhorn)
ピーター・フィリップス/Peter Phillips (bass-trombone)
■リリース
1968年
■録音
1968年3月6日・・・①②③、9日・・・④⑤⑥
■プロデュース
デューク・ピアソン/Duke Pearson
■レーベル
ブルー・ノート/Blue Note
■収録曲
A① ライオット/Riot (Hancock)
② スピーク・ライク・ア・チャイルド/Speak Like a Child (Hancock)
③ ファースト・トリップ/First Trip (Ron Carter)
B④ トイズ/Toys (Hancock)
⑤ グッドバイ・トゥ・チャイルドフッド/Goodbye to Childhood (Hancock)
⑥ ザ・ソーサラー/The Sorcerer (Hancock)
■チャート最高位
1968年週間チャート アメリカ(ビルボード)・トラデショナル・ジャズ・チャート14位、日本(オリコン)279位
シカゴは、ぼくが最も好きなロック・グループのひとつです。高校時代には、とにかく聴きあさりました。
学校の近くに、Nさん兄弟が経営している中古レコード店がありました。弟のヒロシさんはアマチュアの域を超えたギタリストでした。(現在でも地元在住のプロ・ギタリストとして活躍しています)
学校の帰りによくそこへ寄っては、ヒロシさんの学生時代の話や、音楽の話を聞いたものです。大学時代に某有名ジャズ・プレイヤーのバンドに誘われたこと、思い立って渡米し、ジョージ・ベンソンにギターを習いに行ったことなどなど…。
そのお店では、さまざまなグループのレコードを聴かせて貰いました。そこで薦められたレコードのひとつが、この「シカゴⅪ」です。文字通り、シカゴの11枚目のアルバムです。

この頃のシカゴは、ひと昔前のブラス・ロックから脱皮していて、洗練された都会的なポップ色が濃くなりつつあったので、ひところのハードな音が好きだったぼくにはやや物足りない気がしていました。しかし、聴いてゆくほどにこのアルバムのバラエティに富んだ作風が好きになっていったのです。
2曲目の「朝もやのふたり」は、全米チャート4位に入るヒット・ナンバーですが、ぼくは、9~11曲目にかけてのメドレー(「ある男の苦悩~前奏曲~愛しい我が子へ」)の美しさの方がたまらなく好きなのです。

その頃はよく夜更かしをして、ラジオの深夜放送を聴いたり、好きなレコードを聴きながら本を読んだり、物思いにふけったりして、寝そびれたまま明け方を迎えることがままありました。
真っ暗だった外が、夜が明けかかって青みがかかったように見える時、このレコードを聴いていると、ひとりぼっちでいることの寂しさがひときわ感じられました。そして曲が「ある男の苦悩」に移ると、ぼくの部屋にだけ一足早く朝日が昇ってゆくような錯覚に陥ったものです。
精神的に不安定だったギタリストのテリー・キャスは、このアルバムの収録を最後に、ピストル事故(ロシアン・ルーレットをしていたという)で不慮の死を遂げています。そんな悲しいニュースも伝わって来て、よけいにしみじみ聴きこんだという記憶があります。

テリー・キャス
今でも夜中に一息入れたい時など、時々トレイに乗せる一枚です。

◆シカゴⅪ/Chicago Ⅺ
■リリース
1977年9月12日
■プロデュース
ジェイムス・ウィリアム・ガルシオ/James William Guercio
■録音メンバー
【Chicago】
ロバート・ラムRobert Lamm/(Keyboards,vocals,percussion)
テリー・キャス/Terry Kath(guitars,vocals,percussion)
ピーター・セテラ/Peter Cetera(bass,vocals)
ダニエル・セラフィン/Daniel Seraphine(drums,percussion)
ロウディー・デ・オリヴェイラ/Laudir De Oliveira(percussion)
ジェイムス・パンコウ/James Pankow(trombone,keyboards,percussion,vocals)
リー・ローグネイン/Lee Loughnane(trumpet,vocals)
ウォルター・パラザイダー/Walter Parazaider(sax,flute,clarinet)
------------------------------------------------------
【Guest】
デヴィッド・"ホーク"・ウォリンスキー/David "Hawk" Wolinski(keyboard⑤⑪)
ジェイムス・ウィリアム・ガルシオ/James William Guercio(guitar②)
ティム・セテラ/Tim Cetera(backing-vocal②)
カール・ウィルソン/Carl Wilson(backing-vocal②)
チャカ・カーン/Chaka Khan(backing-vocal⑤)
ドミニク・フロンティア/Dominic Frontiere(orchestration②⑨)
■収録曲
A① ミシシッピー/Mississippi Delta City Blues (Kath)
②朝もやの二人/Baby, What a Big Surprise (Cetera) ☆全米4位、全英41位
③永遠の愛/Till the End of Time (Pancow)
④孤独なポリスマン/Policeman (Lamm)
⑤シカゴへ帰りたい/Take Me Back to Chicago (Seraphine, David Hawk Wolinski) ☆全米63位
B⑥僕の公約/Vote for Me (Lamm)
⑦無情の街/Takin' It on Uptown (Kath)
⑧今度こそは/This Time (Loughnane)
⑨ある男の苦悩/The Inner Struggles of a Man (Dominic Frontiere, Instrumental)
⑩前奏曲(愛しい我が子へ)/Prelude(Little One) (Seraphine, David Hawk Wolinski)
⑪愛しい我が子へ/Little One (Seraphine, David Hawk Wolinski) ☆全米44位
☆=シングル・カット
■チャート最高位
1977年週間チャート アメリカ(ビルボード)6位
21世紀に入ってからも、なおいっそう精力的に活動しているポール・マッカートニー。
60歳を過ぎているというのに、若々しい雰囲気は以前のまんまです。
このまま、70歳になっても80歳になっても(さすがにそれはムリかな・・・)ロックンロールし続けてほしい。ロックが反体制の音楽ならば、ポールだってストーンズの面々に負けず劣らず「永遠の不良」なんですね。改めて「カッコいい!」って思います。
ビートルズ脱退後のポールは、自分のバンド「ウィングス」を率いて、名曲佳曲をたくさん発表しています。
ウィングスは1975年9月からワールド・ツアーを開始しましたが、1976年5月3日から6月23日までは26都市31公演の大規模なアメリカ・ツアーを行いました。ツアーは大成功のうちに幕を閉じ、このうちのアメリカ・ツアーのベスト・トラックを収録したアルバムが、「Wings Over America」として発表されました。なお、日本では当初「ウィングスU.S.A.ライヴ!!」のタイトルでリリースされていましたが、現在ではオリジナル・タイトルの「ウィングス・オーヴァー・アメリカ」に改められています。
ちなみにこのワールド・ツアーでは日本にも来る予定になっていたのですが、ポールは大麻所持容疑で入国を拒否され、たいへんな騒ぎになりましたよね。結局日本公演はキャンセルされてしまったのでした。

たしかNHKの音楽番組でこのワールド・ツアーのアメリカ・ライヴの様子が放映され、それを食い入るように見た記憶があります。まだビデオなんてほとんど普及してなかった頃ですからね、まばたきするのも惜しいような気持ちで見たんですよ。
今聴いても、テンションの高い、エキサイティングなステージであることが伺えます。『ヴィーナス&マース』でスペーシーに、そしてロマンチックに始まったこのステージ、『ロック・ショウ~ジェット』で一気にエネルギーが爆発します。ここで早くも、ポールの世界にどっぷり浸っている自分を感じます。

ビートルズ・ナンバーや、アコースティック・ナンバーなどを交えながら聴かせてくれるヒット曲の数々、しめて28曲。『バンド・オン・ザ・ラン』『マイ・ラヴ』『あの娘におせっかい』『イエスタデイ』『レディ・マドンナ』などなど、名曲のオン・パレードです。
この中でぼくが好きなのは、オープニングのメドレー『ヴィーナス&マース~ロック・ショウ~ジェット』、ブルージーな『レット・ミー・ロール・イット』、デニー・レインがヴォーカルをとる『ゴー・ナウ』、原曲に比べて遥かにワイルドな『ハイ・ハイ・ハイ』、ハード・ロック・バンドを思わせるソリッドでエキサイティングな演奏と、ポールのシャウトが存分に楽しめる『ソイリー』などです。

このライヴ・アルバムは、発売当時はLPレコード3枚組。金額は、いくらだったかな~、6000円くらいだったでしょうか、とにかく子供がおいそれと手を出せるような値段ではなかったので、友達に借りた時に録音しておいたテープを大事に大事に聴いていたものです。
臨場感と熱気に満ちている作品です。とても楽しめました。
バンドのまとまり具合の良さも感じることができます。
この頃のポールやリンダ、ウィングスの面々の写真って変顔をしているものが多いのですが、これはバンド内のいい雰囲気の現れとも言えるんじゃないかな、と勝手に思ったりしています。
演奏面では、目立たないけれど、デニー・レインの「内助の功」というか「陰の功労者」と言っていいサポートぶりは貴重です。
またギターのジミー・マッカロックの荒々しくも瑞々しいプレイぶりも特筆しておきたいですね。ジミーは将来を期待されたロック・ギタリストでしたが、ドラッグの過剰摂取のためこのライブの3年後に急逝しています。
このアルバムのテンションの高さ、30年も時が隔たっているのに、ここ数年の間に発表されたDVDなどと比べても遜色ないんです。
それだけのエネルギーを維持しているポールに、改めて驚かされますね。

◆ウィングスU.S.A.ライヴ!!/Wings Over America
■歌・演奏
ウィングス/Wings
■リリース
1976年12月10日
■収録曲
Side-A
1 ヴィーナス・アンド・マース~ロック・ショウ~ジェット/Venus and Mars ~ Rock Show ~Jet (Paul McCartney)
2 レット・ミー・ロール・イット/Let Me Roll It (McCartney)
3 遥か昔のエジプト精神/Spirits of Ancient Egypt (McCartney)
4 メディシン・ジャー/Medicine Jar (Colin Allen, Jimmy McCulloch)
Side-B
5 メイビー・アイム・アメイズド/Maybe I'm Amazed (McCartney)
6 コール・ミー・バック・アゲイン/Call Me Back Again (McCartney, John Lennon)
7 レディ・マドンナ/Lady Madonna (McCartney)
8 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード/The Long and Winding Road (McCartney, Lennon)
9 007死ぬのは奴らだ/Live and Let Die (McCartney)
Side-C
10 ピカソの遺言/Picasso's Last Words (McCartney)
11 リチャード・コーリー/Richard Cory (Paul Simon)
12 ブルーバード/Bluebird (McCartney)
13 夢の人/I've Just Seen a Face (McCartney, Lennon)
14 ブラックバード/Blackbird (McCartney, Lennon)
15 イエスタデイ/Yesterday (McCartney, Lennon)
Side-D
16 幸せのアンサー/You Gave Me the Answer (McCartney)
17 磁石屋とチタン男/Magneto and Titanium Man (McCartney)
18 ゴー・ナウ/Go Now (Larry Banks, Milton Bennett)
19 マイ・ラヴ/My Love (McCartney)
20 あの娘におせっかい/Listen to What the Man Said (McCartney)
Side-E
21 幸せのノック/Let 'Em In (McCartney)
22 やすらぎの時/Time to Hide (Laine)
23 心のラヴ・ソング/Silly Love Songs (McCartney)
24 愛の証し/Beware My Love (McCartney)
Side-F
25 ワイン・カラーの少女/Letting Go (McCartney)
26 バンド・オン・ザ・ラン/Band on the Run (McCartney)
27 ハイ・ハイ・ハイ/Hi Hi Hi (McCartney)
28 ソイリー/Soily (McCartney)
※CD Disc-1=1~15、Disc-2=16~28
■プロデュース
ポール・マッカートニー/Paul McCartney
■録音メンバー
☆ウィングス/Wings
ポール・マッカートニー/Paul McCartney (bass, acoustic-guitar, piano, keyboards, lead-vocals, backing-vocals)
リンダ・マッカートニー/Linda McCartney (piano, keyboards, percussion, backing-vocals)
デニー・レイン/Denny Laine (electric-guitar, acoustic-guitar, bass, piano, keyboards, percussion, harmonica, lead-vocals[3,11,18,22] backing-vocals)
ジミー・マッカロック/Jimmy McCulloch (electric-guitar, acoustic-guitar, bass, lead-vocals[4], backing-vocals)
ジョー・イングリッシュ/Joe English (drums, percussion, backing-vocals)
★サポート・メンバー
トニー・ドーシー/Tony Dorsey (trombone)
ホーウィー・ケーシー/Howie Casey (sax, percussion)
スティーヴ・ハワード/Steve Howard (trumpet, flugelhorn)
サデュアス・リチャード/Thaddeus Richard (sax, clarinet, flute)
■チャート最高位
1977年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス8位、日本(オリコン)4位
1977年年間チャート アメリカ(ビルボード)35位、日本(オリコン)51位
小曽根真といえば、日本が世界に誇るミュージシャンのひとりです。
彼の活躍する場は、ジャズのフィールドだけにとどまるものではなく、演劇とコラボレイトしたり、クラシックに取り組んで交響楽団と共演するなど、とても幅が広いですね。最近ではドラマ「あしたの、喜多善男」の音楽も担当しています。
小曽根 真
ジャズの世界の小曽根氏を見ても、ピアノ・トリオを始め、ヴォーカルやヴィブラフォーンとのデュオ、ピアノ2台によるデュオ、ビッグ・バンドなど、あらゆる可能性にトライしています。
その中で、ありそうでなかなか見つからないのが小曽根氏によるスタンダード集でした。彼がリーダーを務めるバンドでは、歌モノを除き、ほとんどが彼自身によるオリジナルを演奏しています。ぼく自身、小曽根氏に対して、「オリジナル曲を追求してゆく人」、みたいなイメージを持っていました。そんな中で見つけたのが、この『ネイチャー・ボーイズ』です。
なんでも巷では一時、「小曽根にバップができるはずがない」という評もあったそうです。このアルバムの録音には、そういう風評を吹き飛ばす、という目的もあったらしいです。
しかしスタンダード集といっても、小曽根氏の場合、通りいっぺんの演奏で終わるはずもありません。どの曲にも小曽根流のスパイスがふりかけられています。といっても奇をてらったアレンジではありません。そしてそのアレンジによって「アメリカン・クラシック・ポピュラー・ソングス」が新たな光をもって蘇っているのです。
バックを務めるのはジョン・パティトゥッチとピーター・アースキン。いずれも一騎当千のツワモノです。
ジョン・パティトゥッチ
全9曲のうち、4曲目の「ビフォー・アイ・ワズ・ボーン」だけが小曽根氏のオリジナル。残りは「オール・オブ・ユー」「バット・ビューティフル」「恋人よ我に帰れ」「ゴージャス」「クリスマス・ソング」「オーニソロジー」、ニール・セダカのカヴァー「雨に微笑を」、最後にピアノ・ソロで「ネイチャー・ボーイズ」が収録されています。
1曲目の「オール・オブ・ユー」、イントロから実に躍動的です。テーマに入ると2ビートでパティトゥッチのベースが絡み、2コーラス目からは三者がよくスウィングしながら軽快に曲が進んでゆきます。シンコペーションをうまく使ったブリッジがとても印象的。
「バット・ビューティフル」は、もともとはバラード・ナンバーですが、小曽根氏はこれをジャズ・ワルツに再構築しています。
「恋人よ我に帰れ」はアースキンの刻むシンバルで始まります。テーマは小節数と休符の数を増やし、ゆったり聴こえるように演奏していますが、サビに入ったところから一転して全員が超高速4ビートになだれこむのがスリリング。
「ビフォー・アイ・ワズ・ボーン」は小曽根氏のオリジナル。音がきらめくようなバラードです。
ピーター・アースキン
「雨に微笑を」は、もともと小曽根氏の演奏がテレビのCFに使われていたのですが、このアルバムの録音のためにさらに小曽根氏自身が手を加えています。美しいイントロに続いて現れるのがスピーディーなジャズ・ワルツ。静と動を併せ持っているような曲です。
「ゴージャス」と「クリスマス・ソング」は極上のバラード。美しいメロディーを持っている「ゴージャス」は、一種神々しささえ感じます。
「クリスマス・ソング」は、ぼくが最も好きなクリスマス・ソングで、いろんなヴァージョンがありますが、これにはリハーモナイズ(コード進行の再現)が施してあったり、エンディングでは3連になるなど、また違った味わいを楽しむことができます。
「オーニソロジー」は「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」のコードを元にした、チャーリー・パーカーの愛奏曲です。バップの香りが漂う、軽快な4ビートです。
「ネイチャー・ボーイズ」はタイトル曲。マイナー調の哀愁漂うスタンダード・ナンバーで、ソロ・ピアノで演奏されています。
流麗なパティトゥッチのベース、タイトでメリハリの利いたアースキンのドラムを従えた小曽根氏のピアノ、端正で知的な雰囲気がよりいっそう引き立っているような気がします。この三者がブレンドされたサウンド、まるでレギュラー・トリオのようにアグレッシヴで、意思のあるまとまりを見せていると思います。
でも、驚くことにパティトゥッチもアースキンも、初見の状態で録音に臨んだそうで、それでもこれだけ綿密にコラボレイトできるということは、三人の並外れた力量をも物語っているとも言えるでしょう。
「スタンダード集」だとはいえ、「小曽根流のスパイス」がよく利いていて、小曽根氏のオリジナル作品と言ってもよいくらい、彼の味・雰囲気に満ちているアルバムではないでしょうか。
◆ネイチャー・ボーイズ/Nature Boys
■演奏・プロデュース
小曽根真
■アルバム・リリース
1995年12月1日
■レコーディング
1995年10月4日~5日 ハッター・スタジオ(ロサンゼルス)
■レコーディング・エンジニア
バーニー・カーシュ/Bernie Kirsh
■収録曲
① オール・オブ・ユー/All Of You (Cole Porter)
② バット・ビューティフル/But Beautiful (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)
③ 恋人よ我に帰れ/Lover Come Back To Me (Sigmund Romberg, Oscar HammersteinⅡ)
④ ビフォー・アイ・ウォズ・ボーン/Before I Was Born (小曽根真)
⑤ 雨に微笑みを/Laughter In The Rain (Neil Sedaka, Philip Cody)
⑥ ゴージャス/Gorgeous (Mitchell Forman)
⑦ クリスマス・ソング/The Christmas Song (Mel Torme, Robert Wells)
⑧ オーニソロジー/Ornithology (Charlie Parker, Benny Harris)
⑨ ネイチャー・ボーイ/Nature Boy (Eden Ahbez)
■録音メンバー
小曽根真 (piano)
ジョン・パティトゥッチ/John Patitucci (bass)
ピーター・アースキン/Peter Erskine (drums)
■レーベル
VERVE
エリック・クラプトン、2005年の2月に59歳にしてパパになったんでしたね。
この年には久しぶりにニュー・アルバム「バック・ホーム」も出しているし、音楽生活でも私生活でも充実していたのでしょうね。
こんど、「Hold on, I'm Coming」を演奏することになったので、今夜はその音ネタの仕込みのために、エリック・クラプトンとB.B.キングが組んだアルバム、「ライディング・ウィズ・ザ・キング」を聴いています。
買ったばかりの時はあんまり耳に馴染まなくて、それからほっておいたんですけれど、久しぶりに聴いてみると、これ、意外に良かった! けっこう気に入っちゃったな~
タイトルの「キング」とは、もちろんB.B.自身の姓ですが、「ブルースのキング」という意味もかけたものなのでしょう。
ジャケットには、キャデラックを運転するエリックと、バック・シートで貫禄たっぷりにフンゾリ返っているB.B.が写ってます。まさに「ライディング・ウィズ・ザ・キング」です。
エリックとB.B.の笑顔がまたイイのだ。
そういえばこのふたり、映画「ブルース・ブラザーズ 2000」でも共演してましたね。
ふたりとも、ブルース・ブラザーズのライバル・バンド、「ルイジアナ・ゲイター・ボーイズ」のメンバーという役どころでしたが、この劇中のライヴのなんて楽しそうなこと!そして貫録たっぷりのB.B.のパフォーマンスには言葉もないくらいシビれました。
エリックの少年の頃からのアイドルがB.B.キングだというのは有名な話ですね。ちなみにこのふたり、20歳違いです。
ブルースに傾倒していることで知られているエリックですが、アルバムの販売戦略のためポップ寄りな作風にならざるを得ないこともあるようです。しかし御大B.B.と共演したこのアルバムでは心ゆくまでブルースにひたり、思う存分弾き倒した、って感じです。
このアルバムで聴かれるブルースはほどよく洗練されています。例えて言うなら、どちらかといえばクラプトンのカラーが濃く、そこにB.B.が客演した、という雰囲気を感じました。
全体的にいい感じでリラックスしているのがなんとも言えず心地良いですね。いくつになっても時間を忘れてギターと戯れるオトナふたり。想像するだけでこちらまでニヤリとしてしまいます。
このアルバムの制作中には、ジャケットと同じような笑顔がきっと何度も見られたことでしょう。
「ヘイ、エリック、お前さんますます味が出てきたじゃないか」
「さっきのソロ、ゴキゲンだったよ、B.B.!」
なーんてね。
◆ライディング・ウィズ・ザ・キング/Riding With The King
■歌・演奏
エリック・クラプトン & B.B. キング/Eric Clapton & B.B. King
■リリース
2000年6月13日
■プロデュース
エリック・クラプトン、サイモン・クライミー/Eric Clapton, Simon Climie
■収録曲
① ライディング・ウィズ・ザ・キング/Riding With The King (John Hiatt)
② テン・ロング・イヤーズ/Ten Long Years (Jules Taub, B.B. King)
③ キー・トゥ・ザ・ハイウェイ/Key To The Highway (Big Bill Broonzy, Charles Segar)
④ マリー・ユー/Marry You (Doyle BramhallⅡ, Susannah Melvoin, Craig Ross, Charles Segar)
⑤ スリー・オクロック・ブルース/Three O'clock Blues (Lowell Fulson)
⑥ ヘルプ・ザ・プアー/Help The Poor (Charles Singleton)
⑦ アイ・ウォナ・ビー/I Wanna Be (Doyle BramhallⅡ, Charlie Sexton)
⑧ ウォリード・ライフ・ブルース/Worried Life Blues (Sam Hopkins, Big Maceo Merriweather)
⑨ デイズ・オブ・オールド/Days Of Old (Jules Taub, B.B. King)
⑩ ホエン・マイ・ハート・ビーツ・ライク・ア・ハンマー/When My Heart Beats Like A Hammer (B.B. King, Jules Taub)
⑪ ホールド・オン・アイム・カミング/Hold On I'm Coming (Isaac Hayes, David Porter)
⑫ カム・レイン・オア・カム・シャイン/Come Rain Or Come Shine (Harold Arlen, Johnny Mercer)
■録音メンバー
エリック・クラプトン/Eric Clapton (guitar, lead-vocals①③~⑨⑪⑫)
B.B. キング/B.B. King (guitar, lead-vocals)
ドイル・ブラムホール Ⅱ/Doyle Bramhall Ⅱ (guitar①②④⑥⑦⑨~⑫, background-vocals④⑦)
アンディ・フェアウェザー・ロウ/Andy Fairweather Low (guitar①②④⑥⑦⑨~⑫)
ジミー・ヴォーン/Jimmy Vaughan (guitar⑥)
ジョー・サンプル/Joe Sample (acoustic-piano①⑤⑥⑨⑩⑪, electric-piano①②⑪)
ティム・カーモン/Tim Carmon (organ①~⑦⑨~⑫)
ネイザン・イースト/Nathan East (bass)
スティーヴ・ガッド/ Steve Gadd (drums)
スザンナ・メルヴォワン/Susannah Melvoin (background-vocals①④⑦⑨)
ウェンディ・メルヴォワン/Wendy Melvoin (background-vocals①④⑦⑨⑪⑫)
ポール・ウォーラー/Paul Waller (programming)
■チャート最高位
2001年週間アルバム・チャート アメリカ3位、イギリス15位、日本(オリコン)6位
ジャズの魅力。
いろんな魅力を自由に感じることができるのが"魅力"だと思います。
心地よいスウィング感。創造性。演奏技術の素晴らしさ。即興演奏。ほかにもいろんな要素はあると思います。
「スタンダーズ」と呼ばれるキース・ジャレットのトリオは、文字通りスタンダード・ナンバーを、彼らならではの斬新な解釈で聴かせてくれます。
より自由度の増した展開の面白さ、とでも言ったらいいのでしょうか。

キース・ジャレット・トリオ "スタンダーズ" 左からK・ジャレット、G・ピーコック、J・ディジョネット
目の前で繰り広げられるスリリングな即興演奏、緊張感のある音の構築、そして演奏が行われている場所を支配している熱気などが、生で演奏を聴くことの楽しみではないか、と思うのですが、このアルバムを聴いていると、部屋がまるでライヴ・ハウスのような空気に変わっていくのが感じられて、とても面白い。
仲の良い友人同士で交わされる話は、互いの言葉が互いを刺激して、どんどん会話が発展してゆくものですが、このトリオの演奏もそれに似たものを感じます。メンバー三人による、会話にも似た音のやりとりがとても新鮮で、見事に調和しているんですよね。

『星影のステラ』『ロング・ブルース』『恋に恋して』『トゥー・ヤング・トゥ・ゴー・ステディ』『今宵の君は』『オールド・カントリー』の6曲が収められていますが、どれも美しくて質の高い名演奏と言えるのではないでしょうか。
中でもに『星影のステラ』のスピリチュアルなまでの美しさは「素晴らしい」の一語に尽きると思います。
そして、6曲目の『オールド・カントリー』が終わったあとに聴かれる熱のこもった拍手と歓声、それがこのアルバムの本質を端的に伝えているような気がします。
三人の創造力と演奏技術の高さは言うまでもありません。そしてそれぞれが互いに影響を及ぼし合い、研ぎ澄まされた音を生み出してゆきます。
聴いているぼくは陶酔感に満たされます。
そう、「ジャズの楽しさ」を充分に味わうことができるんです。

◆"スタンダーズ"ライヴ!/星影のステラ (Standards Live)
■演奏
キース・ジャレット・トリオ
キース・ジャレット/Keith Jarrett (piano)
ゲイリー・ピーコック/Gary Peacock (bass)
ジャック・ディジョネット/Jack DeJohnette (drums)
■録音
1985年7月2日 パリ、パリ・デ・コングレ
■リリース
1986年
■レーベル
ECM
■プロデュース
マンフレート・アイヒャー/Manfred Eicher
■収録曲
① 星影のステラ/Stella by Starlight (Ned Washington, Victor Young)
② ザ・ロング・ブルース/The Wrong Blues (William Engvick, Alec Wilder)
③ 恋に恋して/Falling in Love with Love (Lorenz Hart, Richard Rodgers)
④ トゥー・ヤング・トゥ・ゴー・ステディ/Too Young to Go Steady (Harold Adamson, Jimmy McHugh)
⑤ 今宵の君は/The Way You Look Tonight (Dorothy Fields, Jerome Kern)
⑥ オールド・カントリー/The Old Country (Nat Adderley, Curtis Lewis)
「ファースト・アルバムはそのミュージシャンの本質を表している」という言葉を聞いたことがあります。このアルバムを聴くと、それはまさに真理だという気がしてなりません。
今や、ジャズ・ピアニストの最高峰を極めた感のあるキース・ジャレット。
彼のトリオは「スタンダーズ」と呼ばれ、数多くの作品を発表していますが、そのファースト・アルバムである『Vol.1』を聴くと、やはりこのトリオの本質が色濃く出ているように思うのです。
スタンダード・ナンバーをキースならではの解釈で再構築するのがこのトリオのコンセプトのひとつですが、こうして聴いてみると、キースの音楽性の深さ、大きさには改めて圧倒されるばかりです。
また、共演者のゲイリー・ピーコック(bass)、ジャック・ディジョネット(drums)とも当代きっての名手として鳴らしているだけに、キースのピアノと対等に渡り合っているのがよく分かりますね。

それぞれが超一流である三人が、おそらくはとても楽しみながら、そして信じがたい集中力で演奏を繰り広げているのでしょう。彼らは一緒に音を出してみて、すぐに「何かが生み出せる」確信を得たに違いありません。集まるべくして集まったトリオ、と言えると思います。
この三人の相性の良さは、例えば1+1+1が5にも6にもなるようなものだと言っていいでしょうね。
それぞれに自由な音楽的背景や着想を持ちながら、それを放出する時にはひとつの方向に向いているところに、このトリオから得られる大きな感動があると思うんです。
また言うまでもないことではありますが、三人ともがタイム感覚やグルーブ感を内包していることで、リズムの流れ、グルーブの波がより厚くより強力なものとなって聴いているぼくを包んでくれることも、このトリオの魅力のひとつだと思います。

演奏中に「何かが降りてくる」ようなことを感じることがありますが、とくにぼくの好きな5曲目の『ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド』においては、まさにそういう深みへ下りて行くような雰囲気を感じます。ごくリラックスしていながら、一方では静かに、そして激しく燃え盛っているさまはスピリチュアルでさえあり、この曲をゴスペルのように荘厳で魅力的なヴァージョンに仕立て上げているのです。
この曲におけるゴスペル・ロックのような演奏は、ぼくのフェイヴァリットでもあります。心が震えるんです。
聴き始めた最初の頃は、あまりの素晴らしさに何度も何度も繰り返し、そのたんびに全身を耳にして聴いていました。
ついつい堅苦しい文章になってしまいがちですが、平たく言うとぼくは、「これは文句のない名盤である」と言いたいだけなのです。
◆スタンダーズVOL.1/Standards VOL.1
■演奏
キース・ジャレット・トリオ
キース・ジャレット/Keith Jarrett (piano)
ゲイリー・ピーコック/Gary Peacock (bass)
ジャック・ディジョネット/Jack Dejohnett (drums)
■リリース
1983年
■録音
1983年1月11~12日 ニューヨーク市、パワー・ステーション
■プロデュース
マンフレート・アイヒャー/Manfred Eicher
■レーベル
ECM
■収録曲
A① ミーニング・オブ・ザ・ブルース/Meaning of the Blues (Bobby Troup, Leah Worth)
② オール・ザ・シングス・ユー・アー/All the Things You Are (Oscar Hammerstein Ⅱ, Jerome Kern)
③ イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド/It Never Entered My Mind (Lorenz Hart, Richard Rodgers)
B④ ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー/The Masquerade Is Over (Herb Magidson, Allie Wrubel)
⑤ ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド/God Bless the Child (Arthur Herzog Jr., Billie Holiday)