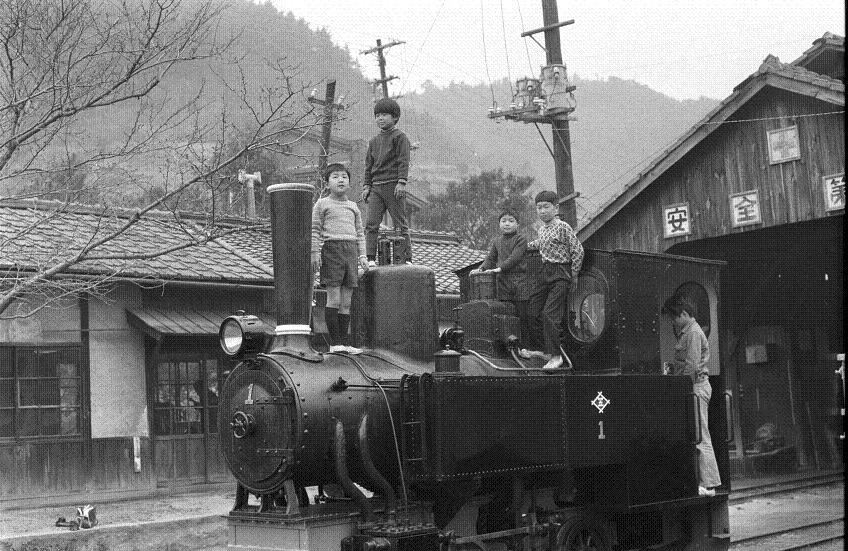撮影場所 広島県河内町(現在は東広島市)
大和町から河内町の茅葺き民家を探す。
茅葺き民家の脇に小屋があり茅だったが痛みかけていた。
造りはこのあたりでよく見かける寄棟の箱棟です。瓦は茶色の釉薬瓦
軒下に椅子が置いてありご主人が新聞を読み始めたので撮影させてもらう。
この近所に茅葺き民家が聞いた。
三軒教えてもらったがうち二軒はいくら探しても発見できず。

大和町から河内町の茅葺き民家を探す。
茅葺き民家の脇に小屋があり茅だったが痛みかけていた。
造りはこのあたりでよく見かける寄棟の箱棟です。瓦は茶色の釉薬瓦
軒下に椅子が置いてありご主人が新聞を読み始めたので撮影させてもらう。
この近所に茅葺き民家が聞いた。
三軒教えてもらったがうち二軒はいくら探しても発見できず。