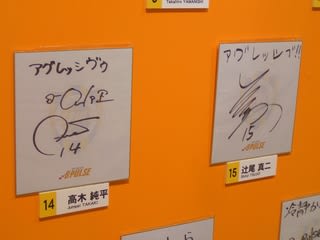<勝ち組、負け組>のような俗語の誤解釈や誤用は、言葉の意味や使用法が時代によって変遷していく<俗語の生命力>の一例ともいえるわけだが、もはや歴史的に、全世界的に疑う余地のない言葉の意味・意図を捻じ曲げてまで八つ当たりする連中というのは何なんだろう。
キミたちがどう思うか、どう感じるか、<暴力装置>という客観的な言葉とは関係ない。
知らなかった言葉をひとつ知り、社会や歴史を俯瞰的に見られるきっかけになれば、それはそれで素晴らしいことじゃないか。知らない、わからないということ――それは全然恥かしいことじゃない。
橋本治の『「わからない」という方法』 (集英社新書)でも読んでみましょう。
ということで<暴力装置>という言葉に、感情的に反発している人たちというのは、どう考えても、実は売り言葉に買い言葉と同じような勢いで拳を振り上げてしまった手前、後に引けないだけなんじゃないか。
それはあまりにも見苦しいし、みっともない…。
そして本当は意味をしっかり理解しているくせに、場当たり的に謝っちゃう人もどうかと思う(←こっちの方は確信犯)。
<暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(Organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを権力の根本にある暴力装置と位置づけた。>(はてなキーワード>暴力装置)
キミたちがどう思うか、どう感じるか、<暴力装置>という客観的な言葉とは関係ない。
知らなかった言葉をひとつ知り、社会や歴史を俯瞰的に見られるきっかけになれば、それはそれで素晴らしいことじゃないか。知らない、わからないということ――それは全然恥かしいことじゃない。
橋本治の『「わからない」という方法』 (集英社新書)でも読んでみましょう。
ということで<暴力装置>という言葉に、感情的に反発している人たちというのは、どう考えても、実は売り言葉に買い言葉と同じような勢いで拳を振り上げてしまった手前、後に引けないだけなんじゃないか。
それはあまりにも見苦しいし、みっともない…。
そして本当は意味をしっかり理解しているくせに、場当たり的に謝っちゃう人もどうかと思う(←こっちの方は確信犯)。
<暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(Organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを権力の根本にある暴力装置と位置づけた。>(はてなキーワード>暴力装置)