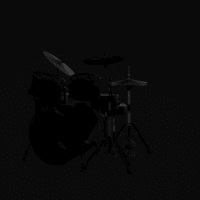今回は、音楽記事です。
これまで音楽カテゴリーでは、いわゆるグループサウンズ(GS)のミュージシャンについて書いてきました。
そのなかで再三ふれてきたように、GSは一過性のブームで終わってしまいます。
そして、そのブーム終焉後に、GSオールスターズともいうべきバンドとして登場したのが、PYGでした。
というわけで、今回のテーマは、PYG。
PYGは、いうなれば、本邦音楽業界における歌謡曲の重力場にさからって飛ぼうとしたイカロスのような存在です。その挑戦と挫折は、この国におけるロックという音楽の立ち位置をはっきりと示しているように思われるのです。
PYGは、GS三大バンドのメンバーが結集したスーパーグループでした。
スパイダースから、井上堯之(Gt)、大野克夫(Key)、タイガースから沢田研二(Vo)、岸部おさみ(Ba)、テンプターズから萩原健一(Vo)、大口広司(Dr)……
錚々たる顔ぶれです。
バンド名は、豚のpig
からきています。
それは、アルバムジャケットにも示されているとおり。
つづりがPYG
となっているのは、アラン・メリルの発案とか。このアラン・メリルというのは、かまやつひろし、大口広司とともにウォッカコリンズを結成した人で、なかなかすごい経歴の持ち主です。
しかし……そのオールスターぶりとは裏腹に、PYGの活動は成功とは程遠いものとなりました。
活動当初からチャートアクションはぱっとせず、その結果、短期間の活動に終わってしまったのです。
彼らは、“ニューロック”を志向していたとよく指摘されます。
ニューロックというのは、新しいロック……私がいう“第二世代”ロックとほぼ同じ意味と考えていいでしょう。
サイケデリックとかアートロックとかいうことがいわれはじめ、まだジャンルとしてのプログレッシブも確立していなかった時代、なにかそれまでのロックとはちょっと違うというものを漠然と“ニューロック”と呼んでいたようです。
PYGが目指したのは、このニューロックの方向でした。
デビューシングル「花・太陽・雨」に、それははっきりと表れています。
冒頭に鳴らされる不協和音めいたコード……これは、GSの音楽世界には存在しえない響きでした。
デビューアルバム『PYG!』の一曲目に収録されている「戻れない道」なんかは、私の感覚では、だいぶいい感じにロックになってると思います。
GSではそぎ落とされていた要素が、前面に出ています。GSが退潮した後だったがために、GS時代にはできなかったことができるようになったのではないか……とも想像されます。
しかしこれが、当時の環境下では受容されませんでした。
単に「受け入れられなかった」というだけではなく、ロック界隈では積極的な批判の対象とさえなっていました。PYGは、フェスに出演すれば、“商業主義!”、“帰れ!”などと罵声を浴び、ステージにものが投げ込まれるなどしていたといいます。
これは、ビーチボーイズと同じようなことが起きていたのだと思われます。
以前書きましたが、ビーチボーイズはPet Sounds によって新たな方向性を打ち出し、それによって低迷するようになりました。それまでビーチボーイズファンが離れていき、新世代のリスナーたちは旧世代のアーティストが入ってきても目もくれないという……基本的にはその構図です。
そして日本の場合は、そもそもGSという旧世代ロックが失速していたわけなので、ますますPYGは寄る辺ない存在であったでしょう。
新世代のリスナーからみれば、GSという旧世代のくたばりぞこないが、顔の売れているメンバーをかき集めてなんとか延命をはかろうとしている――というふうにしか見えなかったのだと思われます。
実際には、PYGが目指したのは新たな世代のロックであり、それは決して中途半端なものではなかったと思いますが……
しかし、それが受け入れられることはありませんでした。
先述したように、GSはもはや過去の遺物となっていて、新たな領域に踏み出したPYGはもう帰る場所も失っていました。離陸したまま、行先も帰る場所ももたない飛行機のようなもの。まさに“戻れない道”……空中分解するよりほかはなかったのです。
やがてジュリーさんのソロ活動のほうが目立つようになり、ショーケンさんは早々と離脱。PYGは、いつの間にか消滅してしまいます。
これはやはり、ビーチボーイズと同じ悲劇ということでしょう。
ほんのちょっとしたタイミングのずれというか……
世代と世代のはざまに開いた亀裂――PYGは、そのなかに呑み込まれてしまったのです。
この試みを主導したのは岸部修三さんでしたが、その後の彼は、サリーでも、岸部おさみでもなく、岸部一徳として俳優業に軸足を移していきました。
この国はやはり、基本的にロックにとって不毛の地なのです。
オールドロックもニューロックも、和風の味付けをかなり濃い目に施さなければ受け入れられないということでしょうか。
とりわけ、60~70年代ぐらいの日本ではそういう傾向が強かったのではないかと思われ、さらぬだに歌謡曲の対極にある“ニューロック”は、苦戦する運命にあったといえるでしょう。
しかし、そんな本邦にあっても、ニューロックという試みに取り組んだアーティストは存在します。次回以降の音楽記事では、そうしたアーティストについて書いてみようと思います。