今日は5月3日。
憲法記念日です。
いまから76年前のこの日、日本国憲法が施行されました。
関連する話として、先日、サンフランシスコ平和条約発効記念日の記事がありました。
そこで、戦後日本が同じことを繰り返さないように、戦勝国側による民主化を主導したという話をしましたが、日本国憲法は、その具体的な方策の一つだったといえるでしょう。
ゆえに、押し付けだというような反発があるわけですが……これに関しては、日本側がみずからそれを作れなかったのならしょうがいないんじゃないかと私は思ってます。
まあ、GHQ案も日本人の考えた案を参考にしているとか、国会審議の過程で日本の政治家がくわえた修正もあるとか、そういった話はあるわけですが……究極的には、自らの手で民主的な憲法を作れなかったのなら「しょうがないからこっちで作ってあげたよ」といって与えられても文句はいえないんじゃないかと。
成立の経緯がどうであれ、世論調査によればその憲法を当時の日本国民の7割ほどが支持したのであり、その憲法によって戦後の日本はまあそれなりにうまくやってきたといえるでしょう。
ただ、惜しまれるのは、その民主化が不徹底だったということです。冷戦を背景にして、いわゆる“逆コース”というかたちで保守反動を容認してしまった。公職から永久に追放されるべきだった人たちを復帰させてしまった……このことによって、せっかくの民主化を台無しにする種が胚胎されてしまったのです。そして、その種がじわじわと根を張り、戦後6、70年を超えたいまになっていよいよ民主化を台無しにしはじめているように見えます。
そして、民主化を台無しにした先に待っているのは、たぶん今のロシアのような国家です。選挙制度は形ばかりで、大統領が勝手に戦争を起こし、徴兵はオンライン、戦争に反対したら牢屋行きといった法律が次々に作られていく……そんな国になってしまわないためには、いま一度日本国憲法というものの持つ意味を考え直す必要があるのではないでしょうか。










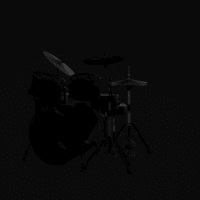









むかし「戦争を知らない子供たち」というフォークソングがありましたが、
社会がどんなに不景気でも、こんな時代が続いてほしいと思っています。
「戦争を知らない子供たち」、名曲ですね。
近年、雲行きが怪しくなってきているようにも感じられますが……「戦争を知らない」世代が続いていってほしいと思います。