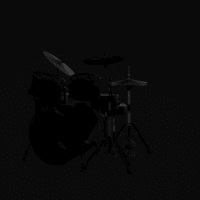前回は、拙著『ホテル・カリフォルニアの殺人』のモチーフになっているイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」について書きました。
ことのついでなので、何回かにわたって、作中に出てくるほかの曲についても書いておこうと思います。
とりあえず、第一章の章題になっている「テイク・イット・イージー」です。
これもまた、イーグルスの代表曲の一つですね。
意外とあまり知られていないことだと思いますが、この曲はジャクソン・ブラウンというアーティストとの共作です。
ジャクソン・ブラウンはウェストコーストを代表するシンガーソングライターの一人ですが、イーグルスの面々とは古くから親交があって、共作している曲がいくつかあります。「テイク・イット・イージー」も、そのなかの一つです。
広大な平原で、地平線まで続くハイウェイを車で飛ばしているような、軽快な曲です。
Take It Easy というのは「気楽にいこうぜ」というほどの意味で使われる慣用表現ですが、まさにこのタイトルがぴったりといえるでしょう。
オープニングから、カリフォルニアの日差しのようなさわやかなギターが響きます。
G音をペダルトーンふうに響かせながら、G→C→Dsus4という構成も、簡単そうにみえてなかなか思いつかないものでしょう。
ペダルトーンというのは、コードが変わっても同じ音をずっと出し続けるというものです(吹奏楽器でいう「ペダルトーン」とは、また別の意味の言葉です)。
本来コードに含まれていない音が鳴っているわけですが、前の小節から続いてきていたりすると、それほど奇妙には感じられません。もちろん多少の違和感はありますが、その違和感がむしろ「お?」という感じを与えます。まわりの和音環境が変わってもそれに合わせずにひたすら同じ音が続いているのは、なにか、揺るがない、力強い意志のようなものを感じさせる表現だと私は思っています。
もっとも「テイク・イット・イージー」の場合、Cのあとに続くコードをDsus4ととらえれば(ふつうはそう解釈するでしょう)別にGはコードからはずれた音じゃないということにもなりますが、それでもやはり、同じG音が続いているのはペダルトーンに通ずる効果を上げているように思えます。
このイントロに、「陽気で軽快そうにみえて、じつは一本の強固な芯がある」という感じが表れているように私には感じられるのです。
このフレーズを2回繰り返したあとにドラムが入ってくるのですが、ここで、拍子がずれたように感じられるという仕掛けが用意されています。
というのはつまり、曲の開始部分が実は小節のはじまりと一致していなかったということなのですが……なぜこんなふうになっているのか不思議なところです。ある種のイタズラ心なんでしょうか。
そこから、歌が入ってきます。
この歌のリードボーカルは、今は亡きグレン・フライ。ドン・ヘンリーとはまた一味ちがった、のびのびとした歌声です。私はどちらかといえばドン・ヘンリー推しですが、この曲はたしかにグレン・フライのほうが合っているような気もします。
曲が進んでいくと、イーグルスの特徴であるコーラスワークや、これでもかというほどのギター多重奏にくわえ、間奏ではバンジョーが使われていたりして、陽気な気分を盛り上げてくれます。
しかし、この歌は、単に陽気なだけの歌ではありません。
前回扱った「ホテル・カリフォルニア」と同様に、この歌もまた、ヒッピー的な精神性をその根底においています。
映画の『イージー・ライダー』にヒッピーたちのコミュニティが描かれていますが、ああいった反・物質文明的な価値観が根っこにあるのです。
「テイク・イット・イージー」の共作者であるジャクソン・ブラウンは、子供の頃に「サンダーバーズ」という少年団体に所属していました。
その団体の活動でアメリカ先住民であるホピ族の文化に触れたことがあり、その体験が、成長してミュージシャンになってからのキャリアにも大きな影響を及ぼしているようです。
それは、“キリスト教徒の白人”という立場からのみ見た価値観への懐疑という形になって表れます。
キリスト教徒の白人から見れば、アメリカの開拓は冒険譚・英雄譚ということになりますが、先住民からみれば、追い立てられ、侵略される歴史です。また、黒人からすれば、アメリカが独立しても自由を与えられず、奴隷として酷使されてきた歴史でしょう。
だから、ジャクソン・ブラウンはアメリカの“正義”というものを素直に信用しません。
そういう観点が、物質主義への批判につながっていき、それがまた、イーグルスの面々と共鳴することになります。
たとえばイーグルスのアルバム『ホテル・カリフォルニア』に、「ラスト・リゾート」という曲がありますが、これもまさに同じような問題意識で作られた歌です。
「ラスト・リゾート」では、「白人の責務」(white man's burden)という言葉が出てきます。
これはキプリングの有名な言葉ですが、白人がその責務として野蛮人を「文明化してやっている」という上から目線の植民地主義を象徴する言葉としても知られています(キプリング自身にそういう意図があったわけではないともいわれますが)。
この「文明化してやっている」という立場で、ヨーロッパからきた移民たちはアメリカ先住民を追い立てていき、その土地を奪い、文化を奪いました。このことを、「ラスト・リゾート」は、「金持ちたちがやってきて、その地をレイプした」と痛烈に批判しています。
まさに、先ほど述べたジャクソン・ブラウンと同じ問題意識があることがわかるでしょう。
そうした観点は「ホテル・カリフォルニア」にもありますし、それはほとんど真反対の曲調に聞こえる「テイク・イット・イージー」にも通底しています。
明かりをともすんだ それができるうちに
理解しようなんて思っちゃいけない
お前のいるべき場所を見つけ出せよ
と、ジャクソン・ブラウン/イーグルスは歌います。
理解しようなんて思っちゃいけない
お前のいるべき場所を見つけ出せよ
と、ジャクソン・ブラウン/イーグルスは歌います。
刷り込まれた価値観ではなく、自分自身の心にしたがって、あるべき場所を探せというのです。
そんなふうに考えると、冒頭部分の変拍子まがいのしかけも「最初に聞かされたことをうかつに信じちゃいけないよ」というメッセージなのかもしれません。
前述したように、これはつまり、一拍目だと思っていた拍がじつは一拍目ではなかったということなので、リスナーからすると、最初に入り込んだ曲の世界がくつがえされてしまうわけです。そうして、はじめにこうだと思っていたことが覆された状態にリスナーを放り込み、本当に信じられるものを見つけろ、ということなのかもしれません。
まあ、これはさすがに深読みのしすぎかもしれませんが……せっかくなので、もう少し深読みを続けてみます。
「変拍子まがい」と書きましたが、よくよく考えてみれば、これを実際に変拍子ととらえても別に不都合はありません。
まぎらわしいシンコペーションなのかもしれないし、変拍子なのかもしれない。譜面的には、どちらにも解釈できます。
こうなってくると、この不確定さに、よりどころのない、放り出されたような気持になります。
でも、ここで見方を変えてみるとどうでしょう。
よりどころがないということは、ある意味自由でもあります。
よるべがないということは、つまり、自分を縛り付けるものがない、自由ともいえる。そう、サルトルふうに解釈しなおすこともできるのです。
それはたとえば、一枚の真っ白な紙をわたされて、「ここになんでも描きなさい」といわれているような自由です。
「なんでも描いていいといわれたって困るよ」と途方に暮れるのか、「そうか、なんでも描いていいのか!」と喜ぶか。
これは、イーグルスやジャクソン・ブラウンが出てきた当時の社会状況に重なっている部分があります。
70年代初頭というのは、政治の季節から経済の季節へと移行しつつある時期だったと、前回「ホテル・カリフォルニア」の記事で書きましたが、この変化は音楽の世界にもある種の混迷をもたらしていました。
社会運動と連動していたフラワームーブメントが一段落し、進むべき方向が見えなくなっていたのです。
それ以後、多くのアーティストが社会的なメッセージを込めた歌を歌わなくなり、代わりに、捨て鉢な態度で既存の価値観を徹底的に否定するパンクが台頭してくることになるわけですが、その過渡期に、ある種の真空状態がありました。
これまであった“流行”がすたれ、まさに白紙の状況が生じたのです。
その「進むべき方向がみえない」ということを、誰かに示された道を進まなくてもいい、自分の好きな方向を目指していい、という“自由”ととらえたのが、ジャクソン・ブラウンやイーグルスの面々でした。
それは、いうなれば“白紙の自由”です。
誰かに決められることはないけれど、その代わりに自分で決めなければならない。そういう覚悟を求められる自由。みわたすかぎりの荒野を走るような……と、ここで「テイク・イット・イージー」に話が戻ってきます。
まさに「テイク・イット・イージー」は、“白紙の自由”を歌った歌だと思えるのです。
だとしたら、例のイントロ部分の奇妙な拍子は、その音楽的な表現なのでは……というのは、やっぱり深読みのしすぎでしょうか。