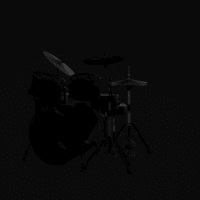今月の14日……
2月14日は“ローリング・ストーンズの日”ということで、このブログでストーンズに関する記事を書きました。
しかし、なにしろストーンズというのは、ロック史においてあまりに巨大な存在です。
研究も相当にされているし、あれこれ論じようと思えば、いくらでも論点があるわけです。
個人的にこれは書いておこうと思いながら書き漏らしたことも多々あり……そういうことなので、今回は、ストーンズについてもう少し書いてみようと思います。
掘り下げられるべき論点は、前回の記事でも少し触れた「ストーンズは裸の王様に過ぎないのか」という問いです。
この問いに対する答えが、部分的にイエスなのは疑いようがないと思われます。
ストーンズというバンドは、あまりにも多くの装飾に飾り付けられている。それによって、実体が見えなくなってしまっている。
そのこと自体は、ストーンズファンも認めるでしょう。
スタジアムに数十万人の観客が集まったとしても、そのうちどれだけが日ごろからストーンズを聴いてその音楽に共感しているのか、という話です。
ここで問題になってくるのは、その装飾のかなりの部分がミック・ジャガー自身によって施されているというところでしょう。
前にも書いた、ミック・ジャガーの“商魂”という部分です。
ミック・ジャガーがバンドに施したさまざまな演出が、ストーンズ伝説を作り出していることは否定できないでしょう。
ここには、ミック・ジャガーという人の出自もかかわっているものと思われます。
ミック・ジャガーは、中流階級の出身です。
しかも、中の上ぐらいの、そこそこ裕福な家庭で育ったといいます。
その表れなのか、たとえばステージ上で服を脱いだりしても、その服を脱ぎ捨てずに畳むような感じで置いておくといいます。行儀がいいのです。
実際、ミック・ジャガーというのは会ってみるとジェントルマンだという評がありますが、それも育ちがいいためでしょうか。話す英語も、労働者階級の粗野な英語ではなく、きれいな英語なのだとか。
あるいは、学歴。
ミックは、高校も出たし大学も出た人です。
その出身大学というのが、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス。卒業後の進路として、国税局に進むことも真剣に考えていたのだとか。
大卒のミュージシャンは別に珍しくないでしょうが、経済系というのはなかなか異例ではないでしょうか。
さらに、もっと根本的なことをいうと、白人であるということがあります。
これはロック全体にかかわることですが……白人が黒人の音楽をやっているというねじれがロックの根源に横たわっているということは、これまでにも書いてきました。いうなら、黒人の真似事をしているというコンプレックスがあるわけです。
それは多くのロックミュージシャンにあてはまることなんですが、そういうねじれを、ミックは肌の色以外にも持っているわけです。
いいとこの坊ちゃんで、大学では経済を学んだ――という履歴は、ロックンローラーのそれとしてかなり違和感があるのではないでしょうか。
そういうことがあるために、ミックは自分自身を演出しなければならなかった。
ワルの仮面をかぶらなければならなかった。
これが、ミック・ジャガーが自らを演出していく一つの動機となっているように思われます。
逆にそこから、ストーンズでやってることはある種の演技なんじゃないかという疑惑も出てくることになるわけです。
ミック・ジャガーの二面性とかいうことがよくいわれるのも、そういうところでしょう。
ステージ上の演出なんかも、実は周到な計算にもとづいてやってるんじゃないか……そんなことがしばしばいわれます。
たとえば、ストーンズの日の記事で紹介したマディ・ウォーターズとの共演。
あの動画をみていると、一人ずつ呼ばれてステージに上がっていって、その場で即興でやっているところはすごくかっこよく見えます。これこそ、ロックというものの本来の姿だ……みたいなことを書こうともするんですが、しかしそこで、いやちょっと待てよとなります。もしかすると、これも事前にきっちり筋書きを用意したうえでの演出なんじゃないか……そういう疑念が首をもたげてくるのです。
この視点を一度もってしまうと、ストーンズにまつわるいろんなものがそんなふうに見えてくるようになります。
たとえば、初期の代表曲である「サティスファクション」はどうか。
満足なんかできやしねえというあの歌は、若者の不満を代弁するものといわれる。だが、それは本当に彼らの言葉なのか? 不満を抱える若者にアピールするようにそんな歌詞を書いただけなのではないか……?
その歌詞中にあるI Can't Get No Satisfaction というフレーズは、英文法としては間違っています。一つの節のなかに否定語を二つつけているのが、教科書的にはよろしくないのです。
これに関しては、文法的には正しくないけれど若者が不満をぶちまける汚い英語としては、リアリティがある……というふうな評が一般的だと思いますが、疑いの目でみると、これもやはり演出なのではないかということになってきます。先述したように、ミック本人は非常にきれいな英語を使う人です。それがわざと汚い英語を使ってみせるのは、ある種の“演出”であることは否定できないでしょう。
そういうことがあるので、人がローリング・ストーンズというバンドに接する際には複雑な距離感が生じます。
特に、音楽評論家などといった人種の場合にはそれが顕著で、評論家がストーンズを論じると、やたらとややこしい衒学的ともみえる論理を展開しがちです。あれこれ調べたりしたうえでストーンズについて何か言おうとすると、どうしてもそうなってしまうのです。
ミックの形成したストーンズ幻想――
それが独り歩きし、いつしかミック・ジャガーという人物、そしてローリング・ストーンズというバンドの実像をつかめないぐらいに肥大化してしまっている。人がストーンズを見るとき、幾重ものフィルターを通してその姿を見ることになり、そこにはもはや虚像しか見えない……
これはもう、本人たちにもどうしようもないことでしょう。
本当のローリング・ストーンズを、誰も知らない。本人たちでさえ……
ただまあ、ストーンズというのは結局音楽をやるバンドなので、余計な予備知識なしに、その音楽を聴いて、リスナーがどう感じるか……最終的にはそれがすべてです。
というわけで、最後は動画を。
記事中に出てきた「サティファクション」。
The Rolling Stones - (I Can't Get No) Satsfaction (Live) - OFFICIAL
そして、やはり初期の代表曲である Jumpin' Jack Flash。
これは結構若いころの動画ですね。
The Rolling Stones - Jumpin' Jack Flash (Live) - OFFICIAL
最後に、「イッツ・オンリー・ロックンロール」のPV。
The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It) - OFFICIAL PROMO
たかがロックンロール。だけど俺はそいつが好きなんだ――結局は、そういうことかもしれません。