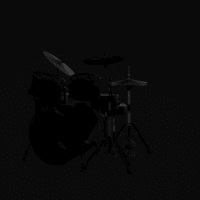今回は、音楽記事です。
なぜだか、最近の記事は死去した人物ということを軸にして書くことが多くなっていますが……
今回も、その流れは続きます。
登場するのは、Dead Kennedys。
去年の暮れに書いた記事で、ドラムのDHペリグロが死去したという話を書きました。
そして、先日のAudioslave
の記事では、ロックにおける「原初の炎」の一つに、デッド・ケネディーズの名が出てきていました。
この流れで、そろそろ登場してもらってもいいでしょう。
去年の記事でDHペリグロについて書いた際、アメリカはパンクにとって不毛の地だ、と書きました。
はじめに、そのあたりのことをもう少し書いておきましょう。
この点はたぶん、日本と近いところがあると思われます。
イギリスのような階級社会と違って、一介の労働者であることに、ある種の尊厳が認められている。ゆえに、UKパンクのようなむき出しの怒りというかたちにならないということです。
そのため、アメリカのパンクは、別の装いをもたなければならなかった。だいたいの場合は、ちょっとアートな方向というのが目だったんじゃないでしょうか。先日トム・ヴァーラインが死去したという話がありましたが、テレビジョンもそうでしょう。ヴァーラインというステージネームはフランスの詩人ヴェルレーヌを英語読みしたものですが、“フランスの詩人”なんかが出てくる感じが、アートなわけです。
このヴェルレーヌという人は、太宰治が処女作『晩年』の冒頭でその詩の一節を引用していることでも知られます。「選ばれてあることの恍惚と不安と二つわれにあり」……野良犬の怒りを叩きつけるUKパンクとは真反対にあることがわかるでしょう(もちろんUKパンクにもそういう系統のものはありますが)。
こうしたアート的傾向というのは、たとえばパティ・スミスなんかも同じでしょう。アメリカでは、「労働者階級の怒りとをぶつける」という方向性が封じられているがゆえに、そういう方向に発展せざるを得なかったのです。
そんなアメリカにあって、怒りをぶつけるパンクをやってきたのが、デッド・ケネディーズです。
そのためには、音楽的なスキルだけでなく、ある種のクレバーさが要求されます。労働者の怒りということを直接いってもぴんとこないので、隠蔽された搾取の構造を問題にするところからはじめなければならない。そういうラディカルな主張を、ラディカルな音楽に載せ、かつ、偽悪と諧謔でコーティングする……デッド・ケネディーズは、それを成し遂げうる稀有な存在だったのです。そして、これだけのアーティストでありながらあくまでもアングラカルトバンドの域を出ないというのが、つまりアメリカがパンクにとって不毛の地であることの証明でもあるのです。
代表曲の一つとして、California Über Alles の動画を載せておきましょう。
Dead Kennedys - "California Über Alles" (Live - 1979)
Über Allesとは、かつてのドイツ国歌の一節で「ドイッチュラント・ユーベル・アーレス」=「世界に冠たるドイツ」というふうに使われていました。それを、「世界に冠たるカリフォルニア」としているわけです。
もとの言葉はナチ時代にそのスローガンのようになり、第二次大戦後ドイツ国歌から削除されたといういわくつきのフレーズ。
それをカリフォルニアとして使ったのは、ジェリー・ブラウンを批判するという意図から。
このジェリー・ブラウンという人は、ロック史上にちょくちょく名前が出てくる政治家です。そのジェリー・ブラウンを、ヒトラーになぞらえて批判しているわけです。こういうタイトルからしても、ラディカルさは伝わってくるでしょう。
パンクというからには、やっぱりこれぐらいのことはやってほしいわけです。
しかし、この域に達すると、アングラバンドであることを余儀なくされる……そこが、アメリカはパンクにとって不毛の地であるということであり、日本とも共通していると感じられる部分なのです。