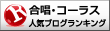岩見沢東高校合唱部OB,21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」会員の横山琢哉君が、現在イタリア(ボローニア)で開催されている「国際合唱指揮者コンクール」(http://www.marieleventre.it/it/index.html)に挑戦中です。昨日(12日夕方)、「予選通過しました。とりあえず報告まで。」の連絡がありました。私からは「まずはおめでとう!早々に退散することにならなくて良かったね(笑)」と返信しました。12日、13日(現地時間)に本選があります。
高等学校では近年、札幌地区において合唱部が増えつつある。この傾向が全道各地に波及して欲しいものである。現状では、吹奏楽部はあるが合唱部は無いという学校が圧倒的に多いようである。高等学校では、ほとんどの学校が一校に音楽教師は一人である。したがって、音楽教師が吹奏楽を担当すると合唱部までは手が届かないことになる。そのような悩みを抱えている学校もあるが、悩む以前に端から合唱部のことは念頭に無い(あきらめている)学校が多いように思える。吹奏楽の存在を否定するものではないが「音楽の原点は歌うことにあり」を忘れずに、ささやかでも良いから“歌う集団”を育てて欲しいものである。
合唱と吹奏楽が両立し、両者が健全に活動を続けている学校もある。現状では、たくさんあるとまでは言えないが大変喜ばしいことである。両部並立共存している学校では、ほとんどがそれぞれの部に顧問がつき一人二役の例は少ないようである。一人一役でも大変なのだから当然であろう。その場合、どちらかは音楽担当教師以外の先生が顧問になる。そして、音楽教師以外の先生が合唱部を担当して大活躍している例が多くなっている。高校の部活動として合唱や吹奏楽が育つためには大変良いことであり、もっともっと全道各地で同様な動きが出ることを期待したい。
ちなみに、札幌市内の小学校で熱心に合唱指導をされている先生方の多くが以前は吹奏楽をやっていた人である。もちろん、その逆(合唱から吹奏楽へ)の例もある。決して不思議なことではなくて、むしろ当然あって然るべきことである。東海大学付属第四高等学校の井田先生は偉大な吹奏楽指導者である。彼が昔から取り入れている練習方法の一つ、しかも特に力を入れている練習に“歌うこと”がある。新曲の最初は自前の声で歌うことから始める。そして、定期演奏会では合唱部顔負けとも言えるような合唱ステージがある。「歌が音楽の原点」なのである。
『小学校に合唱があり、中学校でも合唱が出来る。そして、高等学校へ行っても合唱部がある。歌いたい人はどこへ行っても歌える、合唱が出来る。』そのような社会を創りたい、が8703の願いである。
合唱と吹奏楽が両立し、両者が健全に活動を続けている学校もある。現状では、たくさんあるとまでは言えないが大変喜ばしいことである。両部並立共存している学校では、ほとんどがそれぞれの部に顧問がつき一人二役の例は少ないようである。一人一役でも大変なのだから当然であろう。その場合、どちらかは音楽担当教師以外の先生が顧問になる。そして、音楽教師以外の先生が合唱部を担当して大活躍している例が多くなっている。高校の部活動として合唱や吹奏楽が育つためには大変良いことであり、もっともっと全道各地で同様な動きが出ることを期待したい。
ちなみに、札幌市内の小学校で熱心に合唱指導をされている先生方の多くが以前は吹奏楽をやっていた人である。もちろん、その逆(合唱から吹奏楽へ)の例もある。決して不思議なことではなくて、むしろ当然あって然るべきことである。東海大学付属第四高等学校の井田先生は偉大な吹奏楽指導者である。彼が昔から取り入れている練習方法の一つ、しかも特に力を入れている練習に“歌うこと”がある。新曲の最初は自前の声で歌うことから始める。そして、定期演奏会では合唱部顔負けとも言えるような合唱ステージがある。「歌が音楽の原点」なのである。
『小学校に合唱があり、中学校でも合唱が出来る。そして、高等学校へ行っても合唱部がある。歌いたい人はどこへ行っても歌える、合唱が出来る。』そのような社会を創りたい、が8703の願いである。