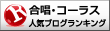これまで「悪癖」という言葉を何度か使って来ましたが、このあたりで何が「悪癖」なのかを考えてみたいと思います。8703が指揮者、もしくは顧問として、まず頭に浮かんだのが「サボり(休み)癖」です。これは心がけの問題ですが、合唱部員として最も信頼できるのは「黙々と、特別なことが無い限り休むことなく練習に参加する人」です。反面、少しは歌う力があっても「休み癖を持つ部員」は困り者とさえ言えます。この稿の冒頭でも述べたように、部員一人ひとりが掛け替えの無い存在であり、チームの一員としての自覚と責任を持った行動が期待されます。
実技面での「悪癖」の典型は我流です。たとえば、ある程度合唱経験がある人で、合唱に適さない発声(我流)が身についている人と、初心者で「発声のことなど考えたこともありません」という人が同時にレッスンを始めた場合、初心者のほうが素直に、順調に育つことが多いようです。もちろん、個人差はありますが、ある程度の期間(長ければ長いほど頑固)に身についた我流(悪癖)を是正することは大変です。くどいようですが、あらためて基礎基本を正しく習得することの重要性を確認して下さい。
具体的に「悪癖」の例を挙げてみます。まずは姿勢です。これは目で見て確認できることなので、みなさん想像してみてください。いかにも良い声で良い歌が歌えていそうな人の姿勢と、そうではない人の姿勢です。後者の例として思い浮かぶのは「猫背で首が曲がり、顎が出ていて、腕が前」、これは丁度、動物園のチンパンジーを彷彿とさせる様な姿勢です。「スックと真っ直ぐ」のイメージとは全く違います。まさかそんな姿勢で歌う人はいないと思うかもしれませんが、それに近い姿で歌っている人もいます。ぜひ「人の振り観て自分も観てください」。くれぐれも「悪癖」が身につかないようにチエック、チエックです。
次は「上体の力み」です。「力み」とは「脱力」の反意語になりますが、いかに脱力するかがとても重要であり、難しい課題と言えます。
「力み」というのは、必要が無い時に、必要でない所に力が入ることです。具体的に上から、舌、顎、首、肩、胸(おへそから上)などです。これらは全て、歌唱においては余計な力が入ってはいけない箇所です。そして、ほとんど連動しています。たとえば、舌(舌根)に力が入ると、顎や首にも力が入り、いわゆる「のど声」になります。肩に力が入ると胸も硬くなり、伸びやかな声にはなりません。ここで、唯一「力を入れてよし」と言える箇所は、吸気から呼気に向かっている時の下腹部(おへそより下、いわゆる丹田)であり臀部(お尻)です。
実技面での「悪癖」の典型は我流です。たとえば、ある程度合唱経験がある人で、合唱に適さない発声(我流)が身についている人と、初心者で「発声のことなど考えたこともありません」という人が同時にレッスンを始めた場合、初心者のほうが素直に、順調に育つことが多いようです。もちろん、個人差はありますが、ある程度の期間(長ければ長いほど頑固)に身についた我流(悪癖)を是正することは大変です。くどいようですが、あらためて基礎基本を正しく習得することの重要性を確認して下さい。
具体的に「悪癖」の例を挙げてみます。まずは姿勢です。これは目で見て確認できることなので、みなさん想像してみてください。いかにも良い声で良い歌が歌えていそうな人の姿勢と、そうではない人の姿勢です。後者の例として思い浮かぶのは「猫背で首が曲がり、顎が出ていて、腕が前」、これは丁度、動物園のチンパンジーを彷彿とさせる様な姿勢です。「スックと真っ直ぐ」のイメージとは全く違います。まさかそんな姿勢で歌う人はいないと思うかもしれませんが、それに近い姿で歌っている人もいます。ぜひ「人の振り観て自分も観てください」。くれぐれも「悪癖」が身につかないようにチエック、チエックです。
次は「上体の力み」です。「力み」とは「脱力」の反意語になりますが、いかに脱力するかがとても重要であり、難しい課題と言えます。
「力み」というのは、必要が無い時に、必要でない所に力が入ることです。具体的に上から、舌、顎、首、肩、胸(おへそから上)などです。これらは全て、歌唱においては余計な力が入ってはいけない箇所です。そして、ほとんど連動しています。たとえば、舌(舌根)に力が入ると、顎や首にも力が入り、いわゆる「のど声」になります。肩に力が入ると胸も硬くなり、伸びやかな声にはなりません。ここで、唯一「力を入れてよし」と言える箇所は、吸気から呼気に向かっている時の下腹部(おへそより下、いわゆる丹田)であり臀部(お尻)です。