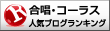誤審と言えば、スポーツで審判の判定について話題になることがある。音楽の世界ではほとんど聞かない言葉であるが、はたして、合唱コンクールにおいて誤審は無いのか?先日、某コンクールの結果を聴いて、某有名人が「あれは明らかに誤審です」と断言した。しかし、あくまでも個人の見解であって、スポーツのように写真、ヴィデオ等の資料が後押しするようなことは無い。あるとすれば録音となるが、録音では生で聞く臨場感等は判断できないので絶対的資料にはなり得ないのである。音楽の場合は、あくまでも、聞く人それぞれのの判断で審査し、それを集計して結果が出る。したがって、「誤審」と断言できるような客観的資料とか根拠はありえないのである。しかし、聞いた人が「???」と思う審査結果はある。聞いた人個々人の中にもそれぞれ審査結果があり、しかも千差万別なのだから当然である。それがコンクールなのだ!願わくば「出来るだけ客観性の高い結果」を期待するのみである。
上記のようなことを前提にして、8703自らが(演奏者として)体験したコンクールにおいて、個人的に「あれは誤審だ」と信じている事例が2件ある。
その一は、昭和55年の北海道合唱コンクール、庄司 寛部長、部員84名、札幌教育文化会館(?)、自由曲は「都会」からであった。(全校生800名中の部員84名は圧巻であった)
その二は、昭和60年の北海道合唱コンクール、横山琢哉部長、部員78名、函館市民会館、自由曲は「オンゴーオー二」であった。(3年連続全国大会出場を断たれ、翌61年春に8703は岩東を去った)
あくまでも、個人的思い込みの世界であるが、「金賞、全国大会出場!」という場面より、「何故、どうして?」と落胆した場面の方が強烈な印象として残っている。だから、「誤審」と信じたいのかもしれない。あの頃の連中はどうしているであろうか?音信有る無し様々だが、懐かしくもほろ苦い思い出である。
上記のようなことを前提にして、8703自らが(演奏者として)体験したコンクールにおいて、個人的に「あれは誤審だ」と信じている事例が2件ある。
その一は、昭和55年の北海道合唱コンクール、庄司 寛部長、部員84名、札幌教育文化会館(?)、自由曲は「都会」からであった。(全校生800名中の部員84名は圧巻であった)
その二は、昭和60年の北海道合唱コンクール、横山琢哉部長、部員78名、函館市民会館、自由曲は「オンゴーオー二」であった。(3年連続全国大会出場を断たれ、翌61年春に8703は岩東を去った)
あくまでも、個人的思い込みの世界であるが、「金賞、全国大会出場!」という場面より、「何故、どうして?」と落胆した場面の方が強烈な印象として残っている。だから、「誤審」と信じたいのかもしれない。あの頃の連中はどうしているであろうか?音信有る無し様々だが、懐かしくもほろ苦い思い出である。