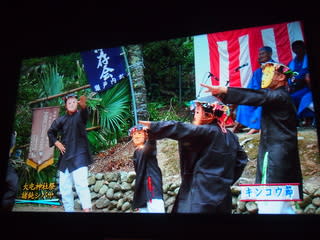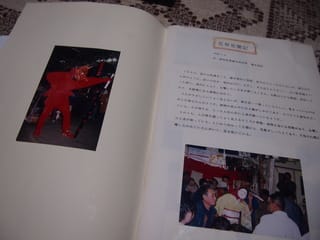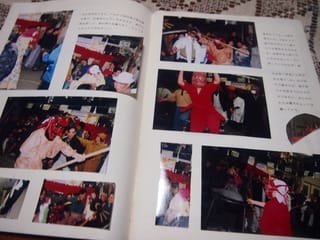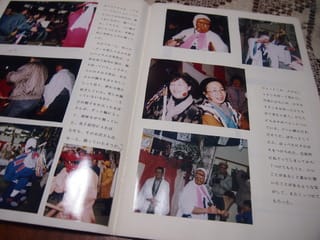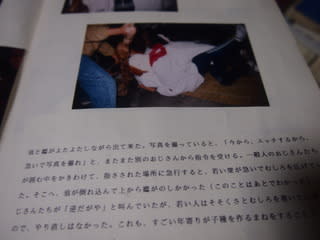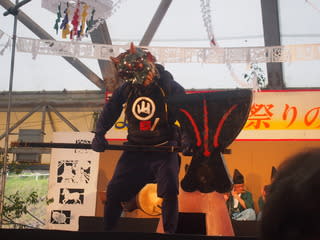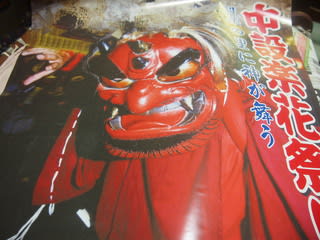しびらんか最後の朝食には、なり味噌が出ました。救荒食として食べられていたソテツの実。毒出しして粉にしたものを味噌に混ぜているものだと思うのですが、こちらはかなり砂糖を入れてピーナッツまで入っている甘い贅沢な食べ物になっています。市販されているものだというので、帰りにお土産に買いました。甘すぎて、まだ冷蔵庫に残っています。

薩川から瀬相港に向かう途中。俵小学校の前には山羊が草を食んでいました。

昔は、山羊を飼っている家は多かったのではないかしら。

瀬相港。フェリーがつくと、観光客というより年配の女性が何人も下船。みな手に花束を持っています。どうやら墓参りらしい。先祖崇拝の盛んなこの地では、月に2回、決まった日に墓参りする習慣があるそうです。地元に住んでいるならできないことはないでしょうが、近ごろは遠くに移住した人も多いので、墓参りがままならなくなったそう。それでもまだ、フェリーでわざわざやってくる人たちがいるようです。そういえば、道すがら見たあちこちの立派なお墓には、生花が供えられていました。花が枯れるか枯れないかのうちに、次の墓参りをするのでしょう。

車の運転、とくに狭いところでの縦列駐車とかバックが苦手の私。今回の旅で最も心配だったのが、フェリーの中の決められたわずかな場所にちゃんと車を入れられるかどうかでした。でも、私同様、心配していた友人が結局難なく、行きも帰りも入れてくれました。
加計呂麻島をあとにして、古仁屋港に。港の河口付近にかかっている橋。

古仁屋から、まず、瀬戸内町の西の端へ。途中、マネン崎展望台に立ち寄りました。

そのあと、ヤドリ浜へ。こちらの海岸は広い。でも、加計呂麻の浜のどこでも拾えたサンゴが、ここは皆無。

そこからさらに西に進み、ホノホシ海岸へ。

ガイドブックで見た、この丸い石に惹かれて訪ねました。丸くてすべすべの石、持って帰りたいところでしたが、ここは禁止。

この海岸は、太平洋に面しています。だから、加計呂麻島の静かな海岸とは様相が違います。

ホノホシ海岸の駐車場のある場所は広い公園になっていて、一面白いイソギクが咲いていました。

ノギクやミヤコワスレに似ていますが、絶滅危惧種なのだそう。

移植したのか、イソギクだけを残したのか、きれいに手入れされています。

でも、「ハブ注意」の立て看が。ぎょっとします。
ホノホシ海岸を後にして、一路奄美の中心地名瀬へ。行きとほぼ同じ道をたどったので、長いトンネルをいくつも通過しました。
1時間半ほどで名瀬に。街らしい街ではありますが、人も車もさほど多くはありません。この日の宿はゲストハウス。私も友人もゲストハウスに泊まるのは初めて。1泊3000円という安さに惹かれて選んだのですが、部屋のドアを開けてびっくり。全面ベッドしかない!
夕食は、加計呂麻島で知り合った方に勧められた「かずみ」へ。島唄が聞けて、島の郷土料理が食べられるお店です。予約した時間に間があったので、商店街を散策しました。こちらも、そんなににぎわっていません。広い間口のリサイクルショップに入ってみました。値段を見ておどろきました。なにもかも、高いのです。そういえば、加計呂麻の人たちからも、物価は高い、と聞いていました。離島だからなのでしょう。たぶん、最低賃金は低いと思うので、普通に暮らすのは厳しそうです。

こちらが「かずみ」の料理のほんの一部。次々に盛りだくさんの量が出てきました。カウンター越しに見える、女将のかずみさんと娘さん二人の仕事の手早さがすごい。

ツワブキの煮もの。フキのように筋を取って煮たものです。筋を取るのに二時間かかったと、女将さん。さて、この女将・かずみさんは島唄の歌い手の第一人者だそう。島では、島唄の歌手のことを「唄者」というようです。

この日も、お客の所望に応じて何曲か歌ってくれました。揚げ物をする手を休めないまま、太い、響きのある独特の節回しで歌いだし、居合わせたお客を魅了。三線を弾く男性に合わせて、お客として来ていたちょっと年配の女性も歌い出しました。

こちらの男性は、本職の三線弾き語りらしく、滑らかな口調で次々島唄を紹介しながら歌ってくれました。島唄は、沖縄民謡とは少し違う、もっと哀調をおびているような印象を受けました。

そのうち、たぶんチヂンという名の太鼓を順番にお客に持たせて、三線の男性のリードで叩くという趣向がはじまりました。最初に持たされたのが私たち。打楽器をたたくのはひさしぶりで、楽しかった。そして最後は、全員立って踊りが始まりました。踊る、というのも久々で、なんだか気分爽快。奄美最後の夜がこうして終わりました。

薩川から瀬相港に向かう途中。俵小学校の前には山羊が草を食んでいました。

昔は、山羊を飼っている家は多かったのではないかしら。

瀬相港。フェリーがつくと、観光客というより年配の女性が何人も下船。みな手に花束を持っています。どうやら墓参りらしい。先祖崇拝の盛んなこの地では、月に2回、決まった日に墓参りする習慣があるそうです。地元に住んでいるならできないことはないでしょうが、近ごろは遠くに移住した人も多いので、墓参りがままならなくなったそう。それでもまだ、フェリーでわざわざやってくる人たちがいるようです。そういえば、道すがら見たあちこちの立派なお墓には、生花が供えられていました。花が枯れるか枯れないかのうちに、次の墓参りをするのでしょう。

車の運転、とくに狭いところでの縦列駐車とかバックが苦手の私。今回の旅で最も心配だったのが、フェリーの中の決められたわずかな場所にちゃんと車を入れられるかどうかでした。でも、私同様、心配していた友人が結局難なく、行きも帰りも入れてくれました。
加計呂麻島をあとにして、古仁屋港に。港の河口付近にかかっている橋。

古仁屋から、まず、瀬戸内町の西の端へ。途中、マネン崎展望台に立ち寄りました。

そのあと、ヤドリ浜へ。こちらの海岸は広い。でも、加計呂麻の浜のどこでも拾えたサンゴが、ここは皆無。

そこからさらに西に進み、ホノホシ海岸へ。

ガイドブックで見た、この丸い石に惹かれて訪ねました。丸くてすべすべの石、持って帰りたいところでしたが、ここは禁止。

この海岸は、太平洋に面しています。だから、加計呂麻島の静かな海岸とは様相が違います。

ホノホシ海岸の駐車場のある場所は広い公園になっていて、一面白いイソギクが咲いていました。

ノギクやミヤコワスレに似ていますが、絶滅危惧種なのだそう。

移植したのか、イソギクだけを残したのか、きれいに手入れされています。

でも、「ハブ注意」の立て看が。ぎょっとします。
ホノホシ海岸を後にして、一路奄美の中心地名瀬へ。行きとほぼ同じ道をたどったので、長いトンネルをいくつも通過しました。
1時間半ほどで名瀬に。街らしい街ではありますが、人も車もさほど多くはありません。この日の宿はゲストハウス。私も友人もゲストハウスに泊まるのは初めて。1泊3000円という安さに惹かれて選んだのですが、部屋のドアを開けてびっくり。全面ベッドしかない!
夕食は、加計呂麻島で知り合った方に勧められた「かずみ」へ。島唄が聞けて、島の郷土料理が食べられるお店です。予約した時間に間があったので、商店街を散策しました。こちらも、そんなににぎわっていません。広い間口のリサイクルショップに入ってみました。値段を見ておどろきました。なにもかも、高いのです。そういえば、加計呂麻の人たちからも、物価は高い、と聞いていました。離島だからなのでしょう。たぶん、最低賃金は低いと思うので、普通に暮らすのは厳しそうです。

こちらが「かずみ」の料理のほんの一部。次々に盛りだくさんの量が出てきました。カウンター越しに見える、女将のかずみさんと娘さん二人の仕事の手早さがすごい。

ツワブキの煮もの。フキのように筋を取って煮たものです。筋を取るのに二時間かかったと、女将さん。さて、この女将・かずみさんは島唄の歌い手の第一人者だそう。島では、島唄の歌手のことを「唄者」というようです。

この日も、お客の所望に応じて何曲か歌ってくれました。揚げ物をする手を休めないまま、太い、響きのある独特の節回しで歌いだし、居合わせたお客を魅了。三線を弾く男性に合わせて、お客として来ていたちょっと年配の女性も歌い出しました。

こちらの男性は、本職の三線弾き語りらしく、滑らかな口調で次々島唄を紹介しながら歌ってくれました。島唄は、沖縄民謡とは少し違う、もっと哀調をおびているような印象を受けました。

そのうち、たぶんチヂンという名の太鼓を順番にお客に持たせて、三線の男性のリードで叩くという趣向がはじまりました。最初に持たされたのが私たち。打楽器をたたくのはひさしぶりで、楽しかった。そして最後は、全員立って踊りが始まりました。踊る、というのも久々で、なんだか気分爽快。奄美最後の夜がこうして終わりました。