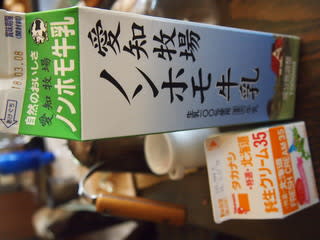しばらくまえになりますが、暮らしの学校でいとカフェのクラフトコーラづくりの教室を受講しました。
イベントでしばしばご一緒するいとカフェさんは、豊田市駅近くのカレー屋さん。カレーもとてもおいしいのですが、イベントで私がよくいただくのが、スパイス入りの飲み物いろいろ。特にスパイスコーラは、スパイスが効いていて、味も香りもいい。この春お店での講座に参加する予定だったのが、covid-19の感染拡大防止のため中止に。残念におもっていたところ、暮らしの学校で、夏に続き二回目の講座が9月に開催されると知り、すぐに申し込みました。

いとカフェさんが用意したスパイスは20種類以上。免疫力アップブレンドとデトックスブレンド、二つの推奨モデルのうちどちらかをえらび、各自お皿に取ります。

わたしが選んだのはデトックスブレンド。カルダモン、オールスパイス、クローブ、シナモン、ジャンジャー、ナツメグほか10種類にプラスして、この実でレモングラスとレモンバームを足しました。
彼がブレンドしたコーラの粉~甜菜糖とキビ砂糖他主要のスパイスが入っているものを水で溶かし、少し煮てからスパイスとハーブ類を一気に入れます。冷めたら要してきた瓶に入れ、完了。

水や炭酸で薄めるほか、牛乳や豆乳で薄めてもおいしいそう。わたしは、外での作業後、水で薄めてちびちび飲んでいます。あと少しでなくなるので、シロップを入れてもう一度楽しみたいと思います。
焼き菓子づくりやそのほか料理に使おうと思って買ったスパイスの残りが、結構あるので、あと数種買い揃えたら、このコーラ、簡単に作れそう。自分なりのブレンドもしてみたい。でも、問題はバニラ。いとカフェさんによればバニラがあるとコーラっぽくなるのだそうですが、このところバニラの値段が急騰して、わたしはお菓子には一切使わなくなりました。バニラを入れずに、体に良くておいしいスパイスコーラ風飲料はできないものでしょうか。試してみたいとおもいます。
イベントでしばしばご一緒するいとカフェさんは、豊田市駅近くのカレー屋さん。カレーもとてもおいしいのですが、イベントで私がよくいただくのが、スパイス入りの飲み物いろいろ。特にスパイスコーラは、スパイスが効いていて、味も香りもいい。この春お店での講座に参加する予定だったのが、covid-19の感染拡大防止のため中止に。残念におもっていたところ、暮らしの学校で、夏に続き二回目の講座が9月に開催されると知り、すぐに申し込みました。

いとカフェさんが用意したスパイスは20種類以上。免疫力アップブレンドとデトックスブレンド、二つの推奨モデルのうちどちらかをえらび、各自お皿に取ります。

わたしが選んだのはデトックスブレンド。カルダモン、オールスパイス、クローブ、シナモン、ジャンジャー、ナツメグほか10種類にプラスして、この実でレモングラスとレモンバームを足しました。
彼がブレンドしたコーラの粉~甜菜糖とキビ砂糖他主要のスパイスが入っているものを水で溶かし、少し煮てからスパイスとハーブ類を一気に入れます。冷めたら要してきた瓶に入れ、完了。

水や炭酸で薄めるほか、牛乳や豆乳で薄めてもおいしいそう。わたしは、外での作業後、水で薄めてちびちび飲んでいます。あと少しでなくなるので、シロップを入れてもう一度楽しみたいと思います。
焼き菓子づくりやそのほか料理に使おうと思って買ったスパイスの残りが、結構あるので、あと数種買い揃えたら、このコーラ、簡単に作れそう。自分なりのブレンドもしてみたい。でも、問題はバニラ。いとカフェさんによればバニラがあるとコーラっぽくなるのだそうですが、このところバニラの値段が急騰して、わたしはお菓子には一切使わなくなりました。バニラを入れずに、体に良くておいしいスパイスコーラ風飲料はできないものでしょうか。試してみたいとおもいます。