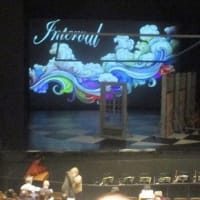10月24日(土)午後、池袋の豊島区立生活産業プラザで第37回教科書を考えるシンポジウム「特別な教科『道徳科』の学習指導要領『解説』を読み解く」が開催された。
安倍政権が積極的に推進した道徳科が「特別の教科」として教科化され、今年3月には学習指導要領が改訂され、7月に「解説」も公表された。
来年には小学校の「道徳科教科書」の検定が行われる。しかしまだ具体的な内容や授業、評価がさっぱりわからない状況なので注目度が高い。この日は小学校から高校までの教員、道徳推進教師に任命されている方、大学で道徳教育研究を担当されている方など多数が参加した。60人ほどの比較的小さい部屋だったせいもあるが、満席で座れない人もいるくらいの盛況だった。
講師は世取山洋介さん(新潟大学)と吉田典裕さん(出版労連)の2人だった。
世取山さんの講演は、「子ども観」や「発達観」にまで立ち戻り、この指導要領「解説」のように「教育」すると子どもの自律的な良心形成は根絶やしにされるという恐ろしい結論だったので紹介する。
学習指導要領『解説』は、吉田さんの説明によると、指導要領に比べ分量が多く道徳科の場合ページ数で22倍、字数で41倍もある。しかし読んでもよくわからない。法的拘束力はないはずなのに、「正しい解釈」(有権解釈)なのでこれに従えと文科省はいうし、教科書作りでも事実上のガイドラインになっているもの、とのことだ。
「道徳科」の学習指導要領「解説」を検討する
世取山 洋介さん(新潟大学)

1 道徳の教科化をめぐる法制論
「特別の教科」として道徳が設定された。これは、2006年に第一次安倍政権が成立させた新教育基本法2条に掲げる約20の徳目が基本になっている。この徳目を内面化することが国民としてもつべき必要な資質であるとする。
20の徳目は4つに分類できる。1 主として自分自身に関すること、2 主として人とのかかわりに関すること、3 主として、生命や自然、崇高なものとのかかわりに関すること、4 主として国や集団とのかかわりにかんすること、である。ここで気づくのは、自分の周囲の同心円ということなら3と4は逆である。人間の力を超えたものとして崇高なものがあるはずなのに、それを包括するものとして人間がつくった国家が置かれる。神のうえに国家が立つ。これはグロテスクだ。
1989年以来この構造の学習指導要領だったが、2006年に教育基本法が改訂されたときに道徳だけ条文として格上げされた。戦前、筆頭科目だった道徳と同様に、道徳がすべての教科の上に立つという含意がみられた。そこで教育基本法の国会審議の際、文科省に問いただしたところ「筆頭科目にするつもりはない」と答弁した。ところが2012年の第2次安倍政権で懸念が現実のものとなった。
安倍政権は2つのことを行った。ひとつは学校教育法施行規則を改正して、道徳を「特別の教科」にしたことだ。もうひとつは新教科書検定基準として、すべての科目で2条の道徳の徳目を教えさせることだ。俗ないい方をすると、地学を学んでどうやって郷土への愛を育てるか、あるいは物理を通してどうやって伝統と歴史を尊重する姿勢をつくるかということである。つまりあらゆる教科を通じて、特定の徳目を教育するということになる。
特設道徳の時期とは大違いだ。道徳には対応する学問分野がない。これまで教科書検定の違法性を批判する場合、使われたのは通説準拠主義だった。裁判所も通説から離れていなければ合法としてきた。しかし道徳には通説が存在しないので、国家はどこまででも踏み込むことができる。グロテスクな事態が展開しようとしている。
また評価の問題もやっかいである。これまでは科学的真理を子どもたちがどの程度理解しているかで客観的に評価できた。ところが真理かどうかもわからないものを主観的に評価し、恣意的に子どもの内面を評価しなくてはいけなくなる。教師はそんな訓練は受けていないし、教師の地位と両立するのかどうか。
教師が科学的真理を伝達する専門職から、国家の道徳をたんに配達して教え込む郵便配達人に変っていく可能性が高い。教師の「教育の自由」や教師の地位には決定的なことだ。いっぽう子どもの思想良心の自由にとっても、教師は内面にずけずけ入る危険な存在となる。子どもの自律的な良心形成の自由が侵されることになる。
2 道徳の教科化を支える諸勢力
道徳を教科化した政治的な勢力とはどんなものなのだろうか。わたしは2つあると考える。ひとつは旧文部省以来の「宗教的情操教育派」だ。特定の宗派に偏らないかたちで子どものなかに宗教的な情操心を引き起こすことが教育だとする。日本には政教分離原則があるので、特定の宗教に偏るわけにはいかない。宗教的情操とは、世の中には人間を超えるものがあり人間は絶対的に服従しなくてはならないという意味合いだ。絶対的力への帰依を利用して国家統合を図ることがねらいで、文部省は1959年以来50年以上にわたり、一貫してそれをやり続け、89年の学習指導要領は彼らなりの回答だった。
2番目は経済界の「グローバル人材」育成派である。海外への企業進出を支えるエリートづくりのため道徳が必要だと考え、国際的でありながら日本の利益を最優先し、しかも外国人と仲よくなりながらも彼らを搾取することをいとわないような人間をグローバル人材だとする。たとえば戦前の南満州鉄道のエリート人材がそれに当たる。インターナショナルでありながらナショナルで、二面性をもつエリート。一方日本国籍の多国籍企業の海外進出に熱狂する国民づくりも目指す。これが学校教育ではたしてできるのか。教育政策以上に文化政策が重要になる。近い将来出てくるだろう。現在はまだ体系的議論はできていないので、指導要領では宗教的情操教育派が圧倒している。
最後に戦争法案ができたので、志願兵制度を支える「兵士づくり」派が必ず出てくるはずだ。いまはまだ姿がみえない。
3 「解説」を読むための下地
人格や良心について、わたくしはヴィゴツキーの心理学的定義を採用する。人格とは、外界の認識に関する固有の統合の形であり、そのうえで良心とは外界の認識に関する固有の統合の形に基づき個々人が自らつくった自らの行動を律する真善美に関する基準である。人間の力を超えたものの命令に従うのでなく、自ら独自の良心を形成し、それに従って行動することができることを前提として教育する。良心は自分の行動を律する点にポイントがある。宗教的情操のような絶対的権威を離れ自分の良心をつくれることが画期的である。社会と自然に関する科学的認識を自分のなかに内面化し、さまざまな実践をとおして基準はますます複雑化するという構造をもつ。特設道徳はそういう道を開くものだった。
たとえば陶芸家は自分の美の基準に合わなければ作品をぶっこわし、次にどうするか考え最終的に自分の基準に合うものをつくり出す。これが非宗教的、世俗的な良心形成のモデルである。
伝統的な見方として、子どもはもともと非合理的に生まれついているので、非合理的なものを子どもから追い出す、追い出す方法が教育で、そのときに大人(教師)の権威により追い出す、非合理的なものを合理的なものから追い出すという見方が根強くあった。これをどう克服するか。
対抗する見方として、子どもは生まれつき主体性をもつ。外界に働きかけて応答を引き出し、内面化することで外界を変容させる力がある。子どもの主体性を軸にして、人格を保存しながら人格への新しい要素をその上に統合することによって新しい人格をつくりあげていく、このプロセスを発達とみる見方である。
この対抗的な見方の含意として「あなたのやったことはダメなことだけど、あなたは悪くないよ」と、人格と行為を区別する。こういう叱り方はわれわれがすでに多くやっている。しかし伝統的な見方では、悪いことをやったのだから人格も悪い。だから人格をまるごと変えなさいということになる。
4「解説」(小学校)を読む
では今回の解説はどうなっているのだろう。第1章総則で「人格の完成及び国民の育成の基盤となるものが道徳性」(1p)とし「道徳教育においては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を前提に」(1p)と、はじめから畏敬の念、すなわち人間の存在を超えたものを上位におき道徳教育の基礎に宗教的情操があることを示している。しかも今回初めに述べた徳目のなかの宗教と国家の順を入れ替え、宗教を最後にした(4p)。宗教的情操を軸に道徳教育全体を構成している。
「第2章道徳教育の目標」では、「価値理解」「人間理解」「他者理解」という枠組みを設定し、人間理解では「道徳的価値は大切であってもなかなか実現することができない人間の弱さなども理解すること」(16p)、他者理解では「道徳的価値を実現したり,実現できなかったりする場合の感じ方,考え方は一つではない,多様であるということを理解すること」(17p)と書いている。彼らがいう多様性は、道徳的価値を実現するうえで、強い精神をもつか、弱い精神をもつかということだ。
「第3章道徳科の内容」で要となる「主として生命や自然,崇高なもの」について、「生命の尊さ」「感動、畏敬の念」「よりよく生きる喜び」から構成されるが、「よりよく生きる喜び」について、「人間は決して内在する弱さをそのままにはしておく存在ではなく,弱さを羞恥として受け止め,それを乗り越え誇りを感じることを通して,生きることへの喜びを感じる」(68p)と書く。この部分だけものすごく力が入っていておどろおどろしい。キーワードは「羞恥」だ。恥は、人格を隠したいときや捨てたいときに使う言葉だ。
子どもが道徳的価値を達成できなかったとき、教師は子どもに「あなたは弱い。恥じろよ!」と指導しろということだ。つまり人格を入れ替えろというメッセージである。いちばんわかりやすいイメージは特攻隊だ。死への恐怖をのりこえ、強い人間になる。死をいとわない忠義の強さ、弱さを克服し強くなるのが特攻だ。
今回の学習指導要領解説は、教科の要として道徳があり、道徳の要として宗教的情操心があり、これをもとに子どもの良心形成すべてをコントロールする。できなかったときには恥を感じさせ人格を入れ替えることを子どもにわからせるという構造になっている。したがってこの道徳教育では、非科学的になり、非歴史的になり、かつ反発達的にならざるをえない。子どもの自律的な良心形成は根絶やしにされる。
われわれには真理性や科学性を軸に教育政策に対抗してきた重要な舞台がある。これに「発達」を加えてさらに大きくする必要がある。いま、子どもの発達の見方の深部が問われている。
この後、吉田典裕さんの「学習指導要領『解説』は必要なのか」という講演があった。「解説」の説明、調査官が「解説」を活用するので教科書づくりの事実上のガイドラインになっていること、道徳科には根拠となる学問分野や科学分野がないので他の教科のような検定ができないのに「指導方法や教材については研究があるからできる」などと、はじめから「強弁とこじつけ」をしていること、検定基準・同実施細則を一部変更しいったん不合格になると次年度にならないと申請できなくなったこと、などが述べられた。
この日のシンポジウムは、質疑応答・討議が3回に分け合計1時間も時間がとれたので、道徳性や子ども観、発達観、徳目に人権や思想・良心の自由も入れるべきこと、「私たちの道徳」や道徳教科書の検定、使用義務、成績評価の問題などさまざまな角度から質問や意見が出た。
わたくしには現場の先生方の意見が興味深かった。高校教員の方から「ふだん頭髪や服装などの規律を正す指導をしている。結果として生徒が落ち着いて授業を受けられるようになった。それを道徳の授業のときだけ『多様な価値観がある』と教えるのは矛盾を感じ悩む。若い教員は『規律正しく授業を受けろ』というほうがすっきり通るという。ここに教科書が入ってくると『このとおりにやれ』というマニュアル教育になってしまう」と語った。それに対し小学校の先生から「だからこわいのだ。マニュアルどおりなら楽だが、自分で判断できない子どもが増える危険性がある。ものいわぬ国民づくりになることは明らかだ。楽に流れてはいけない。のたうち回りながら子どもたちとなにが正しいのか考えることを選ぶべきだ」との発言があった。またこれに関連して、大学教員から道徳律をみんなでどうつくるか、それをどうやったらつくれるか議論できる能力をつくる、これが道徳教育でやるべきことではないかという意見があった。
たいへんまじめなシンポジウムだった。
最後に、司会から道徳教育については批判だけでは勝負にならない、対案を出すべきである。また子どもをどう見るのかという子ども観が基礎になる、とのしめくくりの言葉があった。
安倍政権が積極的に推進した道徳科が「特別の教科」として教科化され、今年3月には学習指導要領が改訂され、7月に「解説」も公表された。
来年には小学校の「道徳科教科書」の検定が行われる。しかしまだ具体的な内容や授業、評価がさっぱりわからない状況なので注目度が高い。この日は小学校から高校までの教員、道徳推進教師に任命されている方、大学で道徳教育研究を担当されている方など多数が参加した。60人ほどの比較的小さい部屋だったせいもあるが、満席で座れない人もいるくらいの盛況だった。
講師は世取山洋介さん(新潟大学)と吉田典裕さん(出版労連)の2人だった。
世取山さんの講演は、「子ども観」や「発達観」にまで立ち戻り、この指導要領「解説」のように「教育」すると子どもの自律的な良心形成は根絶やしにされるという恐ろしい結論だったので紹介する。
学習指導要領『解説』は、吉田さんの説明によると、指導要領に比べ分量が多く道徳科の場合ページ数で22倍、字数で41倍もある。しかし読んでもよくわからない。法的拘束力はないはずなのに、「正しい解釈」(有権解釈)なのでこれに従えと文科省はいうし、教科書作りでも事実上のガイドラインになっているもの、とのことだ。
「道徳科」の学習指導要領「解説」を検討する
世取山 洋介さん(新潟大学)

1 道徳の教科化をめぐる法制論
「特別の教科」として道徳が設定された。これは、2006年に第一次安倍政権が成立させた新教育基本法2条に掲げる約20の徳目が基本になっている。この徳目を内面化することが国民としてもつべき必要な資質であるとする。
20の徳目は4つに分類できる。1 主として自分自身に関すること、2 主として人とのかかわりに関すること、3 主として、生命や自然、崇高なものとのかかわりに関すること、4 主として国や集団とのかかわりにかんすること、である。ここで気づくのは、自分の周囲の同心円ということなら3と4は逆である。人間の力を超えたものとして崇高なものがあるはずなのに、それを包括するものとして人間がつくった国家が置かれる。神のうえに国家が立つ。これはグロテスクだ。
1989年以来この構造の学習指導要領だったが、2006年に教育基本法が改訂されたときに道徳だけ条文として格上げされた。戦前、筆頭科目だった道徳と同様に、道徳がすべての教科の上に立つという含意がみられた。そこで教育基本法の国会審議の際、文科省に問いただしたところ「筆頭科目にするつもりはない」と答弁した。ところが2012年の第2次安倍政権で懸念が現実のものとなった。
安倍政権は2つのことを行った。ひとつは学校教育法施行規則を改正して、道徳を「特別の教科」にしたことだ。もうひとつは新教科書検定基準として、すべての科目で2条の道徳の徳目を教えさせることだ。俗ないい方をすると、地学を学んでどうやって郷土への愛を育てるか、あるいは物理を通してどうやって伝統と歴史を尊重する姿勢をつくるかということである。つまりあらゆる教科を通じて、特定の徳目を教育するということになる。
特設道徳の時期とは大違いだ。道徳には対応する学問分野がない。これまで教科書検定の違法性を批判する場合、使われたのは通説準拠主義だった。裁判所も通説から離れていなければ合法としてきた。しかし道徳には通説が存在しないので、国家はどこまででも踏み込むことができる。グロテスクな事態が展開しようとしている。
また評価の問題もやっかいである。これまでは科学的真理を子どもたちがどの程度理解しているかで客観的に評価できた。ところが真理かどうかもわからないものを主観的に評価し、恣意的に子どもの内面を評価しなくてはいけなくなる。教師はそんな訓練は受けていないし、教師の地位と両立するのかどうか。
教師が科学的真理を伝達する専門職から、国家の道徳をたんに配達して教え込む郵便配達人に変っていく可能性が高い。教師の「教育の自由」や教師の地位には決定的なことだ。いっぽう子どもの思想良心の自由にとっても、教師は内面にずけずけ入る危険な存在となる。子どもの自律的な良心形成の自由が侵されることになる。
2 道徳の教科化を支える諸勢力
道徳を教科化した政治的な勢力とはどんなものなのだろうか。わたしは2つあると考える。ひとつは旧文部省以来の「宗教的情操教育派」だ。特定の宗派に偏らないかたちで子どものなかに宗教的な情操心を引き起こすことが教育だとする。日本には政教分離原則があるので、特定の宗教に偏るわけにはいかない。宗教的情操とは、世の中には人間を超えるものがあり人間は絶対的に服従しなくてはならないという意味合いだ。絶対的力への帰依を利用して国家統合を図ることがねらいで、文部省は1959年以来50年以上にわたり、一貫してそれをやり続け、89年の学習指導要領は彼らなりの回答だった。
2番目は経済界の「グローバル人材」育成派である。海外への企業進出を支えるエリートづくりのため道徳が必要だと考え、国際的でありながら日本の利益を最優先し、しかも外国人と仲よくなりながらも彼らを搾取することをいとわないような人間をグローバル人材だとする。たとえば戦前の南満州鉄道のエリート人材がそれに当たる。インターナショナルでありながらナショナルで、二面性をもつエリート。一方日本国籍の多国籍企業の海外進出に熱狂する国民づくりも目指す。これが学校教育ではたしてできるのか。教育政策以上に文化政策が重要になる。近い将来出てくるだろう。現在はまだ体系的議論はできていないので、指導要領では宗教的情操教育派が圧倒している。
最後に戦争法案ができたので、志願兵制度を支える「兵士づくり」派が必ず出てくるはずだ。いまはまだ姿がみえない。
3 「解説」を読むための下地
人格や良心について、わたくしはヴィゴツキーの心理学的定義を採用する。人格とは、外界の認識に関する固有の統合の形であり、そのうえで良心とは外界の認識に関する固有の統合の形に基づき個々人が自らつくった自らの行動を律する真善美に関する基準である。人間の力を超えたものの命令に従うのでなく、自ら独自の良心を形成し、それに従って行動することができることを前提として教育する。良心は自分の行動を律する点にポイントがある。宗教的情操のような絶対的権威を離れ自分の良心をつくれることが画期的である。社会と自然に関する科学的認識を自分のなかに内面化し、さまざまな実践をとおして基準はますます複雑化するという構造をもつ。特設道徳はそういう道を開くものだった。
たとえば陶芸家は自分の美の基準に合わなければ作品をぶっこわし、次にどうするか考え最終的に自分の基準に合うものをつくり出す。これが非宗教的、世俗的な良心形成のモデルである。
伝統的な見方として、子どもはもともと非合理的に生まれついているので、非合理的なものを子どもから追い出す、追い出す方法が教育で、そのときに大人(教師)の権威により追い出す、非合理的なものを合理的なものから追い出すという見方が根強くあった。これをどう克服するか。
対抗する見方として、子どもは生まれつき主体性をもつ。外界に働きかけて応答を引き出し、内面化することで外界を変容させる力がある。子どもの主体性を軸にして、人格を保存しながら人格への新しい要素をその上に統合することによって新しい人格をつくりあげていく、このプロセスを発達とみる見方である。
この対抗的な見方の含意として「あなたのやったことはダメなことだけど、あなたは悪くないよ」と、人格と行為を区別する。こういう叱り方はわれわれがすでに多くやっている。しかし伝統的な見方では、悪いことをやったのだから人格も悪い。だから人格をまるごと変えなさいということになる。
4「解説」(小学校)を読む
では今回の解説はどうなっているのだろう。第1章総則で「人格の完成及び国民の育成の基盤となるものが道徳性」(1p)とし「道徳教育においては,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を前提に」(1p)と、はじめから畏敬の念、すなわち人間の存在を超えたものを上位におき道徳教育の基礎に宗教的情操があることを示している。しかも今回初めに述べた徳目のなかの宗教と国家の順を入れ替え、宗教を最後にした(4p)。宗教的情操を軸に道徳教育全体を構成している。
「第2章道徳教育の目標」では、「価値理解」「人間理解」「他者理解」という枠組みを設定し、人間理解では「道徳的価値は大切であってもなかなか実現することができない人間の弱さなども理解すること」(16p)、他者理解では「道徳的価値を実現したり,実現できなかったりする場合の感じ方,考え方は一つではない,多様であるということを理解すること」(17p)と書いている。彼らがいう多様性は、道徳的価値を実現するうえで、強い精神をもつか、弱い精神をもつかということだ。
「第3章道徳科の内容」で要となる「主として生命や自然,崇高なもの」について、「生命の尊さ」「感動、畏敬の念」「よりよく生きる喜び」から構成されるが、「よりよく生きる喜び」について、「人間は決して内在する弱さをそのままにはしておく存在ではなく,弱さを羞恥として受け止め,それを乗り越え誇りを感じることを通して,生きることへの喜びを感じる」(68p)と書く。この部分だけものすごく力が入っていておどろおどろしい。キーワードは「羞恥」だ。恥は、人格を隠したいときや捨てたいときに使う言葉だ。
子どもが道徳的価値を達成できなかったとき、教師は子どもに「あなたは弱い。恥じろよ!」と指導しろということだ。つまり人格を入れ替えろというメッセージである。いちばんわかりやすいイメージは特攻隊だ。死への恐怖をのりこえ、強い人間になる。死をいとわない忠義の強さ、弱さを克服し強くなるのが特攻だ。
今回の学習指導要領解説は、教科の要として道徳があり、道徳の要として宗教的情操心があり、これをもとに子どもの良心形成すべてをコントロールする。できなかったときには恥を感じさせ人格を入れ替えることを子どもにわからせるという構造になっている。したがってこの道徳教育では、非科学的になり、非歴史的になり、かつ反発達的にならざるをえない。子どもの自律的な良心形成は根絶やしにされる。
われわれには真理性や科学性を軸に教育政策に対抗してきた重要な舞台がある。これに「発達」を加えてさらに大きくする必要がある。いま、子どもの発達の見方の深部が問われている。
この後、吉田典裕さんの「学習指導要領『解説』は必要なのか」という講演があった。「解説」の説明、調査官が「解説」を活用するので教科書づくりの事実上のガイドラインになっていること、道徳科には根拠となる学問分野や科学分野がないので他の教科のような検定ができないのに「指導方法や教材については研究があるからできる」などと、はじめから「強弁とこじつけ」をしていること、検定基準・同実施細則を一部変更しいったん不合格になると次年度にならないと申請できなくなったこと、などが述べられた。
この日のシンポジウムは、質疑応答・討議が3回に分け合計1時間も時間がとれたので、道徳性や子ども観、発達観、徳目に人権や思想・良心の自由も入れるべきこと、「私たちの道徳」や道徳教科書の検定、使用義務、成績評価の問題などさまざまな角度から質問や意見が出た。
わたくしには現場の先生方の意見が興味深かった。高校教員の方から「ふだん頭髪や服装などの規律を正す指導をしている。結果として生徒が落ち着いて授業を受けられるようになった。それを道徳の授業のときだけ『多様な価値観がある』と教えるのは矛盾を感じ悩む。若い教員は『規律正しく授業を受けろ』というほうがすっきり通るという。ここに教科書が入ってくると『このとおりにやれ』というマニュアル教育になってしまう」と語った。それに対し小学校の先生から「だからこわいのだ。マニュアルどおりなら楽だが、自分で判断できない子どもが増える危険性がある。ものいわぬ国民づくりになることは明らかだ。楽に流れてはいけない。のたうち回りながら子どもたちとなにが正しいのか考えることを選ぶべきだ」との発言があった。またこれに関連して、大学教員から道徳律をみんなでどうつくるか、それをどうやったらつくれるか議論できる能力をつくる、これが道徳教育でやるべきことではないかという意見があった。
たいへんまじめなシンポジウムだった。
最後に、司会から道徳教育については批判だけでは勝負にならない、対案を出すべきである。また子どもをどう見るのかという子ども観が基礎になる、とのしめくくりの言葉があった。