
久しぶりに先生の講座に参加して、箱根で撮影をしてきた。
箱根に長安寺というお寺があり、そこの庭には500羅漢像が置かれている。
今回初めてその寺を訪れた。
素晴らしかった。
今年は紅葉らしい紅葉を楽しんでなかったので、本当にありがたかった。

500羅漢を今ざっと調べてみると、ブッダが亡くなった後の第1回、第4回仏典編集会議に集まった500人の弟子たちのことを指すという。
しかし、第1回はブッダがなくなってすぐだし、第4回の結集は紀元前1世紀とされているので、この2回の結集の間には400年近い年月が流れており、同一人物ではなく500羅漢というのは象徴的な存在(つまりブッダの高弟たちのこと)を言うのではないかと思う。

この胸にある赤い落葉は偶然あの場所にあったもの。僕が置いたのではない。見たときラッキーだと思った。
羅漢はもともと阿羅漢から来ており、その語源はサンスクリット語のarhatの漢訳である。ブッダの高弟を指すことから、煩悩をすべて断滅した境地に達した人を言う。
今回は三脚を久しぶりに使うことから、それに慣れることに意識が集中してしまい、先生のご指導も上の空で、自分の撮りたい羅漢像を好きにとっていた。まさに不肖の弟子である。
三脚はやはり面倒くさい。いままではほぼすべてといっていいくらい手持ちでの撮影だった。

手振れの危険性は多々あるのでシャッタースピードと撮影姿勢にだけは注意しながらとっていた。
しかし、ここのところよく見る海外のユーチューバーの風景写真動画を見るうちに、自分も長時間露光や暗いところでの撮影に備えてそろそろ三脚を使うことになれる必要があるということと、風景写真のプロの先生の講座を受けるのに、三脚なしで参加するのはいくらなんでも失礼ではないか、といおもいから急遽1昨日三脚を買った次第。
手振れの心配がなくなるというのは確かにいいが、周りの人を気にしながら急いで三脚を据えて撮影するというのは結構骨が折れた。
しかしそれもなれるだろう。
写真を初めて約10年以上がたち、ようやく今頃、その世界の奥広さ、面白さ、に気づき始めてきた。英語では学びが遅い人のことをSlow developerというみたいだが、まさに自分はその典型だろう。

心配だった天気も良く、富士山も曇り空ではあったがよく見えた。
ただ、先生いわく、少し小雨ぐらいが紅葉や石像を撮るには一番いいというし、まぁ僕もその通りだと思う。雨が風物につやを塗ってくれるからだ。いわば天然のコーティングをしてくれるようなものである。

何気に僕の気にいっている羅漢様
500羅漢に話は戻るが、やはり、共感できる羅漢とそうでない羅漢がいる。
それはみんな同じだろうと思う。共感できる羅漢には、これからも折に触れてこの寺に戻ってきて、あぁ、また会いましたね、と心の中で話しかけるのではないか。

500羅漢について考えていて、何かそれにちなんだ仏典からの引用はないかと探したら、ちょうど大パリニッバーナ経というブッダの最後の旅を記録した経典にブッダ自身の言葉としてこんな記述があった。
ブッダがいよいよ亡くなるというとき、彼の周りには500人の修行僧が集まっていた。死期がまじかいことをを悟っているブッダは彼らを前にして自分が生きている間に聞いておきたいことはないか、と問いかけた。しかし誰も質問するものはなかった。
アーナンダ(仏弟子)はそれを見て、誰も法に関してもう聞くことはないほどの境地に達しています、とブッダに申し上げた。それを聞いてブッダは次のように言う。
『アーナンダよ、お前はきよらかな信仰からそのように語る。ところが修行完成者(ブッダ)には、こういう智がある。
〈この修行僧の集いにおいては、ブッダに関し、あるいは法に関し、あるいは集いに関し、あるいは実践に関して、一人の修行僧にも、疑い、疑惑が起こっていない。
この500人の修行僧のうちの最後の修行僧でも、聖者の流れに入り、退堕しないはずのものであり、必ず正しいさとりに達する〉と。』
そこで尊師(ブッダ)は修行僧たちに告げた。――
『さあ、修行僧たちよ、お前たちに告げよう。[もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成なさい]と。』
これが修行を続けてきた者の最後の言葉であった。』

これは同じ経典の全く別の場面でだが、ブッダがガンジス川を渡るシーンで語る言葉である。
ブッダはガンジス川を「この世界」そして渡り切った向こう岸を仏教における最終到達地点であるニルヴァーナ(涅槃と漢訳されている)に喩えて次のように語っている。
『次いで尊師はガンジス河におもむいた。~中略~ある人々は船を求めている。ある人々は(大きな)筏(いかだ)を求めている。またある人々は(小さな)筏を結んでいる。いずれもかなたの岸辺にいこうと欲しているのである。
~中略~ついで尊師は、或る人々が船を求め、或る人々は筏を求め、或る人々はいかだを結んであちらとこちらへ往き来しようとしているのを見た。
そこで尊師はこのことを知って、そのときこの感興のことばをひとりつぶやいた。
〈沼地に触れないで、橋をかけて、(広く深い)海や湖を渡る人々もある。
(木切れや蔓草を)結びつけて筏をつくって渡る人々もある。
聡明な人々は、すでに渡り終わっている。〉』
原始仏典を読んでいていつも思い、そして心大いに動かされるのは、これらの言葉が「あのブッダその人」がじきじきに本当に発した言葉である可能性が極めて高いことである。
もちろんそれらの経典が書かれてすでに2000年以上もたっているのだから、絶対にブッダのことばだとは言い切れない。でも、ブッダの死後チベットや中国を伝わってきた仏典は翻訳をした人の恣意的な「意訳」「誤訳」なかには完全な創作、がかなり濃厚に入っているだろう。
ましてや、ブッダ入滅後500年、1000年以上たってから書かれた仏典は、「仏典」とは言ってもそれはもうブッダその人の思想とはかなり離れていて、ブッダの教えというよりは「その経典を書いた人の教え、思想」である。しかも、それらはそれらの経典を書いた人より前に書かかれた経典をもとにしている。その前に書かれた経典も、そのさらに前に書かれた経典をもとにして書かれている……いや、そもそもそれはその人だけの考えであり、その考えもさらにその前の人の独自の考えをもとにしている、そしてその前の人の独自の考えも、その前の前の前の人の独自の考えをもとに書かれている……
言葉を変えれば、2000年以上の歳月をかけてインドからこの東アジアに伝わってきた「伝言ゲーム」になっているといってもいい……
いったいブッダは本当にそんなことを言ったのか?それはあなたがあなたの前に書かれたものを参考にして言っていることなんじゃないの?そしてあなたの前に書かれたものは、さらにその前に書かれたものを参考にしている、そしてそのまえのまえにかかれたものも、その前の前の前に書かれたものを参考にして書かれている………
いったいブッダは本当にそんなことを教えていたのですか?本当にそんなことを説いていたのですか?
僕が知りたいのは、「あの偉大なブッダ」その人が何を言ったか、何を教えたか、何を説いたのか、である。
そういうことを考えていると、ブッダの教えを直接じかに聞いた500人の阿羅漢たちがほんとうにうらやましいと思うのだ。
そういう僕を迎えながら、長安寺にいる阿羅漢たちはただただ様々な表情、しぐさで、僕をはぐらかし、叱咤し、諭してくる。











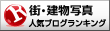
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます