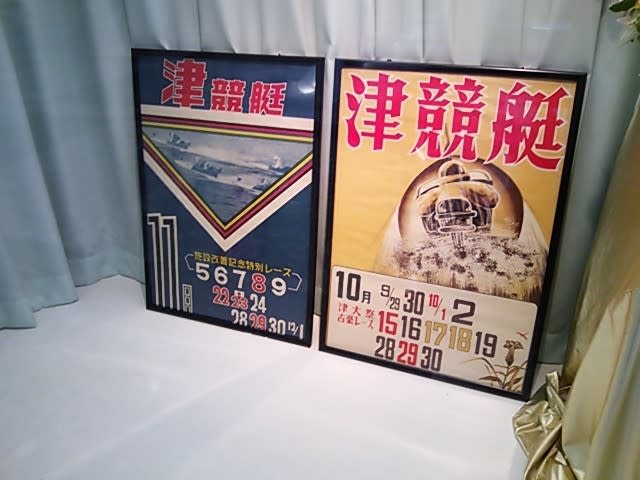ほんの手すさび、手慰み。
不定期イラスト連載、第百六弾は「古(いにしえ)のエジプト女性」。

世界史の授業で習った、古代「四大文明」の舞台とされている場所は、
いずれも大河流域である。
水の恵みを活かした農耕や牧畜によって営みが安定し、多少のゆとりを手に入れてこそ、
人知が進み、精神的、物質的に生活が豊かになり「文明」が生まれる。
中でも“ナイルの賜”と呼ばれる「古代エジプト」のそれは、つとに有名だ。
太陽の運行を基準にした暦(こよみ)。
ピラミッドに代表される、土木建築技術。
数学と統計学。
象形文字(ヒエログリフ)。
英語のPAPERの語源になったパピルス。
中央集権と官僚、租税制度。
死後の世界観とミイラ。
思いつくまま幾つもの例が挙がり、高度に発達していた事が分かる。
今から5,000年以上昔へ思いを馳せるのは、歴史の醍醐味。
人々はどんな暮らしをしていたのか興味が湧く。
特に、女性はさぞ美人だったに違いない。
壁画などで見かけるように、アイライン・アイシャドーの類で目の周りを縁取り、
日常的に香油を嗜んでいたそうだ。
それは、砂漠地帯の強い陽射しを和らげるため、乾燥から肌を護るためといった、
必要性に迫られての側面もあるそうだが、
目鼻立ちが際立ち、いい香りのする女性は、何とも魅力的である。
叶うなら、お目にかかってみたいものだ。
人は衣食足りて礼節を知り、美が宿る。
不定期イラスト連載、第百六弾は「古(いにしえ)のエジプト女性」。

世界史の授業で習った、古代「四大文明」の舞台とされている場所は、
いずれも大河流域である。
水の恵みを活かした農耕や牧畜によって営みが安定し、多少のゆとりを手に入れてこそ、
人知が進み、精神的、物質的に生活が豊かになり「文明」が生まれる。
中でも“ナイルの賜”と呼ばれる「古代エジプト」のそれは、つとに有名だ。
太陽の運行を基準にした暦(こよみ)。
ピラミッドに代表される、土木建築技術。
数学と統計学。
象形文字(ヒエログリフ)。
英語のPAPERの語源になったパピルス。
中央集権と官僚、租税制度。
死後の世界観とミイラ。
思いつくまま幾つもの例が挙がり、高度に発達していた事が分かる。
今から5,000年以上昔へ思いを馳せるのは、歴史の醍醐味。
人々はどんな暮らしをしていたのか興味が湧く。
特に、女性はさぞ美人だったに違いない。
壁画などで見かけるように、アイライン・アイシャドーの類で目の周りを縁取り、
日常的に香油を嗜んでいたそうだ。
それは、砂漠地帯の強い陽射しを和らげるため、乾燥から肌を護るためといった、
必要性に迫られての側面もあるそうだが、
目鼻立ちが際立ち、いい香りのする女性は、何とも魅力的である。
叶うなら、お目にかかってみたいものだ。
人は衣食足りて礼節を知り、美が宿る。