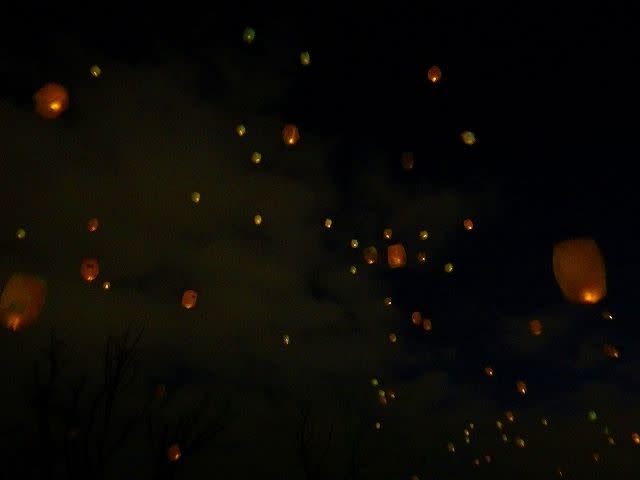2020年7月12日に白老町に開業した、「ウポポイ(民族共生象徴空間)」。本来は4月24日に開業が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2回の延期を経てのオープンとなった。
同施設の「愛称」であるウポポイとはアイヌの言葉で「(おおぜいで)歌うこと」を意味するといい、2018年に一般公募によって決定した。民族共生象徴空間という名称は、閣議決定された内容に基づいている。
オンラインでの予約が必要で、その説明や手続きが非常に煩雑で面倒だった。なんとかチケット(一人1200円)は取れたが、PCやスマホがない人はどうするのか? また、チケットのほかに、博物館の入場時間の予約も必要とのことだったが、その手続きが良く分からなかった。しかし、チケットがあれば何とかなるだろうと思って、開業時刻の9時に間に合うように行った。

8:30に、広大な駐車場(500円)に入り、開業時間を待った。入場料を払うのに、駐車料金はいささか不満である。マスクをし忘れたら、駐車場の係員に注意された。
8:50には、開門された入口を通り、北海道の景観をコンクリート壁に彫った長い回廊を通って受付へ。その手前には、新型コロナ感染対策(検温・消毒)の建物を通るようになっていた。

当日受付のチケット売り場もあった。ネット予約の段階で良く分からなかった時間予約の必要な博物館は、すでに昨日段階で18:00と19:00しか空いていなかったとのこと。その日の内なら再入場も可能とのことなので、18:00に予約を入れてもらった。夜はプロジェクションマッピングも観られる。

広大な土地にいろいろな施設があり、それぞれの施設ごとの催し物のプログラムのタイムテーブルがあるので、マップとタイムテーブルは必携で、それを見ながら、回らなければならない。
しかも、新型コロナ感染対策で、人数制限があり、それぞれの整理券を、その時間の前に施設ごとにもらわなければならない。
18:00まで待たなければならない博物館と、それに合わせて17:30からの短編アニメを除いて一通り見て歩いたら、昼食を入れて14:00になった。各施設ごとの入場時間までの待ち時間も結構多い。14:00からは、外には出ずに、駐車場の車の中で、自分はブログ書き、妻は昼寝をして時間つぶしをした。
そんなこともあり、時系列ではなく、各施設ごとのプログラムを中心に紹介したい。なお、雨天だったので、屋外ステージのプログラムは、夜のプロジェクションマップ以外は、すべて中止となった。
◎国立民族博物館

入口の正面にあるメイン施設。2階の博物館は、予約時間の18:00でないと入場できない。

1階部分のお土産コーナーをまず見て回る。

シアターは、いつでも入れるので、9:15に、まずはそこからスタート。上映は「アイヌの歴史と文化」で、ちょうど良いオリエンテーションになった。
以下は、18:00の予約時間に入館した博物館内



「基本展示室」は、「ことば」、「世界」、「くらし」、「歴史」、「しごと」、「交流」の6つのテーマをアイヌ民族の視点で紹介。「特別展示室」は、アイヌ文化、先住民族文化についての調査・研究の成果等を紹介。また、これら以外のテーマについても幅広く扱い、多様な展覧会を開催されている。
◎工房

ここでは、伝統工芸の実演が観られる。

木彫の実演見学

織物の実演見学。
◎伝統的コタン

一番手前の干している緑色の植物は、蓙にするガマの茎。その隣は建築中のチセ。

ポロチセ(大きなチセ)の内部

和人との交易で手に入れた貴重な漆器等。

担当者がセンの木をくり貫いて作ったという丸木船。アイヌは川が道路のようなものだから、移動の手段には欠くことのできないものだった。
◎体験交流ホール

ここでは、ステージ上での伝統芸能上演、短編映画上映、夜に屋外プロジェクションマッピングショーが観られる。

伝統芸能上演は、撮影禁止なので、パンフレットから借用。
上は、11:30から観た「イノミ~アイヌの歌、躍り、語り」~伝統的儀礼「イヨマンテ」を軸にしたストーリー性のある舞踊と映像。
下は、13:30から観た「シノッ~アイヌの祈り、歌、躍り」~伝統的な歌や躍り、楽器演奏などを最新の映像技術や北海道の美しい映像を取り入れて紹介。

17:30から観た短編アニメ「カムイを射止めた男の子」と「キツネに捕まった日の神」※これも撮影禁止なのでパンフから。


土日祝日のみの夜の屋外プロジェクションマッピングショー「カムイシンフォニア」
◎体験学習館

ここでは、楽器の演奏観賞、ポン劇場等、ドーム型スクリーン映像体験ができる。

ドーム型スクリーン映像体験館。一人一人の目の前に、「カムイ アイズ」という、ワシの目とキタキツネの視線で撮影した、北海道の自然が写し出される。
ポン(小さな)劇場の紙人形劇では、アイヌの料理のことが演じられていた。楽器は、体験交流ホールでの伝統芸能で見たのでパス。
◎フードコートでの昼食

上は、ウポポイ野菜ラーメン。下は、ぎょうじゃにんにくいりザンギカレー(共に、790円+税)
結局、駐車場の車の中での時間も含めて、全部見終わったら、19時過ぎになってしまった。ほかのブログで「6時間半もいた」と書かれていたが、自分も正味同じくらいの時間になった。
このあと、室蘭の道の駅に泊まるべく戻る途中、虎杖浜温泉に入って、ブログを完成して投稿を試みた。しかし、なぜか、昼に途中まで書いた部分以外は、いくら書いても消えてしまう。諦めて「明日アップします」とだけ書いたものをアップした。
◎ 昨日のブログ投稿の不調は、スマホではなく、この無料のgooブログの容量に達してしまったことが原因だった→有料ブログへ移行

最近になって、このブログの画像フォルダの容量が、無料ブログの容量に近くなっていたので、近いうちに、有料に切り替えなくてはならないと思っていた。
昨夜に書き足したものが、投稿に反映されないで、消えてしまうのは、これまで経験のないトラブルだった。画像フォルダの使用容量はまだわずかながら余裕があると思っていたが、これに文章部分の容量も加えると、すでに限界容量の3GBに達したせいかもしれない。
帰宅後、直ちに、有料ブログへの移行手続きを取ったら、スムーズに書き上げることができ、公開することができた。有料(税込月524円)に移行すると、1TBまで使用できる。無限に近い容量である。また、広告も入らないので見やすくなるはず。



































































































 ゴジラの雪像と氷像の手
ゴジラの雪像と氷像の手













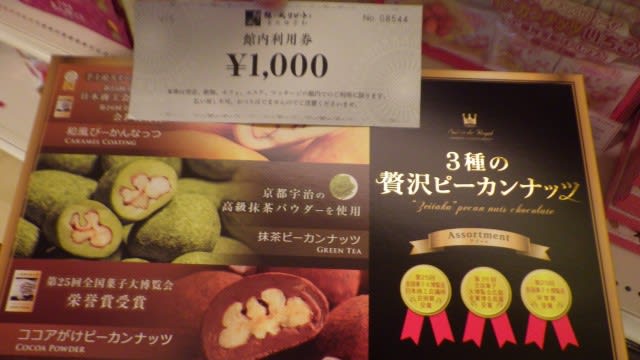 館内利用券1000円で買ったお菓子。
館内利用券1000円で買ったお菓子。