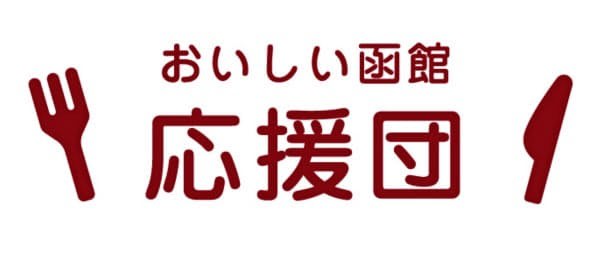今日も朝から雨が降り続き、最高気温10℃までしか上がらず、寒い1日だった。これで、4日連続ポータブルストーブを点け放しである。
今回は、ベイエリアから、緑の島の入口前を通り、弁天町の西浜岸壁までの「西部臨海通り」に建つ「景観形成指定建築物」ほかを紹介したい。
◎函館大学ベイエリア・サテライト(旧金森船具店)(末広町22-17)<明治44年(1911年)築>

かつて北海道の玄関口であった東浜桟橋に面して建つ、ルネッサンス風の重厚なデザインの建物。そうは見えないが、レンガ造りである。
1階両側の戸袋や2階部分の後退、大きく立ち上げた袖壁など土蔵造町屋の形式をもちながら、正面2階は、三角形のへディメントが施された上げ下げの縦長窓が並び、後退部をベランダとしたことや、袖壁を漆喰仕上げとしているものの、目地を切って石造風にみせ、さらに1階には、2本のトスカナ式鋳鉄柱や大振りな鋳鉄製のブラケットを設けるなど洋風の仕上げとなっている。
2013年(平成25年)4月に設置された、函館大学の教育施設で、観光を題材とした大学生と社会人の共同教育、共同研究の拠点として利用。2018年8月には、イスラム圏のムスリム礼拝所を設置して、一般へ開放している。

◎喫茶JOE(旧遠藤平吉商店)(大町9-14)<明治18年(1805年)築>

東坂と湾岸の大通りの角地にある明治初期の白漆喰と3連アーチが美しい、往時の洒落た雰囲気をしのばせる建物。建築当時は、上海や大連に航路を持つ廻漕店の遠藤吉平商店の店舗。屋根は方形の瓦葺きで、煉瓦壁に白漆喰を塗り、一部には目地を切って石造り風に見せている。1階には大型の3連アーチ、2階には小ぶりな2連アーチ窓を配した洋風建築。3連アーチは鋳鉄製の柱で支えられている。
なお、店名のJOEは、1964(元治元)年に、この建物の前の岸壁から同志社の創設者・新島穣がアメリカへと密航を企てたという場所といわれ、それが店名の由来のようだ。現在は営業はしていないようだ?

営業していたころの画像 ※2016年当時入店したことがあるが、内部の様子は撮影していなかった。
◎港の庵(旧松橋商店)(大町8-26)<明治35年(1902年)築・明治40年ころの説もある>

緑の島入口前に建つ、明治から時空を超えて甦った建物。道路側から煉瓦造、木造、土蔵の3種で構成された、函館の歴史の奥深さを知ることができる大変貴重なもの。当時米穀店と海産商を営んでいた松橋像作によって建てられた。
以降4代にわたって所有者が変わり、解体予定だったものを、2014年に建築当時の姿に復元している。基本的には出資者を中心とした団体の定期食事会で使用しているため、一般公開はされていない。景観形成指定建築物にはなっていないが、復元後、平成27年の「函館市都市景観賞受賞建築物」となっている。

建築当時のままの、玄関上に施された蔦のような植物模様の浮き彫り。これは世紀末に勃発した、アールヌーヴォーのムーブメントの影響を少なからず感じさせるものであるとのこと。
◎函館市臨海研究所(旧函館西警察署庁舎)(大町13-1)<大正15年(1926年)築・平成18年(2006年)復元新築>

建設設当初は、函館市水上警察署として利用が開始され、昭和59年(1984年)まで現役の函館西警察署として使われていたが、平成18年(2006年)に建設当時の工法だった型枠コンクリートブロック造りを用いて復元・新築されている。
建物角部を曲面で仕上げ、そこに正面玄関を配し、角地に建つ建物であることを意識した造りとなっている。玄関両脇の太い4本の柱や縦長の窓など,垂直線を意識したデザインもとり入れ、全体としては、重厚な中にも柔らかさを感じさせる造形に特徴がみらる。屋根の上の物見塔は水上警察署時代の名残り。
◎太刀川家住宅店舗(弁天町15-5)<明治34年(1901年)築・洋館は大正4年(1915年)築>

函館の豪商・太刀川家が経営する太刀川米穀店の店舗として建てられた北海道屈指の和洋折衷の土蔵風商家建築。かつての海岸通の繁栄を伝える商家の一つ。現在はカフェとして再生されているが休業中である。
左右両側に袖壁を備えた店舗は、防火造り商店の代表格となっている。屋根は,寄せ棟の瓦葺で、煉瓦の壁を漆喰で仕上げ、鉄柱で1階梁上の3連アーチを支えている。2階部分が和風の意匠となっている。1階2階とも開口部が広がり、開放的な感じを与える。(国指定重要文化財)
左の洋館は、応接専用室として増築したもので、2階部分の破風や軒下に彫りの深い植物模様が施され、アカンサス葉状のブランケットの彫りも丹念につくられている。これに対して、首の長いコリント式円柱が支持する1階部分のアーチ廻りは平坦な印象を受けるが、竣功当初はスパンドレルや胴部飾り板に唐草模様のレリーフが貼り付けられ、華やかな印象だったと言われている。
太刀川家は越後国(新潟県)長岡出身の初代・太刀川善吉(?~1909)が、函館で米穀商と海産商をはじめたのがその始まり。その経営は順調で、明治中期には函館を代表する実業家になるまでの存在になっている。その頃に初代・善吉が建てたのが、この白漆喰塗りの店舗であった。


◎ロマンティカ・ロマンティコ(旧堤商会)(弁天町15-12)<大正5年(1916年)築>

函館の北洋漁業の一時代を築いた日魯漁業の前身・堤商会事務所として,大正期に建築された木造3階建ての貴重な建物。当初は3階正面にバルコニーと屋根にパラペットを持たせた洒落た建物だったそうだ。現在は、1階にカフェ、2階に物販店、3階に事務所が入っている。
堤商会は、当時30代の堤清六(1880~1931)と平塚常次郎(1881~1973)が明治40年に新潟で発足した漁業会社で、大正2年に函館に移転。前身は、大幸機動興業所社屋で、玄関の上にも「日用雑貨諸道具類販売 佐藤商会」の看板がかかっている。
またこの建物は数年前までは無残な姿だったが、当時の写真を参考に復元されて、現在のような姿になった。また防火対策として、現在の建物の外壁は下見板を模した建材が使われている。これは最近、函館の建物再生によく使われている手法とのこと。

◎今井家所有住宅(弁天町15-10)<明治40年(1907年)築>

上掲の通称ロマロマの隣の角地に建つ建物で,当初は、米穀店と住宅を兼ねて建築されたもので、後ろに蔵もある。
正面の店舗部分は、瓦屋根をもった2階建てで、和風様式となっている。後ろの住宅部分は、平屋と2階建てで、屋根は鉄板葺きで、平屋部分は格子窓で和風、2階建て部分は縦長窓を採用し、洋風意匠となっています。
2018年2月に、「BENTEN CAFE&DINING (弁天カフェ)」としてオープンしたが、現在は休業中のようである。

◎函館クラシックホテルズ藍(旧和島家住宅)(弁天町16-9)<大正4年(1915年)築>

幸坂の電車通りと西部臨海通りの間の道路に面した上下和洋折衷様式の典型的な建物。1階は引き違い戸,堅繁格子の出窓と和風のたたずまい、2階は縦長の上げ下げ窓に井型の桟割が施され、下見板張り、屋根の持ち送り、胴蛇腹などが正面から側面に配置され、洋風のたたずまいとなっている。
◎小森家住宅店舗(弁天町23-14)<明治34年(1901年)築>

現存する上下和洋折衷様式民家(擬洋風民家)の中で最古で、そのルーツとも言われると言われる、数少ない明治30年代の貴重な建物。近年、〔海のアンティークショップ〕としてリニューアルオープンした小森商店だが、当初は、田中仙太郎商店という海産商の建物だったそうである。
一般的な函館の擬洋風民家スタイルであるが、興味深い箇所が幾つかみられるという。まず一つ目が、観音開きになる窓。函館の擬洋風民家および木造洋風建築は、一般的に上げ下げ窓が主流なのだが、このスタイルはかなり珍しいもの。
もう一つは、軒下の持ち送り。この持ち送り軒を支える何気ないパーツではあるが、かっての函館の人達はこの部分に隠れたお洒落というか、かなりの拘りを持っていたようだ。この小森商店もその例にもれない作りなのだが、他とはちょっと様子が違う。とにかく大きい。カラフルに塗られたペンキに翻弄されがちだが、この形は和風の寺社建築などに見られる造形に近いものだといえる。

◎旧野口梅吉商店・わらじ荘(弁天町32-5)<大正2年(1913年)築>

この旧野口梅吉商店は、米穀店として建てられた和洋折衷方式の商家建築だが、2年前の、渡島総合振興局などが取り組む「木づかいプロジェクト」の一環で外観の修繕が行われた。そのときに携わった北海道教育大学函館校の学生4名が、「わらじ荘」と愛称を付けたこの建物に昨年12月から住み始めたことが話題となっている。4月には建物内に私設図書館を開設する予定で、子ども向けの書籍や絵本が多数寄贈されている。
瓦葺の寄棟型に、2階のドイツ式下見板張りに洋風の上げ下げ窓、1階の和風の作りなど、函館擬洋風民家の正統派と言いたくなるようなスタイルが特徴。大正末から昭和初期にかけての函館下見板建築文化のベーシックとも言うべき存在とのこと。
◎旧西浜旅館・ミートハウス別館(弁天町22-14)<明治40年(1907年)築>

西埠頭そばの角地に建つ典型的な上下和洋折衷様式の建物。最大の特徴は、北側のレンガ造りの防火壁(卯建・うだつ)。
戦前は、鉄工所やイカつけ番屋として利用されていたということが、戦後は、旅館・番屋など様々な用途で使われていたという。現在は「ミートハウス」という民宿の別館として使用されている。ちなみに、この民宿は主にバイク旅行者が利用するとのことで、春過ぎになると建物前には宿泊者のバイクがずらりと並ぶ光景がしばしば見られるという。










































 近距離(100km圏内程度)でできるだけ都道府県を跨がない日帰り登山から始めましょう。
近距離(100km圏内程度)でできるだけ都道府県を跨がない日帰り登山から始めましょう。 体調不良(平熱を超える発熱、悪寒、倦怠感、息苦しさ、咳等)での登山は止めましょう。入山後にコロナ感染発症すると命に関わり、救助隊、収容先地元医療機関に多大の迷惑を及ぼします。
体調不良(平熱を超える発熱、悪寒、倦怠感、息苦しさ、咳等)での登山は止めましょう。入山後にコロナ感染発症すると命に関わり、救助隊、収容先地元医療機関に多大の迷惑を及ぼします。 .登山は、少人数で行いましょう。(パーティーは、当面5名以内で。)
.登山は、少人数で行いましょう。(パーティーは、当面5名以内で。) 自粛期間中、季節や地震による山容の変化、登山道の荒廃など思わぬ危険が潜んでいます。十分な登山ルートの下調べと地図、コンパスの持参、登山届けは必ず提出し、家族にも残しましょう。
自粛期間中、季節や地震による山容の変化、登山道の荒廃など思わぬ危険が潜んでいます。十分な登山ルートの下調べと地図、コンパスの持参、登山届けは必ず提出し、家族にも残しましょう。 登山中でもマスクを着用しましょう。マスク着用時は、熱中症及び脱水には十分留意し、こまめに水分摂取を心がけましょう。
登山中でもマスクを着用しましょう。マスク着用時は、熱中症及び脱水には十分留意し、こまめに水分摂取を心がけましょう。 登山、クライミングジムでのソーシャルディスタンスを守りましょう。 一般的には2m前後ですが、登山中の場合は、さらに距離が必要と言われています。また、クライミングジムでは建屋構造、利用人数等で制限がありますので、ジムの指針に従って行動してください。 唖えロープ、滑り止めなどもジムの方針に従ってください。
登山、クライミングジムでのソーシャルディスタンスを守りましょう。 一般的には2m前後ですが、登山中の場合は、さらに距離が必要と言われています。また、クライミングジムでは建屋構造、利用人数等で制限がありますので、ジムの指針に従って行動してください。 唖えロープ、滑り止めなどもジムの方針に従ってください。 登山山域内での買い物や、下山後の呑み会等も地元住民への感染防止の観点から控えてください。食材、飲料、緊急食などは出発前に揃えておきましょう。
登山山域内での買い物や、下山後の呑み会等も地元住民への感染防止の観点から控えてください。食材、飲料、緊急食などは出発前に揃えておきましょう。 自粛中に衰えた筋力、体幹を鍛えましょう。
自粛中に衰えた筋力、体幹を鍛えましょう。