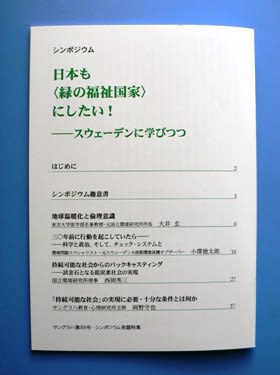大学の後期の授業では、ゴータマ・ブッダから大乗仏教そして唯識と、仏教の話をします。
少し前に「無自性(むじしょう)」という言葉の説明をしました。
「自性」とは、「それ自体の変わることのない本性」というふうな意味です。
私たちは、私自身の変わることのない本性というのがあると思い込んでいるけれど、よく考えて見るとそれは変わるんですよ、という話をします。
例えば、私は私を好きな人にとっては「いい人」という性質があるように見える。ところが私をきらいな人にとっては「いやなヤツ」という性質があると見える。
私の性質は「いい」のか「いやな」のか、その人と私の関係性(縁起)によって変わって見えるのです。
また、最初は「いい人」と思っていたのが、付き合っているうちに「いやなヤツ」に思えてきたり、その逆もあったりで、時間性でも変化します(無常)。
他人にとってだけではなく、その時の気分で、自分自身でも自分の性質は「すばらしい」と思えたり、「だめ」に思えたりします。
そして、だめであっても努力しているとかなりよくなったり、すごくすばらしくなったりもすることができます。変化つまり成長するんですね。
それはともかく、最近、ちょっとスウェーデン漬けで脳味噌までスウェーデン臭くなりそうなので、電車の中での読み物はちょっと味を変えて、黒岩重吾『天風の彩王 藤原不比等』(上下、講談社文庫)を読みました。
私が、黒岩重吾のものを読むと言ったら、意外そうな顔をする方がいます。
何しろ黒岩作品の基本テーマは権力欲や財産欲や性欲でドロドロしているのが人間だということのようですから、「爽やかに生きたい」をモットーとしている私には合わないと思っていただけるようです。
これは、ちょっと善意の誤解というところもありますが、実のところ私も黒岩のテーマが特に好きなわけではないので、現代ものはほとんど読んだことがありません。
そういうテーマで読むのならドストエフスキーです。
しかし、確かに人間にはそういうところも強くあると思うことと、古代史の小説が他にはあまりないので、日本精神史を考えるうえで古代のイメージを描く1つの手がかりとして読んでいるわけです。
『天風の彩王』を読み終わってみて、私の不比等のイメージと黒岩のイメージはまるでといっていいくらい違うなあ、と思いました。
それは、天智天皇、天武天皇などなどについてもすべて同じです(聖徳太子だけはいくらか近いところもありましたが)。
そして仏教、とりわけ唯識を学んでいるので、どちらかが絶対に正しいとは考えません。
すべてのものは「無自性」なので、「唯識(ただ心のあり方しだい)」でまるで違って見えたりするのが当たり前だと思うのです。
『日本書紀』や『続日本紀』などを読む場合も、私はそこに古代のリーダーたちの理想を読み取ることができるのではないかと思って読むので、理想が読めてきます。
しかし、「人間なんてそんなものじゃない。理想なんてウソだ。本心は権力欲や財産欲や性欲ばっかりなんだ」と思って読むと、そうも読めるのです。
私は、どちらが正しいかということより――それは絶対的には決定できないと思いますし――どちらが自分(たち)が生きるのに勇気づけになるかということのほうを大切にしたいと思っています。
しかし、とはいえ、黒岩の古代史作品は今まで読んだものはすべてそれなりに面白く読めました。
ぜひにとは言いませんが、多かれ少なかれ権力欲、財産欲、性欲について身に覚えのある男性諸君には、娯楽として読む分にはけっこうおもしろいですよ、と言っておきます。
これが終わったので、次はまたスウェーデンものになりそうです。
↓いつもクリックしてメッセージの伝達にご協力いただきありがとうございます。
人気blogランキングへ