福島県会津若松市にある会津藩の藩校『日新館』(現在のものは復元されたものです)
江戸時代も中期を過ぎ泰平のなか武士道にもゆるぎが見られる様になった事から
文武両道を学べる学校として1803年に作られたそうです。
会津藩士の子は10歳になると入学する決まりとなっていました。
幕末明治維新の戊辰戦争時には閉校となり
建物は臨時病院として使われ戦争負傷者の治療にあたったそうです。
飯盛山で集団自害した白虎隊の少年剣士達は日新館の生徒達でした。
①日新館正面入り口に向かう階段

②丁度昼頃で弓道の練習をしていた会津の男女の高校生が袴姿で出てきていました。

③南門(日新館正面入り口)

④日新館の『什の掟』(じゅうのおきて)最後の二つを除けば現代の少年にも声を大にして言いたい事です。
「ならぬことは ならぬものです」この強いメッセージが凄いと感じました。

「什とは町内の区域を「辺」という単位に分け、辺を細分して「什」という藩士の子弟のグループに分けた。
什では「什長」というリーダーが選ばれ、什長は毎日、什の構成員の家の座敷を輪番で借りて、
什の構成員を集めて「什の掟」を訓示した、什の掟は7ヶ条からなる。(Wikipediaより抜粋)
⑤戟門 南門を入るとあり、この東側に東塾が西側に西塾と呼ばれる校舎が中庭を囲む様にあります。

⑥寺院ではないのででしょうか?

⑦屋根の鬼瓦の位置にありました。


⑧大成殿 講堂で孔子を祀ってあります。

⑨大成殿の中の孔子像 日新館の教えの元は儒教であった事がうかがえます。

日新館では武道だけでなく医学や天文学なども教授していたようで
授業の様子など人形を置いて当時の様子が説明されていました。
次回にそんな写真を紹介します。
江戸時代も中期を過ぎ泰平のなか武士道にもゆるぎが見られる様になった事から
文武両道を学べる学校として1803年に作られたそうです。
会津藩士の子は10歳になると入学する決まりとなっていました。
幕末明治維新の戊辰戦争時には閉校となり
建物は臨時病院として使われ戦争負傷者の治療にあたったそうです。
飯盛山で集団自害した白虎隊の少年剣士達は日新館の生徒達でした。
①日新館正面入り口に向かう階段

②丁度昼頃で弓道の練習をしていた会津の男女の高校生が袴姿で出てきていました。

③南門(日新館正面入り口)

④日新館の『什の掟』(じゅうのおきて)最後の二つを除けば現代の少年にも声を大にして言いたい事です。
「ならぬことは ならぬものです」この強いメッセージが凄いと感じました。

「什とは町内の区域を「辺」という単位に分け、辺を細分して「什」という藩士の子弟のグループに分けた。
什では「什長」というリーダーが選ばれ、什長は毎日、什の構成員の家の座敷を輪番で借りて、
什の構成員を集めて「什の掟」を訓示した、什の掟は7ヶ条からなる。(Wikipediaより抜粋)
⑤戟門 南門を入るとあり、この東側に東塾が西側に西塾と呼ばれる校舎が中庭を囲む様にあります。

⑥寺院ではないのででしょうか?

⑦屋根の鬼瓦の位置にありました。


⑧大成殿 講堂で孔子を祀ってあります。

⑨大成殿の中の孔子像 日新館の教えの元は儒教であった事がうかがえます。

日新館では武道だけでなく医学や天文学なども教授していたようで
授業の様子など人形を置いて当時の様子が説明されていました。
次回にそんな写真を紹介します。











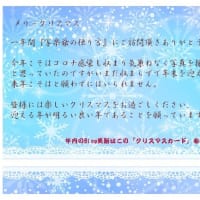








いまさらながら気がついたんですが
儒教って、宗教だったのか
でも皆さん仏教徒だったんですよね
毎日訓示があれば自然に体にしみこんでくると思いました。宗教的な言葉がないので誰でも受け入れやすいし日常生活に欠かせない教えですね。
当時の藩士の子弟たちが過ごした様子なども伺えてなるほどという感じです。
白虎隊のお墓のことぐらいしか覚えていないからここには行かなかったかもしれないです。
建物が美しく見るだけでも価値がありますね。
立派な寺院ですね、手入れも行き届き、
風景の中に、溶け込んでて、美しさを感じます、
狛犬ですよね、獅子に見えますけど、
掟、読みました、いい言葉が並んでて、納得
しています、以外と、日常的に使う言葉なのに、
文字で書いてると、説得力が有ります、
儒教については私も詳しく知りませんし儒教関係の書籍等も呼んだ記憶がありません。
宗教かといえば宗教でもあるでしょう、仏様の教えが仏教なら孔子様の教えが儒教ですからね。
江戸時代は儒教の時代とも言えますがこの場合は宗教とはいえないと思います。
ちなみに皆の知っているところでは、荻生徂徠・新井白石・林羅山など多くの儒学者がいて当時の国(幕府)のあり方に一言ありますよね。
「什の掟」のおきては今で言うなら小学高学年ぐらいの少年に向けての言葉でしょうから分かりやすいのではないでしょうか。
現代の道徳教育には一概に賛成しかねますが、この掟で言われている内容が今一番欠如しているものだと思います。
猪苗代や会津地方は私も何回も行っていますがここは初めてでした、復元されたのが最近ではないかと思います。
孫に昔の学校を見に行くと言ったらあまりのり気ではなかったのですが、飽きずに結構熱心に見学していました。
いえ!ここは寺院ではありません学校ですよ。
獅子の狛犬?がいたり建物の感じなどでは寺院に見えますよね。
ここは野口英世記念館に比べると見学者もすくなく、建物の景色だけでもゆったりした気分になれました。
丘陵に建っているのですか。
凄い構えの建物と什の掟は厳しいようですが大切な教えですね。
ピーンと背筋の張るような教訓、今は無くなりましたね。
暑いですね、外の直射日光が当たらない場所では涼しい風が吹いているのですが。
家の中ではエアコン着けずには居られない暑さです。
昔の教えが現代に全て通じるかは疑問ですが、精神の基本的部分の教訓はどんなに科学や文化が発展しても変らないと感じます。