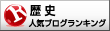「この時代の一番の発明と言ったら、このポテトチップスだな。これは、実にうめえ」
じいさんは、俺の買ってきたポテトチップスを食べながら上機嫌になっていた。
「しかも、のり塩に限る。これが一番だ。おっと、話がすっかりそれちまった。おめえもわっちのポテトチップス礼賛を聞きに来た訳じゃあるめえ。深川の河童の件に戻ってやる。騒動はまだ序の口だった。大変な騒ぎになったのは、汗ばむほとの陽気の日、暮れ六ツ近くのことが発端だ。その日は暖かだったこともあっていつもに増して河童目当ての見物人も多かった。州崎の近くはぬかるんで足場も悪かったので、その近くの土手にござを敷いて、見物人は無駄口などを叩きながら、思い思いにのんびりしていた。こっそり酒などを飲みながら見物している者もたようだが、河童が現れようと現れまいと河童見物に行くと言うこと自体が行楽だった。江戸ってのはそういう時代だった。この頃では常連の者も現れ、話もはずんでいた・・・・・」
「おっ、おめえさんも精が出るな。昨日もおとといも来てたじゃねえか」
「そういうおめえだって、暇さ加減では俺に負けちゃいねえな」
「おうよ。江戸っ子たるもんが、河童が出るかもしれねえってのに、夕方まで天秤棒担いでいるわきゃ、いけねえ」
「そりゃそうだ。でも、山の神は怒る、怒る。おかげで家じゃ酒も出しちゃもらえねえ」
「うちでも同じこった。俺は熊三だ」
「そっちが名乗りを上げたのなら、こちらも名乗ろう。拙者、神田明神下に屋敷を持つ、留助だ」
「何が屋敷だ。屋敷って顔は、してねえぜ」
年の頃にして二十代半ばの若い男二人は、親しげに笑い合った。こういう場では妙な親近感が湧くことがある。
「おい、あれを見ろ」
小太りの熊三が、道先を指さした。
「なんでえ、ありゃ」
対照的に留助は痩せている。
熊三の指さした方向には、風呂桶のようなものを天秤棒に担いだ男が二人、駕籠かきのようにして現れたからだ。二人とも反対の肩には網を担いでいた。
「見たことがあるやつだ」
熊三が言うと、
「昨日も来てた奴だ」
痩せ形の留助が答えた。
「なんでえ、そいつは」
「これかい、見てみな」
熊三の呼びかけに応えて、天秤棒の前を担いでいた男が蓋を開けた。
「魚じゃねえか。これをどうしやがる」
留助が目を見開くと、
「河童は何を食う?」
男は、落ち着いた声で逆に質問を返した。
「魚か?」
熊三には男の意図が少し分かってきたらしい。
「そうだ。河童がなぜ陸に上がって来るか? それは、川に餌となる魚が少なくなってきたからだ。敢えて危険を冒してまで上陸する必要ができた。その腹が空いた河童に大量の餌をみせてやれば・・・・どうなる?」
「食いつくにちげえねえ」
熊三と留助は声を揃えた。
「親方、こいつを早く仕掛けちまいましょうや」
今まで黙っていた後ろの男が声を掛けた。
「お、そうしよう」
男は答えたが、
「ちょっくら待ってくれ。俺は魚屋だ。どんな魚を持ってきたか、見せてくれ」
熊三は、二人を止めて桶の中をのぞき込んだ。他の見物人も興味深そうに桶の中を眺めている。
「アジにイワシ、ご丁寧なことにコイやウナギもいる。海、川両用ってことか。それにしても大層な量じゃねえか」
「河童を目の前にケチケチはしてられねえ。話は後だ。おい、仕掛けちまおう」
男二人は、川岸に桶を担いで降りて行った。
じいさんは、俺の買ってきたポテトチップスを食べながら上機嫌になっていた。
「しかも、のり塩に限る。これが一番だ。おっと、話がすっかりそれちまった。おめえもわっちのポテトチップス礼賛を聞きに来た訳じゃあるめえ。深川の河童の件に戻ってやる。騒動はまだ序の口だった。大変な騒ぎになったのは、汗ばむほとの陽気の日、暮れ六ツ近くのことが発端だ。その日は暖かだったこともあっていつもに増して河童目当ての見物人も多かった。州崎の近くはぬかるんで足場も悪かったので、その近くの土手にござを敷いて、見物人は無駄口などを叩きながら、思い思いにのんびりしていた。こっそり酒などを飲みながら見物している者もたようだが、河童が現れようと現れまいと河童見物に行くと言うこと自体が行楽だった。江戸ってのはそういう時代だった。この頃では常連の者も現れ、話もはずんでいた・・・・・」
「おっ、おめえさんも精が出るな。昨日もおとといも来てたじゃねえか」
「そういうおめえだって、暇さ加減では俺に負けちゃいねえな」
「おうよ。江戸っ子たるもんが、河童が出るかもしれねえってのに、夕方まで天秤棒担いでいるわきゃ、いけねえ」
「そりゃそうだ。でも、山の神は怒る、怒る。おかげで家じゃ酒も出しちゃもらえねえ」
「うちでも同じこった。俺は熊三だ」
「そっちが名乗りを上げたのなら、こちらも名乗ろう。拙者、神田明神下に屋敷を持つ、留助だ」
「何が屋敷だ。屋敷って顔は、してねえぜ」
年の頃にして二十代半ばの若い男二人は、親しげに笑い合った。こういう場では妙な親近感が湧くことがある。
「おい、あれを見ろ」
小太りの熊三が、道先を指さした。
「なんでえ、ありゃ」
対照的に留助は痩せている。
熊三の指さした方向には、風呂桶のようなものを天秤棒に担いだ男が二人、駕籠かきのようにして現れたからだ。二人とも反対の肩には網を担いでいた。
「見たことがあるやつだ」
熊三が言うと、
「昨日も来てた奴だ」
痩せ形の留助が答えた。
「なんでえ、そいつは」
「これかい、見てみな」
熊三の呼びかけに応えて、天秤棒の前を担いでいた男が蓋を開けた。
「魚じゃねえか。これをどうしやがる」
留助が目を見開くと、
「河童は何を食う?」
男は、落ち着いた声で逆に質問を返した。
「魚か?」
熊三には男の意図が少し分かってきたらしい。
「そうだ。河童がなぜ陸に上がって来るか? それは、川に餌となる魚が少なくなってきたからだ。敢えて危険を冒してまで上陸する必要ができた。その腹が空いた河童に大量の餌をみせてやれば・・・・どうなる?」
「食いつくにちげえねえ」
熊三と留助は声を揃えた。
「親方、こいつを早く仕掛けちまいましょうや」
今まで黙っていた後ろの男が声を掛けた。
「お、そうしよう」
男は答えたが、
「ちょっくら待ってくれ。俺は魚屋だ。どんな魚を持ってきたか、見せてくれ」
熊三は、二人を止めて桶の中をのぞき込んだ。他の見物人も興味深そうに桶の中を眺めている。
「アジにイワシ、ご丁寧なことにコイやウナギもいる。海、川両用ってことか。それにしても大層な量じゃねえか」
「河童を目の前にケチケチはしてられねえ。話は後だ。おい、仕掛けちまおう」
男二人は、川岸に桶を担いで降りて行った。