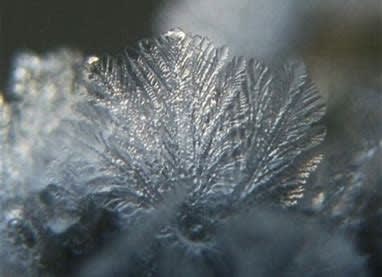枯葉踏む乳母車から降ろされて 中田尚子
よちよち歩きの幼児が「乳母車から降ろされて」、「枯葉」の上に立った。ただそれだけの情景だが、その様子を見た途端に、作者が赤ん坊の気持ちに入っているところがミソだ。おそらく生まれてはじめての体験であるはずで、どんな気持ちがしているのか。踏んで歩くと、普通の道とは違った音がする。どんなふうに聞こえているのだろうか。と、そんなに理屈っぽく考えているわけではないけれど、咄嗟に自分が赤ちゃんになった感じがして、なんとなく足の裏がこそばゆくさえ思えてくるのだ。こういう気分は、他の場面でも日常的によく起きる。誰かが転ぶのを目撃して、「痛いっ」と感じたりするのと共通する心理状態だろう。そういうことがあるから、掲句は「それがどうしたの」ということにはならないわけだ。赤ん坊に対する作者の優しいまなざしが、ちゃんと生きてくるのである。「乳母車」はたぶん、折り畳み式のそれではなくて、昔ながらのボックス型のものだろう。最近はあまり見かけなくなったが、狭い道路事情や建物に階段が多くなったせいだ。でもここでは、小回りの利くバギーの類だと、乗っている赤ん坊の目が地面に近すぎて、句のインパクトが薄れてしまう。やはり、赤ん坊が急に別世界に降ろされるのでなければ……。余談ながら、アメリカ大リーグ「マリナーズ」の本拠地球場には、折り畳み式でない乳母車を預かってくれるシートがネット裏に二席用意されている。揺り籠時代から野球漬けになれる環境が整っているというわけで、さすがに本場のサービスは違う。『主審の笛』(2003)所収。(清水哲男)
枯れし葉の終いの美学ゆうらりと たけし
南無枯葉一枚の空暮れ残り 佐藤鬼房
一葉づつ一葉づつ雨の枯葉かな 八幡城太郎
降り積めば枯葉も心温もらす 鈴木真砂女
枯葉舞ふ唐桟織の糸の艶 藤波康雄
枯葉かく人も枯葉の色に似て 中川宋淵