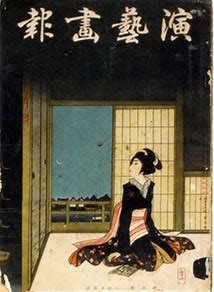何もないとこでつまずく猫じゃらし 中原幸子
【狗尾草】 えのころぐさ(ヱノ・・)
◇「猫じゃらし」
イネ科の一年草。「えのころぐさ」と読む。粟に似て小さい緑色の穂をつける。その穂を子犬の尾に擬した名。子猫をじゃらせるので、
「猫じゃらし」とも。
例句 作者
よい秋や犬ころ草もころころと 一茶
娘たち何でも笑ふゑのこ草 浦野光枝
猫じやらし臥す子の気儘すてておく 北村和子
ゑのころ草抜きざま湧くよ女知恵 手塚美佐
田の神も狗尾草も星明かり 阿波岐 滋
猫ぢやらし触れてけものゝごと熱し 中村草田男
奥伊那の日のさわさわと猫じやらし 名和未知
無住寺の門に陣取り猫じゃらし たけし
長屋門風になびかぬ猫じゃらし たけし
猫じゃらし井戸跡だけの生家かな たけし
何もないとこでつまずく猫じゃらし 中原幸子
こういうことが、私にもたまに起きる。どうしてなのか。甲子園で行進する球児のように、極度の緊張感があるのならばわかる。足並みを揃えなければと思うだけで、歩き方がわからなくなるのだ。だから、チームによっては極度に膝を高く上げて歩いたりする。普段と違う歩き方を意識することで、これは存外うまくいくものだ。しかし、一人でなんとなく歩いていてつまずくとは、どういう身体的な制約から来るのだろうか。やはり、突然歩き方がわからなくなったという意識はある。そう意識すると、今度は意識しているから、余計につまずくことになる。道端で「猫じゃらし」が風にゆれている。くくっと笑っているのだ。コンチクショウめが……。そこで、またつまずく。「猫じゃらし」の名前は一般的だが、昔は仔犬の尻尾やに似ていることから、どちらかというと「狗尾草(えのころぐさ)」のほうがポピュラーだったようだ。たいていの歳時記の主項目には「狗尾草」とある。「良い秋や犬ころ草もころころと」(一茶)。この句は、仔犬の可愛らしさに擬している。『遠くの山』(2000)所収。(清水哲男)