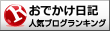群馬県黒保根、花輪村に気鋭の彫刻師がいて、
三代続いた、石原家。
初代石原常八郎、二代目石原常八主信、三代目が石原常八主利。
ほぼ一代で終わった関口文治郎の家系にない、彫り師の系図。
二代目常八主信
江戸後半、参拝者に畏敬を与える鋭利な彫りが信条。
しごかれて、江戸後期に名を遺す、
3代目常八主利が彫った鑿の跡が、
歓喜院・聖天堂(国宝)は埼玉県妻沼市👇の敷地にあります。





👇 大御所初代、石原常八郎

👇 2代目、石原常八主信

👇 左、三代目、石原常八主利

聖天堂ファイルは、👇
文治郎のデビューは、極彩色で。
👇 貴惣門(1851年完成)
この門の設計は、利根川の洪水の治水工事を請けた、
山口県の長谷川重右衛門、聖天山を見て、
熊谷の宮大工、林兵庫正清にデザインを描かせたのに、
建設費用がない。
完成したのは25年後。
宮大工担当は、元のデザインの規模を書き直した、
正清の子、正信。
斬新なデザインを彩ったのは、
3月、6キロ先の俵瀬村で荻野吟子(初の日本女性医師)の
産声オギャァ~を聞いた?11月、
三代目石原常八主利(1810~1882)、41歳の時の彫刻。
今度生まれ変わったら「宮大工」と語る吹田市の女史。
見届けたいけど、同い年。
今度生まれたら、私は「彫師」になり、
いいデザインを彩ってみたいもの。
ただし、こちとら、なまくらにして、無芸。叶うかどうか!












写真 2018.6.18 妻沼歓喜院・聖天堂