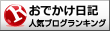粋な、縁結びの蛇の目を
ひょいと肩に置いて、
あついぞ‼熊谷
ひょいと肩に置いて、
あついぞ‼熊谷
久しぶりのリアルタイムの絵で投稿です。
29日、群馬出張合間は、
熊谷市妻沼・歓喜院へ一直線です。
29日、群馬出張合間は、
熊谷市妻沼・歓喜院へ一直線です。

荘園領主だつた、斎藤別当実盛さんが、
先祖代々の御本尊聖天さんを、
1179年にお祀りしたという伝承で、
次男斎藤六実長さんが出家して、
1197年に本坊の歓喜院を開創した由緒。
先祖代々の御本尊聖天さんを、
1179年にお祀りしたという伝承で、
次男斎藤六実長さんが出家して、
1197年に本坊の歓喜院を開創した由緒。

👆の説明の門が👇
歓喜院から20分も歩けば東国にある、
日本一の大河、あだ名は坂東太郎と、
暴れ川。
日本一の大河、あだ名は坂東太郎と、
暴れ川。
源流は群馬県みなかみ町の、
大水上山1840mで、
昔は東京湾に注いでた。
今は改良されて、鹿島灘銚子の先に轟轟と。
大水上山1840mで、
昔は東京湾に注いでた。
今は改良されて、鹿島灘銚子の先に轟轟と。

👆の門をくぐって一枚。

日本一の酷暑地帯の12時30分、
これから小一時間、暑気当たりしないよう、
まず、腹ごしらえ。
👇千代桝さんで・・・。
まず、腹ごしらえ。
👇千代桝さんで・・・。
明治の小説家、群馬、館山生まれの、
田山花袋さんが、歓喜院を見学した後、
思いとどまり
逗留して後日、書き上げたのが「残雪」
田山花袋さんが、歓喜院を見学した後、
思いとどまり
逗留して後日、書き上げたのが「残雪」

👇1894年に建てられた仁王門、



👇極彩色の歓喜院は、
どれだけ金を使ったかと思わせる豪華さ。
使ったのは昭和の官吏官で、
平成15年から23年の8年をかけ、
保存修理に彩色を加えて、
およそ13億円余り。
使ったのは昭和の官吏官で、
平成15年から23年の8年をかけ、
保存修理に彩色を加えて、
およそ13億円余り。
江戸中期、
歓喜院を落成させるまでは、庶民が、
奔走してお金をかき集め、その期間は40数年、
着工してしてからも庶民の努力があって、
25年目の落成は1760年です。
当初は、白木のままの社殿。
腕のある彫り物師を、束ねたのは、
群馬の石原吟八郎さん、完成待たず、
病気になり、使いっ走りの、
関口文治郎さんが、現地に残り、
吟八郎さんの後を継いだ。
群馬の石原吟八郎さん、完成待たず、
病気になり、使いっ走りの、
関口文治郎さんが、現地に残り、
吟八郎さんの後を継いだ。
文治郎28歳。






今日1日は、4回目のワクチン接種で
暑さと接種の障害が出たら
困るからと言われて
老人扱い、明日、明後日は自宅待機
暑さと接種の障害が出たら
困るからと言われて
老人扱い、明日、明後日は自宅待機
今回、歓喜院に飛んだ
話は明日に・・