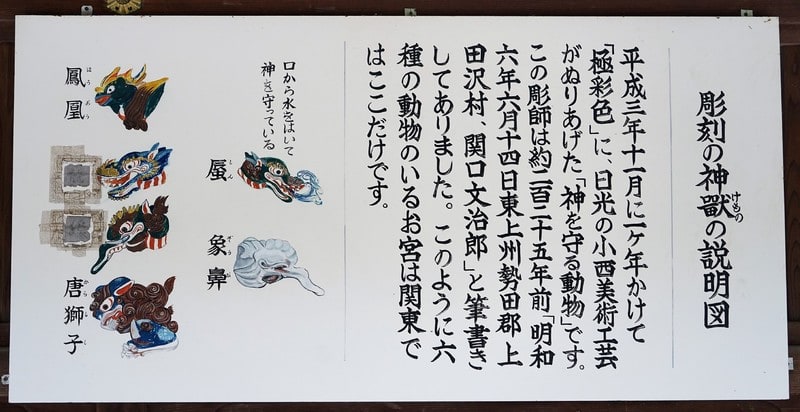向日葵は、太陽を追いかけるけど
今、あしたも、明後日も、太陽は隠れてほしい!
「外に出るな」と、忠実に忠告を守れば、
1メートル四方で、頭カキカキ!
食事は喉を通らず、すきっ腹、
暑さの八つ当たりする物もかすみ、
外の景色を眺める勇気も湧かない。
ただ、ただ、涼しくても気分はぐったり。
群馬、赤城山に登る道、苗ケ島に金剛寺があって、
1761年前橋の大火で延焼した後、建てられたお寺。
地元で育った侠客「大前田栄五郎」の菩提寺でもあるけど、
1771年、文治郎は息子千治と松治、星野新次郎、黒田喜太郎らは、
檀家が造った、掘っ立て小屋に着く。
赤城山から流れる沢の水音は、
禊をしてから鑿を入れる文治郎をいい気分にさせる。
完成した1773年、8つの欄間は、
中国の故事、唐子遊びを題材にしたもの。
息子千治と松治は、仕出として使い走っしり。
43歳、関口文治郎有信は御公儀御棟梁の肩書を持っている。










天井の花鳥図は、前橋藩士であり又御抱画師、
森東渓の次男、森霞巌の筆👇








写真 2018.7.16 前橋・金剛寺 ※花は別な日