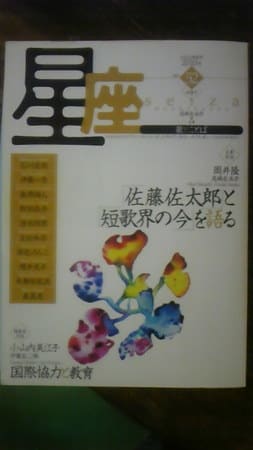「かりん」の小高賢が亡くなった。「批評の不在」を初めて発言したのは小高だった。
「永井祐の作品のどこがいいのか誰か説明しないか。」という言葉だったと記憶している。永井祐の作品は、短歌総合誌の端々、「塔短歌会」の全国集会での高野公彦の講演、加藤治郎のフェイスブックのタイムラインで、見かけた、
僕も永井祐の作品のどこがいいのか分からない。
・あと五十年は生きてくぼくのため赤で横断歩道をわたる 『日本の中で・・・』
この作品は高野公彦が批判した作品だ。(「塔短歌会」全国集会の講演)この場でもう一首紹介された。
・タクシーが止まるのをみる(123 4)動き出すタクシーをみる 『同』
この作品を高野公彦は、苦しい解釈をしていた。「大きな声では、言えないが。」と言いながら。批判が遠慮がちなのだ。
また、加藤治郎のフェイスブックには、永井祐の作品を「現代の秀歌」として紹介して、「このポエジーが、一般の読者に伝わるだろうか。」とコメントしていた。
僕が「この作品のどこにポエジーがあるのですか?分かりません。」とコメントしたところ、「岩田さん。分かりませんか?」とコメントされていた。僕は「はい。」とだけ答えたがそれっきり加藤治郎は答えなかった。
穂村弘にも同様の傾向がある。穂村弘がしばしば用いる言葉に、「ここに詩がある。」というのがある。ところが穂村弘が、「詩とは何か」を論じているのを、ついぞ見かけない。
ここで思い出すのは、安土桃山時代の、呂宗助左衛門と千利休の逸話だ。呂宗助左衛門が、東南アジアから持ち帰った、二束三文の壺に、千利休が、豊臣秀吉の前で高値を付けた。諸大名は先を争って、高値で買い取った。
若手歌人の作品を、穂村弘が「ここに詩がある。」と言い、加藤治郎が「ポエジーがある。」と一言言えば、その若手は、たちまち有望若手歌人となる。歌壇でこんなことが、起こってはいないだろうか。
2015年「角川書店新年会」で、馬場あきこが、受賞者の、谷川電話に辛口の言葉を言い、尾崎左永子が『佐太郎秀歌私見』(角川学芸出版)のなかで、「ツイッター的短歌が歌壇の主流を占めるのは、座視できない。」と述べ、岡井隆が「もはや俵万智の時代ではない。」と『短歌』誌上で発言しているのも、こういう事を危惧しているのだろう。
永田和宏著『近代秀歌』『現代秀歌』(岩波新書)を読んだ。いずれこのブログの書評を書くつもりだが、『近代秀歌』の豊かさに比べると、『現代秀歌』の方は、いかにも不作であると思う。『現代秀歌』では100人の歌人の作品を採り上げているが、これという作品は、三分の一の33人に、大きく及ばない。
とくにライトバース、ニューウェーブ前後からの、歌人の作品は目を覆いたくなる。
大きな賞を受賞した著名歌人でも失敗作は失敗作だと思うのだが、いかがだろうか?