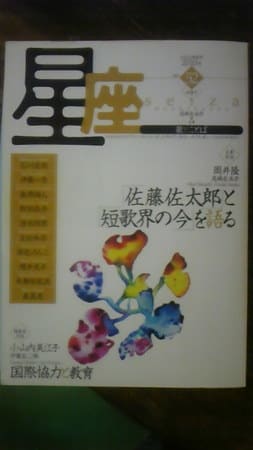「ブナの木通信」「星座66号」
今年の冬は記録的な豪雪など、一段と厳しいものでした。そのためか、今号には季節感のある叙景歌が多かったように思います。季節感は多くの人が感じますから、どこをどう切りとるかに作者の独自性が出て来るとおもいます。
(ビルの窓を蔓薔薇が覆う歌)
(深々と降り積む雪の歌)
絵画も俳句も短歌も「写生」は地方から始まったとされますが、都会には都会の自然があり、それをどう詠むかが問題でしょう。
(二月の寒さの厳しさにカレンダーを割く歌)
カレンダーを割いても、寒さが凌げる訳ではないのですが、何とか凌ごうという意思が、結句の作者の所作で分かります。
(降り積もる雪を懐かしむ歌)
どういう想いか明示されていませんが、暗示にとどまっているところが、逆に作品に広がりを与えました。
(日当たりのよい土の暖かき黒さの歌)
結句の「土の暖かき黒」によって、却って雪の冷たさが印象深く表現されています。
(冬晴れの空に飛行機雲が山を射る歌)
この作品の魅力は何と言っても下の句のインパクトのある表現でしょう。
(春疾風に白梅が散る歌)
冬が厳しいだけ、春を待ちこがれるものですが、やっと咲いた梅の花も「春の嵐」によって散ってしまう。自然の摂理をよく捉えられました。
(山繭に会う歌)
(幽かに梅の花が咲く歌)
(闇の夜の豪雨の歌)
これらも佳詠です。最後に二人の歌人の言葉を御紹介しましょう。
「写生を貫いてゆけば、象徴、幻想にはおのずから達する。」(斎藤茂吉)
「目に見えるものを映すことによって、作者の心情も映すことになる。」(岡井隆)