小名浜の「いわき・ら・ら・ミュウ」に立ち寄った折、
海を見ようと2階に上がり「いわきの東日本大震災展」に出会った。
そこは、2011年3月11日、あの日何が起こったのか記録されたコーナーだった。

展示のタイトルにもある言葉は深く心に刻まれた。
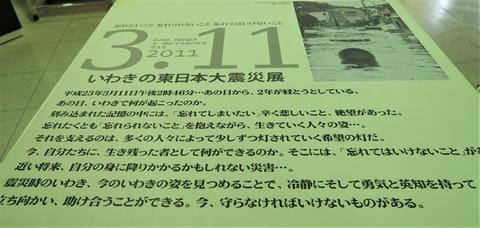
忘れたくとも「忘れられない」ことを抱かえながら 生きていく人々の姿・・・。
それを支えるのは、多くの人々によって少しずつ灯されていく希望の灯だ。
今、自分たちに、生き残った者として何ができるのか。
そこには「忘れてはいけないこと」がある。
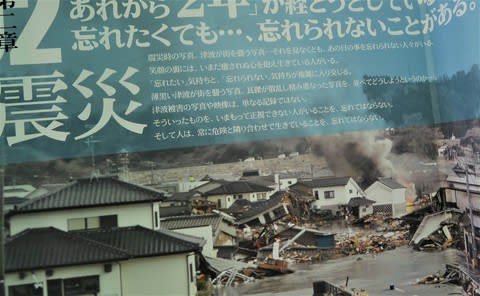
展示はあの日の悪夢の記録、しかし未来への警鐘。
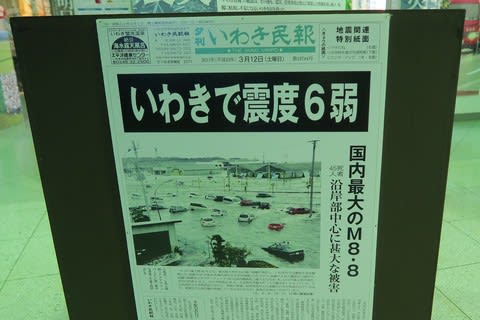
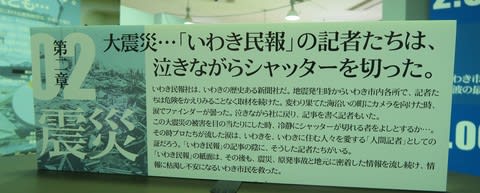
避難所の段ボールで間仕切りしたスペースが再現されている。
そばにいた女性が話してくださったのは、
「うちの娘も避難所にいたけれど、ブルーシート一枚で段ボールすらなかった」と。

床で食べる非常食・・・

今、平和な日々を当たり前と思って生活している私たち、
この東日本大震災の教訓を忘れてはいけないのだと
改めて強く感じました。
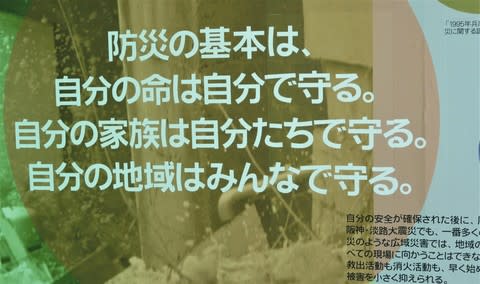
この展示は、いわきの人々ではなく、
震災から遠く離れた人々が見るべきだと思います。

震災と津波で壊滅的な被害を受けた町、

この日の小名浜港は、
あの暴れた海と同じなのかと信じられないほど、静かに青かった。

あの日、私は車で震災を知り、すぐ娘のアパートに駆けつけた。
2歳と生まれて2か月の孫たちを抱いて、鳥肌のたつような映像を見ていた。
自分ならどうしただろう?
想いは前に進まず、自分には及ばないだろうと避けている私がいる・・・。
しかし、災害はいつどこで起きても不思議ではないこと。
「忘れてはいけない」このことを心に刻む旅でした。













































